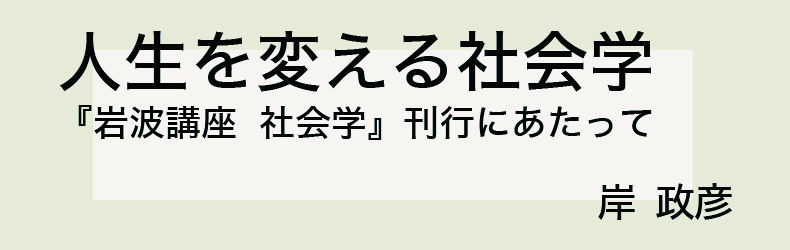岸 政彦 人生を変える社会学──『岩波講座 社会学』刊行にあたって
このたび、『岩波講座 社会学』が正式に刊行開始となりました。前回の「岩波講座」からほぼ30年経つ。私のほかに、北田暁大、筒井淳也、丸山里美、山根純佳の各氏が全体の監修を務め、テーマごとに編集される全13巻の各巻に、そのテーマに造詣が深い社会学者が編者になります。
前回の「岩波講座」が刊行されたときは、たしか私はまだ院生でした。貪るように読んだことを覚えています。あれから社会も、社会学も、大きく変化しました。
前回は上野千鶴子や吉見俊哉、大澤真幸などが全体の監修者で、巻数も26あったと記憶しています。各巻のタイトルも凝ったものが多かった。執筆者も社会学プロパーだけでなく、竹田青嗣などの周辺領域の方が入っていました。文体や内容も派手で、自由で、雑多で、それほど社会学とは関係のないものもたくさんありました。もちろんそれだけではなく、当時の最先端の社会学的な議論をしている論文もたくさんあって、たとえば落合恵美子が実証的な観点から上野千鶴子を強く批判する論文なども収録されていたのですが。
そのころから比べると、社会学も大きく変わりました。どちらかといえば、より地味な、地道な、実証的なスタイルで調査研究をおこなう社会学が求められるようになったのです。今回の『岩波講座 社会学』では、そうした社会学者が中心となって執筆します。特定の対象と特定の問題に、特定の理論と特定の方法を携えて実直に調査研究を続けるような、そんな社会学者たちはこれまでたくさんいたし、いまもたくさんいます。いま、この社会にとってほんとうに必要なのは、「職人的」な社会学者なのです。
要するに、この講座のシリーズ全体でおこなうのは、社会学そのものの再定義です。もっといえば、これは「本来の社会学」へと立ち戻ろうとする試みです。社会学者は、大風呂敷を広げた預言者であってはならない。私はすでに、2018年に有斐閣から出版された『社会学はどこから来てどこへ行くのか』という対談集で、そのような趣旨のことを述べています。
目次に並んだ150名ほどの社会学者はみな、非常に洗練された理論や方法を駆使して、それぞれのテーマと対象に深く切り込んでいます。国際的に活躍している社会学者も多い。この新しい『岩波講座 社会学』は、非常にレベルの高い論集になるでしょう。「講座」とうたってはいるが、むしろこのシリーズは、参加するそれぞれの社会学者がそれぞれの最新の研究成果を盛り込んだ「論集」とでもいうべきものになります。
そしてもうひとつ、ここで述べたいことがあります。それは、「私たちはどうやって社会学と出会うのだろう」ということです。社会学でなくても、人類学、哲学、歴史学、政治学というものと、私たちはどのようにして出会うのでしょうか。それは、本というものを通じてではないでしょうか。こう書いてしまうと、とてもありきたりな、当たり前のことを言っているようにみえますが。
たとえば、この『岩波講座 社会学』に収められた、あるいは収められる予定の論文はどれも、現代の社会を生きる私たちの、切実な問いに答えようとするものばかりです。辺野古や釜ヶ崎で何が起きているのか。地方の過疎化はどうすればよいのか。移民をどのように包摂できるのか。AIと倫理、教育におけるジェンダートラック、原子力災害と地域振興、ポルノグラフィと表現の自由、長時間労働や非正規雇用の問題、ホームレスという人生、家族構造の激変、社会的養護の家族化、地方のノンエリート青年たちの進路、メディアと自己、ネットのナショナリズムとヘイト……。こうしたさまざまな問題に、社会学者たちは取り組んでいるのです。本講座には、これらのテーマに深く切り込んだ論文が多数収録されています。
この時代に、そもそも「講座」という形態で、全13巻もの続きものの本を出版する意味は、どこにあるのでしょうか。
社会学も、そして大学という場所も、いままさに大きく変わりつつあります。とくに大学には、もう自治や自由はありません。私たちは常に、英語で査読論文を書き、わかりやすい成果をあげ、膨大な書類を書き、外部から自力でわずかなカネを取ってくることを求められているのです。そして、「本」というものが業績としてどんどん認められなくなってきています。国際的なジャーナルに英語で論文を書かないと(それはそれで大事なことですが)業績としてカウントされないのです。こうして、本というものを書くモチベーションが、どんどん失われつつあります。
一方で、社会学に興味を抱き、社会そのものにも燃えるような知的関心を抱いて、大学院に進学する学生さんはたくさんいます。さらに、幸いにも、私たちが書く社会学の本も、「飛ぶように売れている」とはとても言えませんが、それなりの数の読者がいます。「社会という謎」に好奇心を抱くひとは、思いのほか、多いのです。そうはいっても、上記のような大学を取り巻く状況を考えると、これからもたくさん本が出版され、そしてそれを読んで社会学や哲学に興味を持つ学生がたくさん出てきてくれるかは、とても心配で、心細いです。社会学や人類学や哲学に興味をもつ若いひとをどのように増やすかは、私たちにとって共通の、深刻な課題なのです。
私たちはいつ、どこで、どのようにして、社会学や人類学、哲学や歴史学と出会うのでしょうか。どうやって、誰の影響で、社会そのもの、歴史そのもの、そして人間そのものについて書かれた「難しい書物」を手に取ろうと思うのでしょうか。レヴィ=ストロースやラカン、ハバーマスやハイデガー、フーコーやハッキング、ウィトゲンシュタインやブルデューに、いつどのようにして出会うのでしょうか。
たとえば、中学生ぐらいでいろいろな本を読み出して、ジェンダーやセクシュアリティ、あるいは戦争や貧困や差別という社会問題に興味が出たとき、ひとはどうするでしょうか。どうしてこんなくだらない規則が多いのか、どうして女子ばっかり外見で判断されるのか、どうして受験で人生の大半が決まってしまうのか。こういう問題に「目覚めた」ときに、ひとはどうするでしょうか。CiNii や Google Scholar でキーワードを入れて論文を検索するでしょうか。絶対にしないと思います。というか、CiNii や Google Scholar の存在さえ、普通のひとは知らないと思います。
言うまでもない、当たり前の話ですが、私たちはそういうものと、書店で出会うのです。ほぼ全員がそうだと思います。
私自身、80年代から90年代にかけての大阪の書店で、そういう本とたくさん出会いました。いまでも、曽根崎の旭屋書店(もうなくなってしまいましたが)の狭い階段や本棚をよく覚えています。紀伊國屋書店梅田本店(こちらはいまでも賑わっています)にもよく行きました。そういうところで、岩波書店やみすず書房、筑摩書房から出ている、なにやら難しそうな本を手に取って、ページを開き、そして人生が変わってしまいました。小さなころから『ドリトル先生』や『西遊記』や『オリバー・ツイスト』など、たくさんの本を読んでいましたが、学生のころに書店で出会った本たちは、分厚くて難しくて字がいっぱいで、まるでひとが登ることを拒否する山のようでした。でも私は、そんな険しい山にむしろ憧れて、いろんな書店に何度も通ったのです。そういう出会いを、次の世代の人びとにも経験してほしいと思っています。
この講座も、たくさんの書店の棚に、たくさん並んでほしいと祈っています。書店というものは、不思議な、奇妙な、そして素晴らしい空間です。みんな静かで、ひとりで、誰とも目を合わせない、しんとした場所ですが、そこにはたくさんの「人生を変える出会い」が並んでいるのです。
この時代に「本」というかたちで『岩波講座 社会学』を刊行する意味がここにあると確信しています。私自身が人生を変えられた社会学というものの面白さと切実さを、次の世代の人びとにも体験してほしい。私自身が人生を変えられたように、日本中の書店で『岩波講座 社会学』と出会って、人生が変わってしまうひとがたくさん現れますように。そんな願いをこめて、このシリーズを刊行したのです。
繰り返しますが、社会学はほんとうに変わりました。それも、とても良い方向に変わりました。一見すると地味で地道ですが、人びとが人生において出会うさまざまな問題に正面から向き合ったこの『岩波講座 社会学』は、手に取ったひとの人生を変える力を持っていると確信しています。たくさんの方に読まれることを願っています。