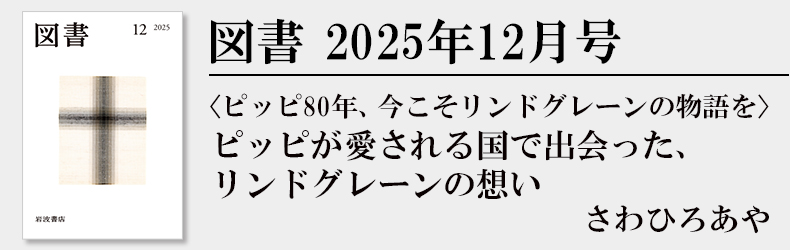さわひろあや ピッピが愛される国で出会った、リンドグレーンの想い[『図書』2025年12月号より]
ピッピが愛される国で出会った、リンドグレーンの想い
今年5月末、週末と祝日を利用して、スウェーデン・ストックホルムの友人を訪ねた。私が暮らすデンマーク・コペンハーゲンから列車で約5時間北へ向かう旅だ。列車の窓から外を眺めると、からりと晴れた空に新緑をまとった木々、その奥からちらちら顔をのぞかせる湖面が通り過ぎていく。初夏の美しい風景に身をゆだねながら、私はかつてこの二つの都市を何度も行き来した、ある女性に思いを馳せていた。
『長くつ下のピッピ』をはじめ数多くの作品で世界にその名が知られる児童文学作家、アストリッド・リンドグレーン。彼女の存在を初めて強く意識したのは、ある夏の日のことだった。デンマークの児童図書館で司書として働く私は、夏の休暇を利用し、家族とともにスウェーデンのスモーランド地方にあるリンドグレーンの生家と博物館を訪れた。そこに展示されていた一枚の写真の前で、私は思わず立ち止まった。そこには、小さな男の子と並んでベレー帽をかぶり、少しだけ微笑むリンドグレーンの姿があった。写真の下には小さく「息子のラッセは3歳になるまでコペンハーゲンの養母に預けられ、19歳で母となったアストリッドは息子に会うために何度もコペンハーゲンへ通った」という言葉が添えられている。なぜ、幼い子を3年間も隣国の遠い街に預けなくてはならなかったのか、その理由がとても気になった。
リンドグレーン博物館を訪れた後、コペンハーゲンへ戻った私は、彼女の生涯を綴った伝記(Denne dag, et liv by Jens Andersen, 2014, Gyldendal 〔『この日、人生そのもの』イェンス・アナセン著、未訳〕)を読み始めた。のどかで牧歌的なスウェーデンの子どもたちの物語を描く作家と、10代で未婚の母として幼子を異国に預けていた女性という二つの現実がうまくかみ合わず、とにかく詳しい事情を知りたかったからだ。伝記には、17歳で働き始めた地元の新聞社の上司で、父親ほど年の離れた既婚男性の子を身ごもったこと、小さな田舎町でうわさになることを恐れストックホルムへと移り住んだこと、そして中絶が当時のスウェーデンでは違法であり、極秘に出産するために、臨月にたった一人でコペンハーゲンへ来ていたことが記されていた。
出産してからの3年間、リンドグレーンはわが子に会うため、年に何度も夜行列車と船を乗り継ぎ、ストックホルムからコペンハーゲンへと通ったという。妊娠、出産に際し孤独や困難を抱えながらも、息子を想う気持ちが彼女を支え、幾度もその旅へと向かわせた。
だが3年と少しが経った頃、養母が病に倒れる。ここからリンドグレーンの人生がまた動き始める。養母は彼女に、息子を引き取り、自身で育てることを勧める。「もう寂しい子にしないであげて。」そんな養母の言葉に導かれるように、リンドグレーンは、狭いストックホルムのアパートに息子を引き取る覚悟をする。
初めて息子と二人きりで過ごした夜のことを、彼女はのちに自身の言葉でこう記している。
「ラッセ(息子の名前)は(養母のもとで暮らすという)自分が思い描いていたことが、もう何もかもちがうこと、それがかなわないことに気づいたようでした。そして椅子に突っ伏して、静かに泣きました。本当に静かに。ああ、もう大人はぼくを好き勝手にするんだと悟ったようでした。その泣き声は今も私の心の中にありますし、ずっと消えることはないでしょう。もしかしたら、その泣き声が私にあらゆる面で子どもの味方をさせているのかもしれません。」(養母の家族に宛てた手紙より。『この日、人生そのもの』、111頁。( )は筆者による補足)
未婚女性がひとりで子どもを育てることが社会的にも非常に困難であった時代、コペンハーゲンの養母のもとで息子が健やかに育つことを、リンドグレーンはひそかに願っていたのかもしれない。だが養母の病をきっかけに、自分が息子を引き取り、育てていかねばならないのではという不安がよぎる。そしてこの夜、初めて息子と二人きりの時間を過ごしながら、彼女は、もっとも大きな不安を抱えているのは自分ではなく、むしろ息子であることに気づく。
孤独と不安、寂しさ、また子どもであるがゆえにどうすることもできない無力感──この時、息子ラッセが抱えていた声にならない悲しみは、この日以降、リンドグレーンの心に消えることなく残り続けた。そして「あらゆる面で子どもの味方でありたい」という決意が、その後の彼女の作品の原点となった。
リンドグレーンが子どもの味方であることは、彼女の代表作、『長くつ下のピッピ』からもうかがえる。
自立心旺盛で世界一力持ちな女の子ピッピは、たくさんの金貨を自宅にもっていて、孤児というイメージとは対極的な、明るく自由奔放で、これ以上ないほど愉快な存在として描かれている。
ピッピの日常や言動には、子どもならだれもが一度はやってみたいと思うようなワクワク感があふれている。それはきっと、普段は大人から「してはいけない」と止められていることと重なるからだろう。大人が決めたルールのなかで暮らしている子どもたちにとって、ピッピのもつ圧倒的な力と自由はまるで夢のようであり、大きな憧れでもある。ピッピの姿に自身を重ね、「もし自分にもこんな力や自由があったなら」と願いながら、物語を通じてその生き方を追体験しているのではないか。
だがピッピは「強くて自由な女の子」という側面だけにとどまらない。隣家に暮らすトミーとアンニカとともに訪れたお菓子屋さんで、ピッピは自分が大量に買い込んだお菓子(18キロ!)を、店先で羨ましそうに見つめる子どもたちに惜しみなく分け与える。また自宅の金貨を狙って泥棒がやってきたときには、ただやり込めるだけでなく、「おなかが空いてるでしょう?」と食事までふるまう。ピッピは力強さや奔放さだけでなく、人に寄り添うやさしさももつ存在として描かれている。
そんなピッピの物語は、デンマークで多くの人々に愛されている。『長くつ下のピッピ』は、出産祝いや洗礼式の贈り物として現代でも根強い人気があり、女の子だけでなく男の子にも贈られている。作品から引用される言葉も多く、なかでもよく見かけるのは、絵本版にある「とってもつよい人は、とってもやさしくなくちゃいけない」という言葉だ。自分の意志を貫き、自由に生きるピッピは、他者へのやさしさも忘れない。その強さとやさしさを併せもつ姿は多くの人に「こうありたい」と思わせるもので、デンマークの人々はそんなピッピの姿に、人としてあるべき姿を重ねてきたのだろう。
デンマークの児童図書館や児童書専門店で、私はこれまで多くの人々にリンドグレーンの作品を手渡してきた。子どもの頃に読んだ彼女の作品を、自分の子どもにも読んで聞かせたいという思いとともに図書館や書店を訪れる人は少なくない。その人気の高さや根強い支持にふれるたびに、この作家がただ者ではないことを感じてきた。
そんな経験を重ねるうちに、さらに気づいたことがある。それは「子どもの味方でありたい」と願うリンドグレーン自身の信念と、デンマークの人々が大切にしている人としての生き方、あり方がピッピの描かれ方と重なるだけでなく、ピッピの物語に込められたメッセージが、人々が戦後の社会で重視してきた価値観とも呼応しているのではないかということだ。
『長くつ下のピッピ』は第2次世界大戦が終わったその年にスウェーデンで出版され、翌年にはデンマークでも翻訳版が刊行された。戦後のこの時代、北欧の人々は民主的な社会を築いていく過程で、権力が独り歩きしないよう注意深く目を光らせながら、自由で平等な社会を作っていこうという連帯の精神を培ってきた。だが権力というものは放っておくとすぐに芽を出し、人々の心を支配しようとする。9歳の女の子ピッピの奔放な言動は、そうした見えにくい権力の芽生えに光を当て、時に痛快に笑い飛ばしながら、自由で平等な社会を作っていくとはどういうことかを深く問うてきたのではないか。
ピッピは警官や学校の先生、サーカスの団長など、いかにも大人社会の権威を象徴するような存在を軽々と打ち負かす。だがそれはただの力比べではない。大人たちが当然のように振りかざす権威や秩序に対し、ピッピは「それって必要なの?」と問い直す。これは一種の風刺ともとらえられる。こうしたピッピの姿勢が、戦後、民主的な社会を築いてきたデンマークの人々のあいだで、広く共感を呼んできたのだろう。「強くてやさしい」ピッピのあり方は、力をもつ者が弱い立場の人々を支え、寄り添う存在であることを示しているとも言える。だからこそ、ピッピの物語は、子どものための楽しいお話であることを超えて、人々がこの社会を共に生き、築いていくための哲学として子どもたちに手渡されるのだろう。デンマークの人々は『長くつ下のピッピ』に、こうした深い考えを読み取っているように私は感じている。

春の暖かな光に包まれた5月のストックホルムでは、今年80周年を迎えた『長くつ下のピッピ』が、生まれ故郷の児童図書館や書店の一角を鮮やかに彩っていた。
『長くつ下のピッピ』以降、数多くの作品を世に送り出したリンドグレーンは、創作活動にとどまらず、生涯にわたり子どもや弱者の味方として声を上げ続けた。1978年にドイツ書店協会の平和賞を受賞した際、子どものしつけに暴力は不要であることを力強く主張したスピーチ、『暴力は絶対だめ!』は、日本でもよく知られているだろう。また、スウェーデンで何年も暮らした末に滞在を拒否された難民の子どもたちの問題にも、メディアを通じ社会に問いを投げかけた。わが子が静かに流した涙をきっかけに芽生えた、「あらゆる面で子どもの味方でありたい」という彼女の願いは、生涯変わることなく貫かれた。
リンドグレーンのこうした願いを、現代を生きる私たちは今どれほど実現できているだろう。平和で民主的な未来を築いているはずだった私たちは、今も子どもたちを戦禍や暴力の犠牲にしている。80年の時を経て、リンドグレーンが伝え続けた「子どもの味方でありたい」という願いは、今改めて問いを投げかけている。私たちは子どもたちの悲しみや孤独に寄り添えているだろうか。かれらの声に耳を傾けられているだろうか。ピッピの声は私たちに「あなたは、力をもつ大人として子どもたちに寄り添い、かれらを守り、希望を届けられていますか」と問いかけているようにも感じられる。
私たちはリンドグレーンが信じた、自由で平等であたたかな世界を築いていけるだろうか。ピッピとリンドグレーンの声は、私の心に響き続けている。
(さわひろ あや・デンマーク児童図書館司書)