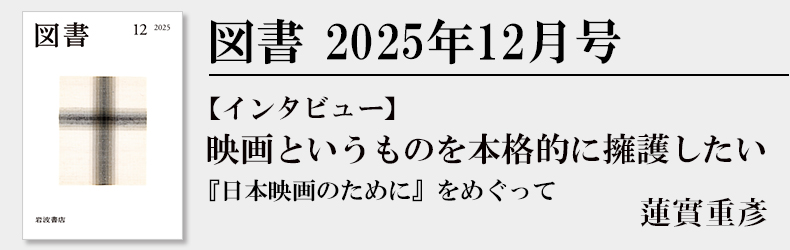蓮實重彥 【インタビュー】映画というものを本格的に擁護したい[『図書』2025年12月号より]
映画というものを本格的に擁護したい
『日本映画のために』をめぐって

内田吐夢とラオール・ウォルシュ
──今日は新著『日本映画のために』をめぐって著者の蓮實重彥さんにお話を伺います。本書は企画から約30年の時を経て刊行されました。蓮實さんは近年では『ショットとは何か』三部作(講談社)や『ジョン・フォード論』(文藝春秋)など映画ファンを魅了する著作を発表されていますが、初の日本映画論集となる本書刊行の経緯からお聞かせください。
蓮實 ご紹介のように企画そのものはかなり以前に遡るわけですが、一冊の書物として出すにあたり、わたくしがどうしても必要だと考えていたものが内田吐夢論だったのです。今回の内田吐夢論(「内田吐夢論──またはその画面を彩る慎ましい顕在性をめぐって」)は、ある意味、わたくしの晩年の仕事といってよいものです。それは、『ショットとは何か 歴史編』に収められているラオール・ウォルシュ論(「ラオール・ウォルシュ または「伝説」と「現実」を超えて」)に対応するような形で書かれている。ウォルシュも世界一の監督である。ところが世間的にはさほど評価されていない。そのことをなんとか正したい。その思いから、ラオール・ウォルシュ論を『ショットとは何か 歴史編』で書きました。
今回、それとほとんど同じくらいの熱量と時間とを掛けて、内田吐夢論が書けたのではないかと思っております。『日本映画のために』の内田吐夢論をお読みになった読者は、ぜひ『ショットとは何か 歴史編』のラオール・ウォルシュ論も読んでいただきたい。ラオール・ウォルシュ論をお読みになった読者も、内田吐夢論をぜひお読みいただきたい。それが、蓮實の晩年の仕事の一環であるとご理解いただければと思います。
──書き下ろしの「内田吐夢論」がなければ『日本映画のために』もなかったということですね。著者としては、内田吐夢だけでなく、日本映画史で過小評価されてきた映画作家や作品について黙っていられないという思いが強かったと。
蓮實 はい、それはありました。もう少しわたくしに時間的な余裕と心の余裕があったなら、それにふさわしいものをもっと探し出して本に入れることができたかもしれません。たとえば田中徳三についてだとかマキノ雅弘についてだとか、好きな映画はたくさんありますから。
──巻頭「「日本映画」のために──序文に代えて」では、「網羅性からは思いきり遠い書物」だと書いておられます。網羅性を前提としないとはいえ、取り上げたい主題はまだ多々あったと。同じ映画作家でも、代表作とされているものとは別の作品を取り上げたいということも?
蓮實 そうですね。やはり『高原の駅よ さようなら』でなければ中川信夫はだめだ、ということは絶対に言いたかった。
──序文では、三隅研次監督の『座頭市 血煙り街道』(1967年)、中川監督の『高原の駅よ さようなら』(1951年)、伏水修監督の『東京の女性』(1939年)、この3作品の素晴らしさが語られます。
蓮實 『東京の女性』についてはヒロインの原節子をほとんど無視しております(笑)。しかし、伏水監督にこれまで触れた人はほとんどいないでしょう。
──今回のご本を契機に注目されるのではないでしょうか。
蓮實 そうなってほしい。『東京の女性』は先輩(ジャズ評論家の故瀬川昌久氏)から教えられた映画ですが、見たら本当にびっくりしました。撮れてるんですよ。それで瀬川さんと一緒に伏水監督の作品を探したら、これがけっこうあった。
「黄金時代」?
──本書では北野武、黒沢清、濱口竜介といった1990年代以降の「第三期黄金時代」の作家たちが論じられる部分も読み応えがあります。巻末には三宅唱監督との対談、小田香・小森はるか両監督との鼎談もあり、いま脂の乗りきっている映画作家たちに光が当てられます。
蓮實 ただ、そもそも「黄金時代」などということを、とりわけ問題にするには及ばない。優れた作品が、ある一定の期間、ほとんど定期的に撮られていればいいだけのことで、1930年代、50年代といった黄金時代というものを強く主張したいわけではなかった。にもかかわらず、現在こんなものがあるじゃないか。小田香はどうだ。大九明子はどうだ。それから、もう世界的に認識されているけれども三宅唱はどうだと。三宅唱は、その初期から、わたくしは絶対にこの人は世界でも成功すると信じていました。そしたら『旅と日々』がロカルノ映画祭で金豹賞をもらってしまう。これは愉快でしかたない……、もう(笑)。
また、わたくしが立教大学で教えた人たちが世界的に活躍してくれた。こんなに幸福な大学の教師っているのかなと思うぐらいです。彼らは裏切らなかった。黒沢さんにしても、青山真治にしても、裏切ろうとする気すらなく、好きなものを自在に撮っているうちに、世界が彼らを認めた。『EUREKA ユリイカ』(青山監督、2000年)なんて、こんなものを世界で見てくれる人がいるんだろうかと思ったら、いたわけじゃないですか。
これが映画だ、とわたくしが思っていたものが明らかに世界的に通じるものになったということで、たいそう嬉しく思っています。ですから黄金時代とかそういうことは、とりわけ問題にするには及ばない。いいものはいいんだと。それが現在も途切れていないということが肝心なのです。わたくしとしては、どうだ、彼ら彼女らのことを気をつけていた自分は間違いではなかったと自分に言い聞かせられると同時に、ほれみろ!彼ら彼女らはすごいじゃないかと言える。
──三宅さんの最新作『旅と日々』はご覧になりましたか。
蓮實 見ています。これについては、ある種わたくしの呪いというようなものがないわけではない。2時間20分とか2時間半の映画が一般化されているかに見えるときに、1時間半ではっきり終わる映画を撮らなければいけない。そういう強い意志がわたくしのなかにありました。彼がその夢を実現してくれてたわけです。90分で終わっちゃう。まあわたくしの呪いかどうか知りませんけれど(笑)、90分、90分と言ってきたことに対して、彼がそれを実現してくれた。しかも旅の映画でありながら人の移動をほとんど描いていないという、この素晴らしさ……。
──たしかに1時間半で終わる日本映画は最近あまりないかもしれませんね。
蓮實 ないです。みんな2時間20分。
──『旅と日々』は89分です。
蓮實 三宅さんと一緒に『ジョン・フォードと投げること』を編集したときに、絶対に59分で仕上げようと言ったんです。そしたら彼は本当に59分58秒に収めてくれました。
音声と色彩
──話題は変わりますが、日本の場合、映画が音や色を獲得したことで、何か本質的に変わったことはあったのでしょうか。
蓮實 トーキーへの移行に関しては、それは残念ながらなかったと思っています。むしろ、彼らがごく自然にサイレントからトーキーに移行したということの方が驚きでした。小津は多少ともギクシャクした面があったとは思いますが、溝口なんか見事に撮っちゃうわけです。すると、彼らはやはり映画作家だと確信せざるをえない。音があろうがなかろうが、現実をどのように取り込むかということに関して決して間違わなかった。そういうことだと思いますね。まあ成瀬巳喜男が一番自然かなという気がします。音がない時代から、音をもつに至ったという点に関して言えば。
山中貞雄もごく自然でした。山中は、トーキーなのに無言のショットを撮れる人でした。『河内山宗俊』で、原節子のところに子供が買い物に来て、原節子が飴か何かを売ってやると、雪が降り始めるシーンがあります。あそこなど、ほとんど台詞はないのに、あたかもトーキーのようだ。それは伴奏音楽によるものですが、そういうところのうまさは、やはりよく映画を見ていたからだとしか言えないでしょう。
──蓮實さんが最初にご覧になったカラーの日本映画は何でしたか。
蓮實 ほとんど憶えていません。気づいたらカラー映画になっていたというほうが正しいでしょうね。日本の最初のカラーは木下恵介の『カルメン故郷に帰る』(1951年)ですが。
──短編のカラー映画ですと1937年の『千人針』(三枝源次郎監督)というのがあるみたいです。映画に色が付くというのは衝撃的な体験ではなかったかと想像しますが。
蓮實 わたくしはそれを自然に受け入れてしまいました。ハリウッドで『子鹿物語』(1946年)という映画がありまして、それがカラーでした。たいした映画ではありませんが、ああカラー映画というのはこういうものかと思った。わたくしはハリウッドからカラー映画を学んだわけです。でも、やはりカラーでよかったと思ったのが、スタンリー・ドーネンの『On the Town』(1949年)でした。邦題は『踊る大紐育』。もう絢爛豪華というか、よくぞここまでやってくれたと。中学1年か2年でしたけれども、もう狂いましたね。たしか東劇で見た。
──日本公開は1951年ですね。
蓮實 何度も何度も見ました。学友を連れて行ったりして。この映画の衝撃は忘れられません。
──蓮實さんはこれまでスタンリー・ドーネンについては語られていますか。
蓮實 ないです。
──それは意外というか驚きです。スタンリー・ドーネンはどれもいいですか。
蓮實 いや、駄目なのもありますよ。
──『雨に唄えば』(1952年)は?
蓮實 あれは駄目なんです。
──だからでしょうか、世間的に蓮實さんがスタンリー・ドーネンを評価されていないイメージがあるのは。スタンリー・ドーネンといえば代表作の『雨に唄えば』ですから。『シャレード』(1963年)はいかがですか。
蓮實 『シャレード』も、とりわけよくはない。やはり『On the Town』です。
──『掠奪された七人の花嫁』(1954年)もありました。
蓮實 あれは面白い。シネマスコープでしょう?
──シネマスコープ・アンスコカラーです。
蓮實 『パジャマゲーム』(1957年)もよい。キャメラがハリー・ストラドリングでした。
──スタンリー・ドーネンがお好きなんですね。なのに、まだ語られていない。
蓮實 書きますか?
──(編集部一同)ぜひ!
映画というものを本格的に擁護したい
──書名についてお伺いします。『日本映画のために』は30年前の企画時からこのタイトルでしたが、勝手に深読みしますと、蓮實さんがこれまで、映画は常に崩壊前夜にあると語ってこられたことと関係があるのではないかと思っていました。
蓮實 そういうことではないです。この「ために」は、崩壊寸前という意味とは関係ない。まさに、本格的に映画というものを擁護したいという気持ちがありました。わたくしもこの年齢ですから、理由もへったくれもないんですよ。映画への礼のこめられた挨拶といいますか。
──今回、内田吐夢論と序文を書き下ろしていただきましたが、それとは別に、本書が初出となる「京都は、なぜ、「犯罪都市」たりそびれたか──中島貞夫『893愚連隊』から深作欣二『仁義なき戦い』まで」という、とても貴重な論考が収められています。未公表の論考が収録されたのは、蓮實ファンにとっても大きな出来事だと思います。これはどういう背景で書かれ、なぜ今回初出になったのでしょうか。
蓮實 わたくし自身も全くわからない。けれども、そのように書いたペーパーが出てきてしまった。おそらく中島貞夫さんがやっておられた京都映画祭でシンポジウムがあり、なぜか青山真治もいたような気がする年に、お話をした記憶がある。はっきりしませんが、なぜかわたくしのアーカイブのなかに、あの紙が1枚あったんですね。
──本書『日本映画のために』を記念して、シネマヴェーラ渋谷で、本で言及される映画作品から選定したプログラムが組まれました。さらにそれと兄弟企画のようなものとして、ニューヨークのジャパン・ソサエティーでも記念の映画祭が開かれました。映画の本が書かれ、それと連動するプログラムが組まれるというのは、なかなかないことです。
蓮實 いや、ありがたいことであるとしか言えません。やってくださる方の大半は、昔で言えば馬鹿ですよ(笑)。蓮實の映画の本が出たから、その一環で特集するとかね。それからジャパン・ソサエティーで蓮實の映画史をやるなんてのは、馬鹿としか思えない。それが、馬鹿ではないように見えてしまうのですから、これは文化の力かな、と思っております。
(はすみ しげひこ・フランス文学、映画批評、文芸批評、小説家
聞き手=編集部 2025年9月8日)