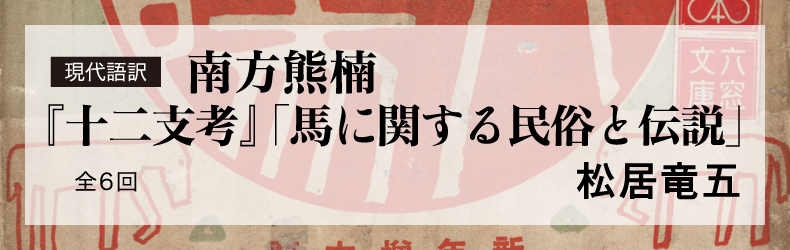第2回 現代語訳 南方熊楠『十二支考』「馬に関する民俗と伝説」 松居竜五
「塞翁が馬」の話は中国だけにある
前回、『淮南子』に出て来る「塞翁が馬」は、中国特有の話らしいと書いた。その後、いろいろ調べてみたのだけれど、やっぱり中国以外の国にこういう話があるのを見つけられない。ただし、中国自体では、『淮南子』よりも300年ほど前に似たものが流通していたことがわかった。『列子』の「説符」第8にある次のような話だ。
三代続けて仁義を通した宋の人がいた。その人の黒牛が白い子牛を産んだので、孔子に聞いてみた。すると「吉祥」だという答えで、その子牛を神として祭らせた。だが、ほどなくしてその人は盲目になった。その後、その牛がまた白い子牛を産み、やはり孔子に聞くと、やはり「吉祥」との答えで、また祭らせた。一年すると、その人の子も盲目となったので、これでは孔子の予言もあてにはならないと思っていた。
そこへ楚の軍隊が宋を囲み、宋の人は従軍して多くが戦死した。しかるに例の親子はそろって盲目のため、徴兵を逃れることができた。戦が終わると二人ともに眼が開いたので、以前は不吉と思ったことも、孔子が言ったとおりに吉祥だったとわかった。
林希逸は「この文章は、塞翁が馬の話の、馬を得たり失ったりするのと同じことだ」と評した。だから「塞翁が馬」という代わりに、「宋人の牛」と言ってもよさそうだね。漢の王充の『論衡』6にも、この話は出ている。
さて、ここからは屁の話の続きだ。またローラン・ダルヴィウーの本から紹介しよう。
かつてアラビアのある港で、一人の水夫が灰を一俵持ち上げようとして一発放つと、集まった人々がひどい不浄に汚されたように、争って海に入るのを見た。またアラビア人が集まったところで、一人の者が私に「フランス人には屁をこらえるというマナーはありますか」と聞いてきた。「無理にこらえるとすこぶる身体に悪いけれども、放って他人に聞かせるのは極めて無礼というところでしょうな。とは言え、そのために一生にわたって恥辱を負うほどではございません」と答えたところ、一同は逃げ去った。
ローランさんのこの逸話から察するに、当時のフランス人は、音さえ立てなければ屁を放っても後悔することはなかったようだ。ともかく屁のことは、臭いのは後回しということで、ボクもとんと不勉強で詳しく調べていなかったヨ。
ローランさんからおよそ100年後のデュフールの説では、古代ローマ人は式典や祭典の際の会合では屁を禁止したが、その他の場所、特に食事の際には放っても少しも咎めなかったそうだ。ただしアプレイウスの本には、イチジクの一種を食べると屁が止まらないので、ご婦人方はこれを避けて食わなかったとある。なので女性は、屁についてはなるべく控えて慎んでいたらしい。ともかく古代ローマ人たちは、放屁については我々とはまったく別の考え方を持っていたと結論づけてよいだろう。
だから他のことはともかくとして、屁の慎みに関しては、今のヨーロッパ人はむかしよりも進歩した。ボクが学んで知っているところや、みずから経験したところからすると、屁とかいうものは、好き勝手に出していると、場所にかかわらず止まらなくなる。反対に、がまんしているとそれに慣れて、けっして突然出てきたりしないものだ。
亡くなったアーネスト・ハートさんなどは、人としゃべっていると、ややもすると話の区切りみたいに放っていた。まあそれは趙の将軍の廉頗(れんぱ)が、晩年になって会見中に三度失禁したというようなもので、ひどく老いぼれたということだろう。今日では、ちゃんとしたヨーロッパ人ならば、音さえ立てなければ「放(ひ)り捨てゴメン」などという者は一人もない。上流の人、真面目な人は、その話さえしないものさ。
迷信はなくならない――岡崎邦輔君への手紙
さて、一昨年、岡崎邦輔君を介して、ある人がボクに聞いてきたことがある。何とかいう名の鉄道は、「鬼門」に向かって敷設されているというので、一向に乗客が増えない。しかし「鬼門」なんてまったくこの開明の時代に言うべきことではないだろう。そういう理屈を論じて大衆の迷信を排し、鉄道を繁栄に導く方法がありそうなものだということだった。
そこでボクが岡崎君に返事したのは次のような内容だ。
うろ覚えだけれど、マクドゥーガルはたしかこんなことを言っていたよ。「人間はワケがわかったからといって、物を恐れなくなるとは限らない。自分は動物園の鉄のオリは堅いから猛獣が出て来るはずはないとよく知っていても、やっぱり虎がこっちへ飛びかかってくるように吼えるので恐ろしかった。自分の身がふるえるのを抑えきれなかったことがあった」とね。
それと同じで、「鬼門」の祟りなど、凡衆にとっては、あるともないとも確証できないんだよ。「君子はなんでもありうると思って心配する。ないと思って安心しない」ということで、用心に越したことはないという了見がほとんど習い性となっているからね。そこへきて、むかしの蘇秦や張儀みたいな弁舌家気取りで、ボクが上から目線の説教をしたって、簡単に利くはずがないじゃないか。
それに、風習や習俗を変えるのは、社会の上層から始めて、下層がこれに倣うことで、ようやく達成できる。しかるにわが国なんか、わずか数年前にやんごとなきお方がお隠れになった際、発表されたその時刻には本当のものと仮のものの二つがあったそうだよ。それを横浜の外国語新聞がこっぴどくバカにしたのを、ボクは関西の都市圏の新聞に載っていた訳文で読んだ。
古風に則って陰陽道で日や時の吉凶を詳しく詮議したのだろうけれど、この世を去るのに吉時も凶時もないという外国人の理屈ももっともだ。が、エライさんたちは、やっぱり「なんでもありうると思って……」てな調子で、依然、古い習慣に従っておられるんじゃないの。それがいいかどうかは、ボクみたいな下賎な人間の判断するようなことじゃないけれど、社会の上層からしてすでにこんな因襲を廃止してないから、下層凡俗もそれ相応に鬼門の迷信を遵守しているんだよ。ボクが何かほざいたところで、やめるわけなどござりゃーしませんよ。
さて、ついでに言っておきたいのは、ボクが壮年期にずいぶん諸国を歩いていた時のことだ。ある国の元首が重篤になった際の公報では、詳細を極めようとするあまり、何とおならが出る時の様子まで載せていたよ。むかしは、皇帝の堯が自分に譲位すると聞いて、潁川(えいせん)で耳を洗った変人もいるし、近年でも屁を聞いて海に入ったり、屁を聞かせるまいと砂にすかし込む頑民たちもいる。
それほどではないにしても、高貴な方のおならなど、誰一人としてそんなものを期待もしていなければ、聴きたくもないだろう。それを公報に載せて自分の職務を尽くしたなどと誇っている。『論語』にある、ヒツジを盗んだ父を訴えたバカ正直な息子同然だね。こんな風にいりもしないことを聞かせて、異なる習俗を持つ民族に侮られ、「道理のわからぬヤツらめ」とおとしめられる例は少なくないわけだ。
とは言うものの、ボクもすかし屁の張本人みたいなもので、日本の屁の故事は詳しくは知らない。まあ、天正十三年〔1585年〕に千葉新介が小姓に殺されたのは、屁をとがめたことによるとある。それから風来山人〔平賀源内〕の書いた『放屁論』には、遊女が放屁を恥じて自殺しようとしたのを、通人たちが堅く口外しないと誓約書を与えて止めたとしている。
だから大むかしから、どうやら日本人は古代ローマ人のように屁に寛大だったわけではないようだね。海に入ったり、砂に埋めるほどではないにしても、むしろアラビア人流に厳しく忌避したらしい。つまりこれは、本邦固有の美風とも言える。吉凶に関して日時を変えるというような古い習慣は絶つとしても、おならの排出の様子まで公報にするよう外国のやり方を真似ることはないように望みますよ。
岡崎君は良い人だ
こんな風に答えたボクの手紙を読んで、岡崎君は「万事につけ西洋のマネばっかりの時代にあって、いいところに気づいてくれた」と、去年の春に田辺に来た際に、親しく語ってくれた。それも、単なるお世辞ではなくて、どこかで国会議員が集まった席でも、ボクの話が出て、みな感心しきりだったと中村啓次郎さんから聞いた。
実はボクは30年ほど前にアメリカにいた時、同類の学生とつるんで飲酒ばかりしていた。それを岡崎君が非難したことに対して、ずいぶんかみついて悪口を繰り返したことがあった。それなのに岡崎君は懐が広い人で、21年もこの片田舎に隠棲しているボクを訪ねてくれた。そのうれしさに、思わず長々と書いてしまったわけだ。
その頃、亡くなったエドウィン・アーノルドさんが東京に滞在していて、いろいろなことを書いたうちに、「初めは冗談、中頃は義理。今じゃお互い真実の愛」という都々逸を誉めて翻訳した。ボクはその鑑識眼の高さに驚いて、小澤君という人に話して、小澤君はまた岡崎君に向かって受け売りしたことがあった。
すると岡崎君は「恋愛の実態は、そんな言葉では尽くせない。たいてい若者は外見を重んじるけれど、中年になると気持ちが大事だ。初老以降になると、コトはおろそかになるけれど、感情は乱れる。そして人生の最終版になると、健康だけが問題になってくる」と言ったらしい。この言葉はまことに慧眼と言うべきだよ。人間だけでなく、察するに動物についても、年齢を重ねるにしたがって心情がこんな風に移り変わる例がとても多い。
その移り変わるのを、進歩と見るか堕落と言うかはちょっと決めにくい。ただ、わが邦の俗には「20歳の後家は立つけど、30歳の後家は立たない」と言う。若い頃は清廉潔白と思われていたのに、老後になって汚名を流した人は、各国の歴史に後を絶たない。みんな岡崎君の説の通りの理由によるようだ。
ボクがイギリスにいた頃に有名だったある学者にこの話をすると、「ほほう、日本にも賢い人がいるもんじゃ。今日のヨーロッパで女性がらみの行いを論ずる人たちも、たいていその通りの基準で見とるよ。ただ、その岡崎君とやらほど、手短に規則立てて明言した人は聞かんね」と感心された。
32~33歳の時に、これほどの観察力を持っていた岡崎君が、政治の代わりに学問に関わり続けたとしたら、わが邦の学術を一かたならず進展させたことだろう。その学者は、著書はすこぶる多いけれど、多忙のためかボクが一々発案者の名を伝えていることでも、全部ボクが思いついたことのように記している。世界大戦が始まってからは音信がないけれど、もしかしたら岡崎君の説も、ボクの説のように書いているかもしれない。その場合は、読んだ人は、ボクは単に岡崎君の説を吹聴しただけだと思ってほしい。
屁の次はクソの話
さて、屁が済んだから、今度は馬のクソの話にしよう。「クソ成金」になれるかもしれないので、しっかり読むべし。
『大清一統志』222には、湖南の金牛岡に関する次のような故事がある。
むかし、赤牛が川を渡ってクソをするのを見ると金だった。跡をつけて行くと、この丘で見えなくなった。地面を掘って金を探した跡が現存するらしい。また240巻には、秦の恵王が蜀を討伐しようとして、石の牛を五頭作った。毎朝、金をその後に落として、牛が金の便をするというと、蜀の人はよろこんでこれをもらって持ち帰った。その時に作った「石牛道」すなわち今の剣閣道から討ち入って、蜀を滅ぼした。
『醒睡笑(せいすいしょう)』1には、田九郎という者が、「この馬は三日に一度かならずクソとともに金を出すんだよ」と言って兄を欺いて、五十金で売ったという話がある。
ヨーロッパでも、家畜類が金のクソをした話が多い。たとえばクレーンの『イタリアの昔話』に出て来る次のような例だ。
貧しい子どもが叔父に小さなロバをもらった。その下に風呂敷さえ広げておけば、銭の便をしていっぱいになる。そのロバを連れて行くうちに日が暮れて、旅宿に泊まってロバと同室で寝ていた。亭主が怪しんで覗くと、銭をたくさん出している。そこで亭主は、端から端までそっくりの他のロバを連れてきて、その子どもが眠っている間に、金のクソをするロバとすり替えた。翌朝出立して、途中で初めて気がついて、引き返して亭主を責めたが、応じなかった。
叔父を訪ねて泣きつくと、今度は広げさえすれば思いのままの食事と飲み物が出て来るテーブルクロスをくれた。それを以てまた同じ旅宿に泊まると、前と同じようにすり替えられてしまった。そこでまた叔父に泣きつくと、「仏の顔も三度までだからな」とつぶやきながら、今度は杖をくれた。この杖は、「打て」と命じると人を打ち続け、「やめ」と命じるとやめる。それを携えて、例の旅宿に泊まった。
亭主はその杖が美しくて、柄が金作りなのを見て、夜その部屋に入って盗もうとした。それを待ち受けていた子どもが、小声で「打て、打て」と呼ぶと、杖はたちまち飛び出して来て、激しく亭主を打った。勢い余って鏡、いす、ガラス窓以下のものを粉砕し、助けに駆けつけた人々もみな打たれてしまった。亭主は盗んでおいたロバとテーブルクロスを返してようやく許され、子どもはその三つの品を持って家に帰り、母と安楽に豊かに暮らした。めでたし、めでたしとさ。
「鮓答」という不思議な石
『フォークロア・ジャーナル』4巻に、中国人の起源についてモンゴル人が伝えた不思議な話が載っている。
貧しい男がいた。路上で二人がヒツジの眼ぐらいの大きさの玉をめぐって争っていたのを見て、「その玉を渡せ。オレがそれを持って走るから、先に追いついた方が玉のもち主ということにしようじゃないか」と言った。しかし男は玉を受け取るとすぐに飲み込んで、隠れて去ってしまった。それから他の国に行って、ある老人の養子となった。
この養子はツバを吐くごとに金を吐く。そこで老人はその金を国王に献上して、「王女さまを養子の妻としていただきたい」と願った。王様が、「ともかく本人を連れてこい」というので、来させてみると、その男は王様の前で金を吐いた。王女は馬の腹帯で男を縛り、塩水を飲ませてからムチで打った。すると玉を吐いたので、王女がこれを拾って飲んだ。男は老人の家に帰って、ロバの鞍と手綱を作りに行って、白い樹木の下に座した。
この男は、貧乏な時にこの樹木の下で眠り、夢の中で不思議な呪文の力を得ていた。そうとは知らない王女は玉を飲んで懐妊し、お付きの処女二十人を連れて樹下に遊びに来た。男は呪文を唱えて王女をロバに化して、鞍と手綱を付けて一か月の間乗り歩いた。ロバは疲れてもう進めなくなってしまう。そこで男は、歩いてある都にたどり着き、僧侶となった。後に残ったロバの姿の王女は男児を生んだが、その子孫はみな金銀や豪華な布を保有し、いつも富裕で子種も多く、どんどん増えて今の中国人となった。
この話は、モンゴルなどの人々が、動物の体内に生ずる「鮓答(さとう)」という石を尊ぶことから生じたのだろう。「鮓答」は西域の言葉である「ジャダー」の音訳だ。今日もアルタイ地方に「鮓答師」(ヤダチ)という呪術師がいる。よくこの石を用いて天気を支配する。この石は、絶えず強風が吹き荒れる狭い山谷に産する。一切の所有物を捨てる人だけが、初めてこの石を手に入れることができる。だからこの石を使う者は、一文無しで妻もいないという(チャプリカ『シベリアの先住民』1914年、200頁)。
テュルク(突厥)やモンゴル(蒙古)の軍隊で、しばしば「鮓答師」が徴用された例は、ユールの『マルコ・ポーロの書』第1版1巻61章に出ている。元の遺民だった陶宗儀の『輟耕録(てっこうろく)』4には「モンゴル人が雨乞いをするのを見ると、中国の方士が旗や剣や護符などを用いるのとは異なっている。ただ数個の石を浄水に浸して呪文を唱えながら石を揺り動かすと、しばらくして雨が降る。その石を鮓答といい、獣たちの腹の中にある。牛馬に生じるものが、最も効果があるらしい」とある。
これは日本で「馬糞石」などと俗称し、まれに馬糞の中から発見されるもので、ボクも数個持っている。『松屋筆記(まつのやひっき)』に引用されている『蓬窻日録(ほうそうにちろく)』には、「兵法の極意として、急に雨風を起こして囲いを破る術がある。この時、『赭丹(しゃたん)』を身につけているとよい。『赭丹』とは馬の腹の中に産する石だ。これを用いて呪文を念ずれば、すなわち雨風を起こす」とある。この「赭丹」も、モンゴル語の「シャダー」の音訳だ。
曲亭馬琴の『兎園小説(とえんしょうせつ)』には、死んだ馬が侠客の夢に現れて、その死体の埋葬を頼み、謝礼として骸の中の玉を与えたとある。なんにせよ、天下分け目の大戦(おおいくさ)でさえ、鮓答で決せられると信じられていた。1202年、ナイマン族などの大連合がチンギス・ハンおよびアウン・ハンと戦った。その時、アウン・ハンの子が霧や雪を起こしてこれを破ったのも、この石の神威によると言われている。だからこれを手に入れようとして一切の所有物を捨てても十分に引き合うほど、非常に高価なものだったらしい。
クソが金に化する理屈
鮓答は薬としても、近古まで高価だったことが、タヴェルニエの『インド紀行』巻2からわかる。また畜類のクソは古来種々に用立てられた。19世紀に早くもラサに入ったフランス人宣教師ユクの説に、モンゴル人は家畜のクソを巧みに類別して、適宜過たずに応用する。ヒツジのクソを焼くと高い温度を発するから金属の精製に用い、牛のクソの火は温度がそれほど高くならないので肉をあぶるのに使う。
前述したロバのような長い耳を持つフリュギアのミダス王は貪欲で、自分のクソを金に変えたと伝えられている。ローマの皇帝ウェスパシアヌスは、公的な行事に巨万の富を費やすことを惜しまず、財産を殖やすために、熱心に馬のクソを売った。そのことを皇太子に諫められると、「馬糞を売って得た金は悪臭がするのか。匂いを嗅いでみろ」と言った。こんな風に、畜類のクソから高価な鮓答が得られたり、クソそれ自体がずいぶんと金に替えられたりしてきた。それを大げさに改変して、金のクソを出すロバや牛の話ができたわけだ。
アストレイの『チベット記』には、大ラマの糞尿を信徒に配って多くの利益を得ていたラマ僧のことが載っている。モンゴル人はそのクソの粉を小さな袋に入れて首にかけ、その尿を食物に一滴落として用いれば、万病に効くと信じている。カソリック僧のジェルビヨンが韃靼〔タタール〕の西部に使者として赴いた時に、大ラマの使者がこの粉の一袋を清国の皇帝に献上しようと申し出て、拒まれたらしい。こういうのはこの上なく高価なクソだね。
わが邦でも、古くは陣中で馬糞を薪の替わりにしていたし、馬糞の汁で怪我の手当てをおこなった(『雑兵物語』下)。したがって、馬糞を金ほどに重んじた場合もあったのではないだろうか。羽黒山の社の前後には、お賽銭が砂や小石のように満ちていて、参詣人の草履に付く。それを下山の前にことごとく払い落とす。しかし強欲なヤツらがそのまま家に持ち帰ると、全部馬のクソになっているという(『東洋口碑大全』762頁)。
馬のクソに似たキノコ
韓愈(かんゆ)が『進学解』で言っている「牛溲馬勃(ぎゅうそうばぼつ)」つまり「牛のションベン馬のクソ」は、どちらももらって置いておけだ。名医が使えば馬糞でも大きな効用があり、不心得なヤツが持てば金銭も馬糞と同じ。韓愈のこの文句の中の「馬勃」は馬糞を指しているけれど、『本草綱目』に掲げた「馬勃」は馬糞に似た担子菌類のリコペルドン・スクレロデルマで、チリタケとかホコリタケなどと呼ばれているものに当たる(『本草図譜』35巻末の図を参照)。

第一図に示したのは、これらに近縁のポリサックムの2種で、いずれも田辺で採集した。ちょっと見ただけでは、これも馬のクソに生き写しなキノコだ。今まで、およそ20種ばかり記載されていることと思うが、ボクが知っている限りではオーストラリアにとてもたくさんの種がある。30年ほど前に、ヨーロッパで4種、アメリカで2種見つかった。アメリカのフロリダ州のものは、ボクが初めて見つけたらしい。今でもその標本を持っていて、数年前にボクを訪れてきたアメリカ植物興産局の当事者であるW. T.スウィングルさんにも見せた。
本邦では、これもボクがイギリスから帰国したまさに次の日の朝に、泉州の谷川で初めて見出した。それからは、紀州のさまざまな地方、特に温かい海浜の砂の中に多くあることがわかった。従来の西洋人の記載に従うと、これらは少なくとも3種ということになるのだけれど、ボクの長年の観察から言わせてもらえば、この3種は確固とした別種ではない。どうも、ポリサックム・ピソカルピウムという一つの種の3つの異体にすぎないようだ。そこで、この一つの学名で白井光太郎博士に報告し、博士の近著『訂正増補日本菌類目録』485頁に記録された。
馬糞みたいだが染料になる
このキノコについては、スウィングルさんも、最近まで気づかなかったようだ。スウィングルさんは、ボクとまったく同じ時期に、フロリダで植物研究をしていた人だ。ボクは30年前から気づいていたのだけれど、このキノコは染料としての効果が著しい。生活が苦しい人たちなんかに教えて、見つけたら集めて貯めておくようにすれば、大いに産業の役に立つと思う。
ただしボクだって今でもヒマさえあれば研究をしているような身なので、これ以上は一言も漏らせないなあ。近頃は、三銭の切手一枚を貼って同封した手紙で、お手軽に教えを請うような人もいる。だけど、上等のカステラを一箱持って、美人で有名な当地の錦城館のお富さんに仲介してもらってきたってダメだぞ。このお富さんのことは、昨年4月1日号の『日本及日本人』にも出ていて、「この間は軍艦の艦長さんがわざわざ私の顔を見に来たわよ」などと本人は鼻高々だ。
キノコを染料にする話に戻すと、欧米の人たちは、こんなことをちょっと聞いたりしても、くどくどと委細を尋ねたりはしない。一生懸命に自分で研究して、その説の真偽を明らかにしようとして、ウソだとわかったらやめる。もし少しでも意味があると思ったら、他人がどうしているかなど考えずに、一念発起で自分の独自の見解を得ようと努力する。
先日、スウィングルさんが来訪した時には、ボクがそれまでに送った手紙を、すべて写真版にして番号を打って携えていた。口数は少ないけれども深い洞察力を持った人で、感嘆する他なかった。今のわが邦の人たちの多くは、それとはちがって、誠実さや集中力が身に備わっていない。だから水の分量や薬の加減のようなつもりで、分かりもしないことを、根掘り葉掘り聞いてきたりする。そして半信半疑のうちに、鼻歌半分で事に取りかかるものだから、全然ものにならないというわけだ。
さて、ボクがこの菌類を染料にしたらどうかと思い立ったのは、フロリダで中国人の牛肉屋の店番を勤めていた頃のことだ。決して書籍に書かれた他人様の知恵を借りたわけではない。ただ、日本の学者どもは万事につけて書籍を盾にするクセがある。そんな卑劣な連中に、「しょせんオマエのホラ話だろう」などと邪推されるのは面白くない。
だから、バークレーの『隠花植物入門』(1857年)345頁に書かれた「ポリサックムは黄色の染料としてイタリアで多く用いられる」という、その後見つけた文章を引用しておこう。さらにグリフィスとヘンフレーの『顕微鏡学事典』(第4版、1883年)623頁にも「イギリスには一種だけまれに生じる。外国ではその一種を染料とする」とある。
ただしボクが知っている限りでは、本邦産のものが三種なのか三異体なのかは別として、どれも役に立つ。初夏から初冬まで、海から遠くない場所の丘陵や、特に砂浜には少なくない。注意すればずいぶん集まるとことと思われる。黄土や「無名異(むみょうい)」と呼ばれる赤い粘土に似ているから、鉄分を含んでいることがわかる。
砂鉄の産地を見つけたゾ
そうだ、鉄については、ついでにもう一つ国益になることを教えてあげようじゃないか。以前、東牟婁郡の何とかいう村を通った際に、家々の様子を見ると、何となくむかし見た東国の地方にある娼家に似ていた。そこで聞いてみると、以前、そこの二つの村の娘は、年頃になるとみんなある種の「おつとめ」をして家計を助けていた。内外の人たちはこのことを讃えて、その「おつとめ」を果たした娘を争ってめとったそうだ。しかし明治維新の後にはそういう風習は廃れて、家だけがむかしの構造のまま残ったという。
まるで古戦場を弔うような気持ちでその中の一軒に入って、昼食を所望して、たくさんある部屋のうちの一つに入った。食べながら床の間を見てみると、砂鉄で黒く塗ってある。他の部屋を巡ってみたが、みな同様だった。それから口実を設けて他の家も一、二軒入ってみたが、やはりそのようになっていた。「この砂はどこから来たんかいね」と聞いてみたが、老いぼれた親父や婦女子ばかりで、何だかわからない。こんなところに遠方からむかしにそんなものを運んで来るはずもないので、かならずこの地には砂鉄を産するのだろうと考えた。
その後、勝浦から海伝いに浜の宮まで河口を横切って歩いて海藻を調べていた時のことだ。海の潮に揺られている砂鉄で、下駄の跡が黒く「二」の字を描くような場所があった。浜の宮には、砂鉄の中に稲を植えたような田んぼもあった。だから、かつて見た娼家たちの壁は、もっぱらこの辺の鉄の砂で塗られたものだとわかったというワケさ。
ボクは鉱物学の研究をやめてしまってからもう37年になる。問題の海辺にも、14年くらいは行っていないから、これ以上は一言も付け加えることはない。ただ、『和歌山県誌』などの最近の報告では、紀州に砂鉄があるとは一切書いていない。してみると、ボクのようにこの件について知っている者は、現在は多くはないのではないかと疑われる。
鉄は金や銀とは異なって、わずかな分量では利益にならないと聞いたけれど、この頃はアメリカからの鉄が禁輸になって、一粒の砂鉄も粗末にできないという話だ。ふとしたことから大きな国益が得られた例も多いので、娼家の黒壁が、わが邦の慶事を開くことだってあるかもしれないよ。なので、本誌の紙面を借りて、関係者諸氏の注意を引いておきたいと思う。
それにつけても神社合祀はケシカラン
この類いのことは、まだまだおびただしくネタがある。が、とりあえず今回はこれで打ち切りだ。もし市井の人で、この文章を読んだことから大もうけをしたりしたら、お富に大金でも送ってやってくれ。37歳まで仲居奉公を続けてきて、そろそろ飽きてもきたし、娘も嫌がっているとのことだったから、何とか所帯でも持たせてやりたいもんだ。
またさいわいにして、政府がボクの発見や研究成果の功労を認める日が来るかもしれない。その時は勲章の何のと下さるには及ばない。海外の多数の碩学や名士がいつもボクに同情していることを考えてもらえれば良い。ボクが微力ながら、もう老いが迫っていることもおかまいなしに、寝る時間も食事の時間も惜しんで苦心する研究に、致命的な打撃を加えるヤツらがいるんだ。それは和歌山県の役人どものことさ。こいつらに戒告を与えてほしい。
この役人たちときたら、自分たちの利益のために無益なことばかりしている。愚民たちと結託したり、登記料を撤廃したりして、日本の輝かしい宝物である古い神社の林を生きながら切り刻むようなヒドい所業をおこなっている。山を荒涼とさせ、海を汚して、世界でもまれに見るようなたくさんの貴重な生きものに居場所をなくさせ、種が絶えてしまうように仕組んでいるんだ。そうして「良好な結果を得ました」などという虚偽の報告を上申して揚々としている。何とぞ、こうしたやり方を厳しく取り締まってほしいと、平にお願い申し上げる。
さらに甚だしきは、お上に媚びたり、浅はかな外国の宣教師に乗せられて、ボクのことを悪口嘲弄する輩さえいることだ。むかし、織田家に仕えた右馬助(うまのすけ)〔福原長堯〕という男が賄賂を何度ももらっていたので、信長から「『うまのすけ』だけに銭のクツワをはめられたのか。やっぱり『畜生』と呼ばれるだけのことはある」という内容の歌を送られたことがある。「銭のクツワ」が通用しないような人は、残念ながら今の世では生きていけないのかと、ため息をつくばかりだね。
もっとも、海外だけでなく、国内でも多少の同情を寄せてくれる人は少なくない。けれどもその多くは自分も役人で、食うに困るわけにもいかないから、十分には加勢してくれない。かつて、大阪府の薄給の公務員が血書によってそういう事情を吐露して、「先生の高き志を、忸怩(じくじ)たる思いで仰ぎ見ております」と匿名の手紙を送ってきてくれたのが最上の出来というくらいだろう。ともかくも「智恵の馬」が、物を知らない馬商人の鞍の下で、乗り潰されて死んでしまわないようにと、切なる希望を述べてこの章を終結しておこう。
馬を表す名称はどのようにつけられたのか
馬の梵名は「アス」「ヌアスワ」または「ヒヤ」、ペルシア名は「アスプ」。スウェーデンでは「ハスト」、露国では「ロシャド」、ポーランドでは「コン」。トルコでは「スック」。ヘブライ語で「スス」、アラブでは「ヒサーン」。スペインでは「カバヨ」、イタリアとポルトガルでは「カヴァヨ」。ビルマでは「ソン」、インドのヒンドゥー語では「ゴラ」。テルグ語では「グラム」、タミル語では「クドリ」。オランダ語では「パールト」、ウェールズ語では「セフル」。
こういうさまざまな名がついたのには、さまざまな理由があるだろう。なかには、馬の鳴き声や足音をまねて名称にしたものもあるはずだけれど、ちょっとわからない。中国で「馬」と書くのが象形文字であることは周知だが、その音の「マー」は鳴き声をまねたものと解釈する他ない。
『下学集』は、「胡」「馬」の二字で「ウ」「マ」になるのはずのところを、日本では「馬」一字で「ウマ」と読むのは無理があるとする。そこで「馬は北部の胡地方で多く産するから、胡馬と言うのだ」と説かれている。しかし、物茂卿〔荻生徂徠〕が「梅(メイ)」を「ウメ」、「馬(マー)」を「ウマ」というのは、ともに音から来ていると言っている方が当たっている。「ウ」というのは発音の便宜上、付け加えられたんだろうね。
アーリア人の名づけ方はそんなにエラいのかい?
さて、故マクス・ミュラーは次のように説いたことがある。
オウムでさえ、オンドリやメンドリを見ると、その鳴き声をまねて、自分が見たのが何者かを人に教えてくれる。それと同じで、未開民族というものは動物の鳴き声をまねるのが上手じゃ。だから馬のいななきをまねて、馬を名指しするくらいのことは思いつく。
だ-が、そんなのはほんのモノマネで、言語と呼ぶには足りんね。我々アーリア人の言語は、そんな下等なものではござらん。馬を名指しするにも声をまねるわけじゃあない。なんと我がアーリア人の祖先は、馬を名づけるために、その最も特徴的な性質として、「足が速い」ことを採用したのである。
だから梵語の「アース」は「迅速」を意味した。ギリシア語の「アコケー」は「先端」。ラテン語の「アクス」は「針」で「アケル」は「迅速」または「鋭利」または「明察」。「鋭利」を意味する英語の「アキュート」から類推するに、これらの諸言語の根源としてのアーリア祖語には「鋭利」または「迅速」を意味する「アス」という単語があったことがわかる。
その「アス」が「アスヴァ」つまり「走るもの」の意味となり、これがすなわち馬の梵語名やリトアニア語の「アスズウア」(メス馬)や、ラテン語の「エクヴス」、ギリシア語の「ヒッコス」、古代サクソン語の「エツ」という、いずれも「馬」を意味する語を生んだというワケじゃよ(『言語学講義』2巻、1882年)。
このミュラーというのはドイツ人で、イギリスに帰化した。「イギリス人の優秀な遺伝子は、みんなドイツ人と血を分けた者に限るのだあ」とか、「英独の人種が世界でいっちゃんエラいんだあ」などとも説いている。また、しきりに古代インドの文明を称揚して、インド人をイギリスに懐柔させるのに功績があった。
ところが今では、そのインド人はややもすればイギリスを嫌うようになった。またイギリスの学者までもが、ドイツ人はモンゴルの匈奴の末裔だと罵って、「アイツらには独特の体臭があって、イギリス人とは全く別人種だね」などと触れ散らかしている。学説の変転はネコの眼も呆れるくらいに早いものだ。だからアーリア民族の馬の名前が、一番高尚だとかいう説も、バカに高価な御札みたいなもので、簡単には受け入れられマセンときたもんだ。
古語に関する詳しい辞書が手元にないから確信はできないけれど、ドイツ語には「プファールデン」という、「馬がいななく」という意味の動詞があったように思う。果たしてその通りならば、ミュラー氏がアーリア人の中で一番エラいとしているドイツ人の「プファールト」やオランダ人の「パールト」だって同じようなものじゃあないのかね。つまり、いずれも中国の「馬」や、おそらくはアラブの「ヒサーン」がそうであるように、馬のいななき声を採って、その名としたわけだ。
わが邦の学者は腰抜けばっかりだから、ボクがこんなことを言うと、「人もあろうに比較言語学の開祖のミュラー先生に食ってかかるとは」と驚いて、「それはいかがなものか」と不敬罪でも犯したかのように誹るのかもしれんね。だがしかしだ。孟子は「権勢のある人を説得するには、相手を軽んじるべきだ。相手の居丈高な態度を見るな」と言っているじゃあないか。
なにせこちとら、30歳にならぬうちに、オランダの国家的な一大中国学者のグスタフ・シュレーゲル大先生に論争をふっかけたミナカタ・クマグスだぜ。その時は大先生に屈辱の黄色い泡を吹かせて、直筆の降参の手紙を取って、今でも日本の誇りと保存している。ミュラーの亡霊くらい、馬のクソとも思わんね。このくらいの男気があるから、錦城館のお富にも惚れられるんだい。とまあ、単なるウ・ヌ・ボ・レかもしらんけど……。
まだまだミュラーをこき下ろすゾ
ダニール・ウィルソンが言うには、新世界であるアメリカ大陸にヨーロッパ人が移住してきてから、旧世界ではかつて見たことのない異形の生物を見て、その鳴き声をまねて名を付けた例が多い。動物の名の「アイ」や、いずれも鳥の名の「カラカラ」、「ホイプールウィル」、「キタワケ」などだ。
一方、新世界にもともといたインディアンと呼ばれる人たちは、これと反対に、ヨーロッパ人が持ち込んだ動物たちを、その性質や動作などによって命名した。たとえば、チェロキー族の言葉で馬の名は「サウクイリ」で、「小さな荷物を運ぶもの」の意味だ。デラウェア族の名は「ナナヤンゲス」で「背負って運ぶ獣」、チペワ族の名は「パイバイジコグンジ」で「一つのひづめの獣」、またダコタ族はもともと物を負う家畜は犬だけだったから、馬のことを「スンカワカン」と呼んだ。これは「霊犬」つまり「荷を負う不思議な家畜」という意味だ(『有史以前の人類』1巻72頁)。
つまり、後世でもアーリア人の言語では、かえって動物の声をまねて名をつけていることが多い。それに対して、「劣等民族」とされたアメリカ先住民たちが初めて馬を見て名を付ける際に、もっぱらその性質に依拠していて、その声をまねなかった。ミュラー先生は、こんな確固とした反証が少なくとも二十年前に出ているのを知らぬ顔で、何が何でもアーリア民族を持ち上げようと、勝手な言い分を吐いたことになる。わが邦の学者の一派が、今日に至るまで時代遅れにも後生大事に尊敬するような立派な人物じゃあなかったってことだね。
リチャード・バートンはアラビアには馬に関する名が多いと述べているけれど、中国人も古くからずいぶん馬に注意を払ってきた。そのことは『爾雅』を初めとする辞書類を見るとわかる。前足が白い馬を「騱(けい)」、後足がみな白いのを「翑(く)」、前の右足が白いのは「啓(けい)」、前の左足が白いのは「踦(き)」、後の右足が白いのは「驤(じょう)」、後の左足が白いのは「馵(しゅ)」と、なかなかに小難しく分別して命名されている。
わが邦でも、毛色のちがう馬を呼び分けるのに雑多な名称がある。古来、苦心してそれを漢字に直していたことが、『古今要覧稿』巻515から524までに見られる。とは言え、こんなことをくどくど書いていても面白くないから、何か珍説でも語ってみよう。
女の「陰相」をめぐる話
三年前に南洋の各地を視察した長谷部博士の説では、トルク島の住民がけんかする際には、相手やその家族の陰部に関して、聞くに堪えない言葉を戦わせる。マーシャル島の住民もまた、仇敵の母の陰部について悪口するらしい(『人類学』30巻7号279頁)。
『根本説一切有部毘奈耶』には次のような話がある。
ブッダの弟子の優陀夷(うだいや)は人相学に詳しかった。舎衛城の中を托鉢している際に、バラモンの家に至って若い女を見た。「アナタの姑はどんな方ですか」と聞くと、ウサギが矢に当たったように、ここぞとばかりに「意地悪でございます」と答える。優陀夷は「それは姑のせいではございません。姑の二つの乳房の間と秘所には、黒いホクロと赤いホクロと旋毛(つむじ)があります。この三つの悪い相があるためです」と教えて、食事をもらって去った。その後、またその家に来て、今度は姑に「アナタの嫁はどんな方ですか」と聞くと、「仕事もしないでずっと機嫌が悪うございます」と答えた。そこで前回と同じことを教えて、食事をもらって去った。
さて他日、他の信者の家を訪れて説法をした時に、その姑に嫁のことを尋ねると、「実の娘のように孝行を尽くしてくれます」と嬉しそうに語った。「それは嫁の徳ではございません。嫁の二つの乳房の間と秘所に、善き相があるためです」と教えた。その後、またその嫁に姑のことを問うと、「実の母のように愛してくれます」と答えたので、「それは姑に善き相があるためです」と告げて去った。しばらくして、姑と嫁が一緒に沐浴して、互いの身体を流し合った際に、密かに観察すると、優陀夷が言った通りの相があった。
その後、この姑と嫁がケンカした。その際に姑がまず嫁に向かって「この浮気女め」と罵ると、「誓ってそんな覚えはございません」と言い張った。姑はすかさず、「もし覚えがないなら、他人がオマエの秘所にホクロがあるのを知っているはずがないじゃあないか」と言った。すると嫁もまた「それならソチラも姦通したはずですよね」と言って「陰相」のことを語った。二人とも「こりゃあ変な話だわね」と気づいて互いに謝った。そして「誰がそんな相のことを告げたのか」と交互に問うと、いずれも「優陀夷さまから聞いた」と答える。そこで「そんなエラい人が、なんでワタシらなんかを困らせるのかねえ」と憤った。
そこへ年老いた僧侶が托鉢に来たので、「優陀夷さまはどんな方なのですか」と聞いてみた。「大臣の家に生まれて、出家なさったのでございます」と答える。姑は「戒律を守るご出家さまなら、女の身体の陰相などご存じのはずがありませんわ」と言うと、「人相学に通じておられますからね」と話す。姑は、「そんなことを知っているからといって、他人に告げてよいものでしょうか」とやり返した。老僧は閉口して、寺に帰ってブッダに告げた。するとブッダは「弟子たちよ。今後、俗家で女に説法してはならん」と戒めた。しかしそれでは実納(みいり)が少ないとのことで、男子が側にいるところで女人には説法すべし、と改められた。
インドのように、人が衣服をたくさん重ねて着たりはしない熱帯では、こういうことを学び知る機会が他の地方よりははるかに多かったはずだ。したがって、そちらの方面の研究はよほど進んでいたのだろう。それと同時に、そんな相好(そうごう)を覚えていて、人を罵る際に用いた輩も多かったようだ。
『十誦律(じゅうじゅりつ)』47には、女性が出家のための具足戒を受けるのに先だって、あらゆる事を聞いて真実を答えさせたとある。「ワレは今、ナンジに問う。ナンジは人であるかどうか。女であるかどうか。非人ではないか。畜生ではないか。不能女人ではないか。女陰の上に毛はあるか」と。これは、それらの者たちを完全な人間とは見なさず、受戒を許さない定めがあったということだ。この辺でも、そういう女を不吉としていて、特に農家は毛がないのを忌避する習慣がある。そんな者を嫁にすると、隣家までも収穫が減るといって嫌っているわけだ。こんなのは、まったく笑うべき迷信でしかない。
不毛を「カハラケ」と呼ぶこと
ただ、今日でも西洋の医者には間違った説を説いている人が多い。たとえば、顔の良さから寵愛を受けた美少年は、ことごとく弱虫で萎縮して終わる、などと説く者がたくさんいる。西洋にはハンニバルやシーザーのように、少年愛の対象になった偉人も多いのにね。
わが邦でも美少年が後に名を馳せた例は少なくない。「蘭丸をいっち惜しがる本能寺」とか、「佐吉めは出世をしたと和尚言い」と称された森蘭丸や石田三成のことだ。それなのに、むかしの魏の安釐王(あんきおう)とその寵愛を受けた竜陽君のように、少年愛にふける人たちはかならず没落する、みたいな論ばっかりだよ。そんなのは、性欲が偏向している醜男や、ろくでなしの女たらし連中だけを視野に入れた暴論だね。
このことは、イギリスの詩人シモンズの『近代倫理学の一問題』(1896年)や、明治42年〔1909年〕に『大阪朝日』が連載した蕪城生の「不識庵と幾山」に、ていねいに論じてある。それと同じように、「毛のない婦人はかならず不妊だ」と説く者が西洋には少なくないけれど、これも事実とは異なる場合がある。ボクに言わせれば、最近流行の「人種改良」とか「善胎学」とかいうものは、目的は至って結構だけれど、その基礎となっている事実認識がはなはだ危うい。呆れてしまうことも多いから、きちんと情報を収集しようとずっと心がけている。婦女の不毛の件についても、大問題と考えていて、ちょっとした話でもないがしろにはしていない。
そんなところへもって、近くの村から長い間行商に来ていて、さまざまな地域の俗伝に詳しい老人が、この件に関する秘説を持っているというから興味津々だ。人の命は雨の晴れ間を待ってくれたりはしないからと、矢も楯もたまらずに走って聞きに行ってきたよ。すると老人は、何か笙の秘曲でも授けてくれるような顔つきで、ニカッと笑って、次のように語り出した。
むかしからな。なんも生えてへんのを、「まんじゅう」て言いよるんや。これはな、別段、凶ちゅうことやないんよ。ちょびっとだけ生えとるのを、「かわらけ」言うてな、これがえらい不吉なんや。馬にも河原毛いうのがあってな、そっからきとるんや。
その時は特に気にしていなかったのだけれど、ほどなくして老人が死んだ後にいろいろ考えさせられた。中国で「駱」と呼んでいる馬の和名が「川原毛」で、黒いたてがみの白馬のことだから、毛がないというわけではない。しかし実際に川原には砂や小石が多くて、草は少ない。だから老人の説の通り、わずかに春草のある所を、馬の「川原毛」から名前だけ借りて呼称しているのかと推察した。が、死者には質問することもできない。
『逸著聞集』などの多くの書では、「土器(かわらけ)」と書いているが、その意味はわからなかった。すると、ようやくこの頃になって、『皇大神宮参詣順路図会』をひもといてみたところ、伊勢の二見浦(ふたみのうら)の東神前(みさき)の東北海中に七つの島があって「阿波良岐(あはらき)島」というとあった。また「毛无(けなし)島」といって、まるごと巌からなっていて、草木がない島がある。あわせて八つの島が連なっている。
『内宮年中行事記』には、6月15日の贄海(にえうみ)の神事の時に船子が唄う歌の中に「阿波良岐や、島は七島と言うけれど、毛无を加えて八島だ」というのがあるとしている。『続々群書類従』一に収録されている『内宮氏経日次記』では、「阿婆羅気(あばらけ)や、島は七島と言うけれど、毛無もあるから八島だ。エイヤ、エイヤ」となっている。
これだけでは不安だけれど、「アバラケ」という語は「亭」を「あばらや」と読むように、荒れすさんでいるという意味だろう。それだと毛がないのと近く、ほとんど相通ずる意味の詞と言ってもよい。それで「不毛」を「アバラケ」、そこから転じて「カハラケ」と呼ぶようになったのではないだろうか。『日次記』には、これらの歌は宝徳三年〔1452年〕頃にはできていたように書かれている。以上のボクの考えが、もしも当たっているとすれば、不毛のことをこのように呼ぶのは足利義政の時代には、すでにあったこととなるはずだ。まあ、だいぶアヤシい説だけれどね。
名馬の名づけ方
中国の名馬としては、周の穆王(ぼくおう)の「八駿」が挙げられる。その名は「赤驥(せきき)」「盗驪(とうり)」「白義(はくぎ)」「踰輪(ゆりん)」「山子(さんし)」「渠黄(きょこう)」「華驑(かよう)」「緑耳(りょくじ)」だ。漢の文帝の「九逸」というのもある。こちらは「浮雲(ふうん)」「赤電(せきでん)」「絶群(ぜつぐん)」「逸驃(いつひょう)」「紫燕(しえん)」「緑(りょく) 」「竜子(りゅうし)」「 駒(こま)」「絶塵(ぜつじん)」となっている。前者は毛の色、後者は動作を、主に名前の要因としているわけだね。その他に項羽の「騅(すい)」や呂布の「赤兎(せきと)」、張飛の「玉追(ぎょくつい)」、袁顗(えんぎ)の「飛燕(ひえん)」、梁の武帝(ぶてい)の「照殿玉獅子(しょうでんぎょくしし)」などがある。
本邦の古代の『垂仁紀(すいにんき)』には、「足往(あゆき)」という名の犬はいるけれど、特別の名がある名馬というものは見られない。はるか後に藤原広嗣は、太宰府にいた時、ある馬が一声で七度いななくのを聞いて高値で買い取った。この馬は、初めは四本の杭の上に四つの足で立った。が、数日後には四つ足を縮めて一本の杭の上に立った。よく主人を乗せて走って、毎日午前は筑紫、午後は都で勤務することができるようにした。その間の1500里を通ったという(『松浦廟宮本縁起』と『古今著聞集』第30)。
しかし、それほどの名馬なのに、ただ「竜馬」としてうわさされただけで、特に名は伝わっていない。思うに、子どもが飼い犬のことを単に「シロ」とか「アカ」とか呼ぶように、その頃までは「天斑駒(あめのふちこま)」とか「甲斐の黒駒」とか、産地と毛の色で呼んだに過ぎなかったのだろう。
その後になっても、信州の井上から後白河院に献上された馬を「井上黒」、武州河越から平知盛(たいらのとももり)に進ぜられたのを「河越黒」と呼んだりした。余りにも黒いから「するすみ」(磨る墨)、馬も人も食ってしまうから「いけずき」(生け唼き)など、多くは毛の色や、産地、気質などによって名づけられている。遊女が摂津の浪速(なにわ)で営業しているのもまた、仏法のお力というわけだ。同じように「乗り物」として扱われた遊女が馬と同名という例があるかどうかはわからない。ただし『遊女記』には「小馬」という源氏名が載っている。
インドで有名なのは「犍陟駒(こんでいごま)」で、後にブッダとなる悉達太子がこれに乗って宮殿から逃れた。その前世は帝釈天だったらしい(『六度集経』8)。ヨーロッパで馬に名前を付けることはよほど古くからおこなわれていた。「ジケア」というメス馬がアリストテレスによって記録されている。アレクサンドロス大王の乗馬ブケパロスについては、「馬の能力はスゴいんだ」の節で紹介した。古代ローマとその属領の上流の家では、馬屋の間ごとに住んでいる馬の名を掲げ、その表札が今でも残っている。また娼家の源氏名の表札も同じく残されている。
このついでに、イギリスの船長セーリスの『平戸日記』の慶長十八年〔1613年〕の記事を紹介しておこう。6月21日、平戸の殿様が女芸人数名を連れてイギリス船を訪問した。この一団は島から島へと渡って芸を見せ、演題によって衣装を替える。趣向は、もっぱら戦(いくさ)ものと恋だ。みな一人の興行主に仕えていて、その利益のために働く。ただし興行主は、もし上前をはねたりして訴えられると、死刑に処せられる。最も勢力のある貴人も、旅中の宿屋にこの一団を招いて、値を決めて女芸人を召して酌をさせ、自分のものとすることを恥じない。
芸妓たちの興行主は、生きている時には貴人の仲間にも入れてもらえるが、いったん命が尽きると、最も卑しい民としてさえ遇されることはない。口にワラで作ったものをかませて、死んだ時の服のままで街中を引きずり、野原の掃きだめに捨てられ、ニワトリや犬につつかせる。これはセーリスが眼前のできごとを見聞したまま書いたものとして、事実だと思われる。娼家の主人を「クツワ」と呼ぶのは、こんなところから起こったのだろう。(つづく)
(まつい りゅうご・龍谷大学国際学部教授、南方熊楠顕彰館館長)
本連載第1回掲載後、京都大学名誉教授の金文京先生から漢文についてご指摘をいただき、それに基づいた修正をおこなっている。金先生には、第2回以降の原稿についてもご教示をいただいた。この場を借りて感謝申し上げたい。