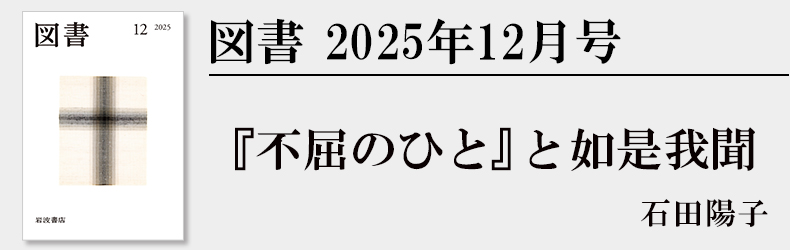石田陽子 『不屈のひと』と如是我聞[『図書』2025年12月号より]
『不屈のひと』と如是我聞
わたくしは編集者として長年本づくりに携わってきた。『不屈のひと 物語「女工哀史」』(岩波書店、2025年6月刊)は初の単著となる評伝小説である。
主人公はトシヲという名の女性。100年前のベストセラー、『女工哀史』の著者細井和喜蔵の妻で共作者でもある。彼女が劣悪な労働環境の紡績工場で、女工として働き始めたのはわずか10歳のときだった。その後も女給、闇屋、ニコヨン(失業対策の日雇い労働)という下層労働に従事した。学歴も縁故もない彼女は社会の底辺で生きざるを得なかった。そして関東大震災、無差別空襲、戦後の食糧難をくぐり抜け、組合潰しに抗しながら労働組合運動に精魂を傾けた。1920年代から60年代にかけて、この国の惨禍をすべて体験することになる。苦しい暮らしのなかでも闘うことをやめなかったのは、生来の負けん気もあるが何よりも、人間らしく生きたかったからである。
巻末に「主要参考文献」を掲げてそれは7ポ二段組6ページにもなったのだけれど、執筆の道しるべとなったのはこれら文献だけではない。筆を止めて考えこむ時、心の中に大切にしまっておいた言葉が浮かんで文章の流れを導いてくれた。それらは仕事を通じて縁を得た、達人たちの言葉である。
半藤一利さんの言葉
「とりとめないお喋りのまとめは、今度も石田陽子さんがやってくれた。彼女とは、とにかく長い付き合いである。どうやら私のことなら私以上に知っているらしく……」。『失敗の本質 日本海軍と昭和史』(毎日文庫)のあとがきで、こんな冗談を交えて半藤さんは、裏方のわたくしへの謝辞を書いてくれた。
“長い付き合い”のなかで、半藤さんが聞かせてくれた言葉のいくつかを作中に忍び込ませてある。
大正12年9月1日。大震災発災後、川合義虎(序盤の重要な登場人物・亀戸事件で虐殺された21歳の労働運動家)が、出先からの帰途、被災した母子に偶然出会って母親を倒壊家屋から助け出そうとした場面にそれはある。
「母親の衣服に火がついた。髪の毛がカンナ屑のようにパッと一瞬で燃え上がると、全身が猛火に包まれていった」(75頁)
14歳の半藤少年は、昭和20年3月10日の東京大空襲を辛くも生き延びる。猛火に追われて逃げた先の中川の川岸でこの悲惨な現象を見た。
半藤さんは晩年、あの被災体験を語る時、この様子を幾度も口にした。恐ろしい目撃証言なのである。
東京大空襲の恐怖というものが、半藤さんの脳に深く刻まれて決して癒えることがなかったということを、あるときわたくしは思い知る。半藤さんは「花火が大嫌い」と常々言っていた。大きな打ち上げ花火は焼夷弾の降るさまそっくりなのだと。そしてある時こうつぶやいた。「花火を見ると、必ず頭の芯が痛くなる」。
あれから七十数年もの月日が流れても、被災の恐怖はトラウマになっていた。外見からはわからない。けれどその心には癒えることのない火傷の痕が残された。
関東大震災被災後、主人公トシヲは夫の細井和喜蔵とともに東京を逃れ出る。故郷、岐阜東津汲でのエピソードを綴っていたときにも半藤さんの言葉を思い出した。桑畑の脇の切り株にふたり並んで腰掛けて、トシヲは和喜蔵から、その祖母と母との間に確執があったことを聞く。あげく母が自死したことを聞いた時の心理描写だ。
「血を分けた母娘なのに、我がせめぎ合い、意地を張り合い、互いにどれほど傷つけあって深い傷を心のうちに抱いていたことか。ふたりとも被害者であり加害者でもあるという寂しい事実がそこにあった。関係がこじれると、他人よりむしろ肉親のほうが他者性を強めるという逆理がある。残酷にもなる」(141頁)
後半部分は半藤さんが聞かせてくれた言葉そのものである。そんな体験が自分自身にあったのかどうかは語らなかった。わたくしもそれは聞かなかった。けれど半藤さんは、そういう人間の哀しさを知っていた。忘れてしまわぬよう、この言葉をその晩、日記帳に書きつけた。
澤地久枝さんの言葉
「いわばわが人生のアンソロジーです」。
全著作に目を通してわたくしが編んだアンソロジー『昭和とわたし 澤地久枝のこころ旅』(文春新書)について、澤地さんはこう評してくれた(「あとがき」より)。この仕事をきっかけとしてお付き合いが始まって、わたくしはもっぱらお話を聞かせていただくのである。
昭和20年8月6日の西宮大空襲で焼け出されたトシヲは、直後に、高井信太郎(2度目の結婚相手)も失って、戦後の過酷な生活が始まる。子どもは5人。稼ぎを得る手段は日雇い労働しかなかった。が、地元伊丹市の支払い額は、失対労働の俗称「ニコヨン(日給240円)」にも満たない160円。これでは一家が食べていけようはずがない。
待遇の改善を求めて、トシヲは労働組合「伊丹自由労働組合」の立ち上げを企図するのだが、当局の妨害に遭い仲間たちからそっぽを向かれてしまう。状況打開の契機とすべく映画会を開催することをトシヲが思いつくくだりで、澤地さんの言葉が助けてくれた。
「信太郎ならこう答えるだろう。「文化や芸術は上級市民にだけ許された贅沢品なんかじゃない。自分たち貧乏人にとっても、誰にとっても人生の必需品なんだよ」と」(292頁)
澤地さんはたいへんな映画好きで、話題作はほとんどご覧になっていた。お誘いして一緒に映画鑑賞したあとの食事のテーブルで、澤地さんはこうおっしゃった。「映画は人生の必需品ですよ」と。
その言い方は「当たり前です」とも言いたげな、じつに確信に満ちた感じなのだった。
芸術・文化はたとえファシズムの時代にあっても魂を救ってくれる。それらには人と人とのコミュニケーションを後押しする力がある。澤地さんは、そう思っておられるに違いない。映画は必需品。わたくしはこの言葉に感じ入った。
金子兜太さんの言葉
最終章では昭和48年の夏を描いた。晩年を迎えたトシヲは20年間働いた失対をやめて2年が経っている。お盆が近づいて、その晩、トシヲは亡くなった人たちをこんなふうに思い出している。
「西宮大空襲で、関東大震災で見たそれと匹敵するほど大量の、無惨な死体を見たのが8月6日。和喜蔵が無念の死を迎えたのは8月18日。帰国の資金にとミルク缶にお金を貯めていた徐景秀さんが、墓参の夢果たせぬまま交通事故で亡くなったのも、そういえば8月のお盆過ぎだった。失対の現場はトラックなど工事用車両による交通事故死が多かった。伊丹自労でずっと一緒に闘ってきた、池内政光さんが57歳で亡くなったのは、そう、8月22日だ。……胃がんで闘病していた池内さんの、死に目にあえなかった悔いはいまも残る。
ほんとうに意見がよく合って、池内と高井は仲が良すぎると仲間から陰口を叩かれたこともあった。息を引きとるときこう言い遺したそうだ。
「またいつか逢いましょうと、高井さんに伝えてください」
亡くなった人は、ここではないどこかにきっといる。そうトシヲは信じている。池内さん、逢えるといいなあ、またいつか。願いをこめて麦茶を飲み干す」(330―331頁)
「亡くなった人は、ここではないどこかにきっといる」
これは金子兜太さんの言葉である。
兜太さんの長い語りをまとめる仕事をしたことがある(『悩むことはない』文春文庫)。
兜太さんは、10年も続けている朝の日課があると教えてくれた。立禅。立って行う瞑想である。神棚の前に立って亡くなった130人ほどの知人たちの名前を、お念仏のように声に出して連綿と唱え続けるという。容易いことではあるまい。どうやってそのやり方を会得したのか尋ねると、こう教えてくれた。
「記憶するということは、映像をともなっていないと難しい。名前だけだと忘れてしまいがちだ。だからわたしは死んだ人の映像を思い浮かべることにした。さらに順番を決めたから、リズムが生まれて名前はバンバカバンバカ滑らかに出てくるようになったんだな。
死んだ人たちと一緒にいるような気持ちになれるから、これもまことに有難い。名前をずっと言っていると、その人たちがみな生きているように見えてくる。やがてわたしは、死んだ人は別のところにいるんだと、確信を持つようになった。死んでも命は残る」
敗戦間近のトラック島で、非業の死を嫌というほど見てきた兜太さんの、この言葉には凄みがあった。
トラック島は、東京から南へ3,500キロ。ドイツの植民地だったが第一次大戦後の大正8年に日本の委任統治領となり、日本海軍の一大拠点であった。
昭和19年3月。24歳の兜太さんは海軍中尉としてトラック島に赴任する。着任の半月前に、アメリカ機動部隊の大規模空襲を受けて基地機能は壊滅している。敵上陸を予測して防衛態勢を固めるべく、要塞構築・土木工事の指揮を執るのが任務だった。あにはからんや米軍は、トラック島ではなくマリアナ諸島のサイパン上陸作戦をとる。サイパンが猛攻撃を受けて7月に陥落するとトラック島は完全に孤立。武器弾薬と食料の補給は途絶えて食料不足がたちまち深刻化した。
栄養失調者は眠ったまま死ぬ。朝、起きてこない者が増え、飢餓とそれによる人心の荒廃がさまざまな悲劇を生んでいく。1本のイモを盗んだ咎でなぶり殺しにされたものもいた。トラック島における軍人軍属の死者は約8,000人と言われているが、その多くは餓死だった。
兜太さんは敗戦から1年3カ月も経った昭和21年11月に帰国する。年配者と妻子のある者から先に帰し、自身は最後の引き揚げ駆逐艦に乗った。島を離れるとき、甲板から山の麓のたくさんの墓碑が見えて、非業の死者たちに見送られるのを感じたと、91歳の兜太さんは言った。
「亡くなった人は、ここではないどこかにいる」。
70歳のトシヲにそれを言ってもらった。トシヲもまた非業の死をたくさん見てきたひとだった。
(いしだ ようこ・文筆業、編集者)