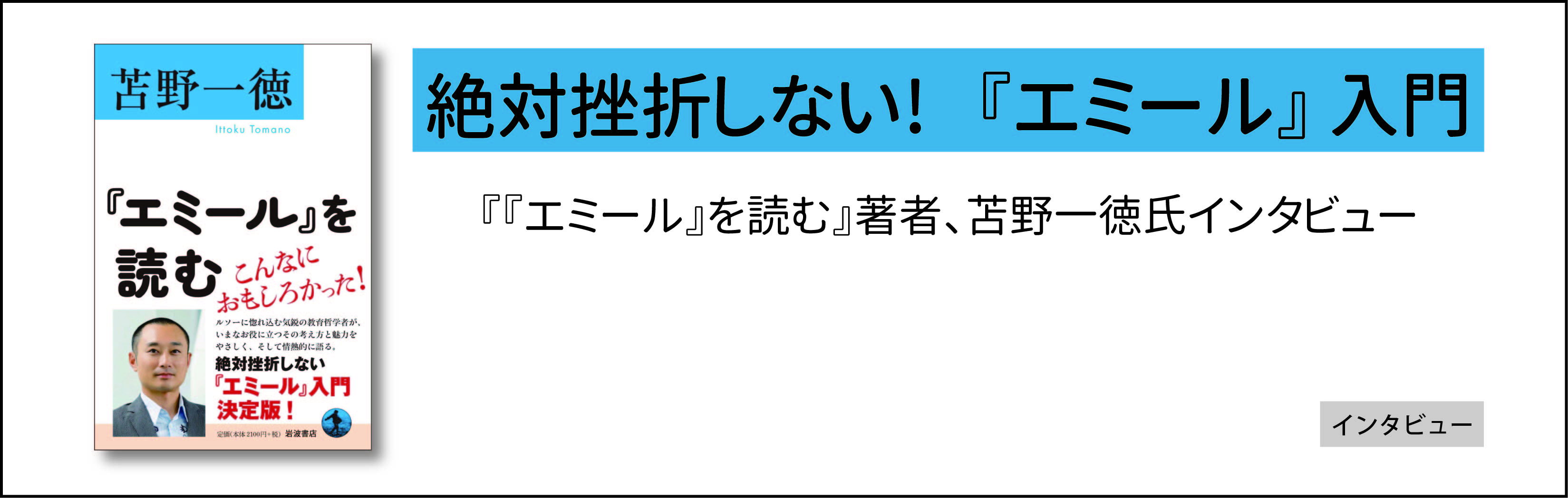絶対挫折しない『エミール』入門――『『エミール』を読む』著者、苫野一徳氏インタビュー
現代の教育に最も大きな影響を与え、教育関係者は誰もが知る名作中の名作、ルソー『エミール』。ただ、その知名度に比べて、中身を読んだ人はそれほど多くはないとも言われます。
でも、それはもったいない。教育哲学者の苫野一徳さんは、『エミール』は現代の私たちが読むことで、実に多くのことを発見できる作品だと言います。
今回、その名作に親しむための入門書『『エミール』を読む』を書き下ろした苫野さんに、新著と『エミール』のおもしろさについて語っていただきました。(聞き手:岩波書店 編集部)
「同じたましい」の持ち主との出会い
――苫野さんがはじめて『エミール』を読んだときの印象はいかがでしたか?
実ははじめて読んだのがいつだったのか、よく覚えていないんです。ルソーとの出会いはよく覚えていて、18歳のころに読んだ『告白』でした。当時わたしは躁うつ病(双極性障害)が酷く、精神の浮き沈みが激しかったんです。その中で『告白』を読み、文学・芸術・哲学的な関心からルソーと共鳴しました。
若い頃って、自分と「同じたましい」の持ち主と出会いたい、と思うことがありますよね。それが偉大な人だと、なお嬉しくなっちゃう。それで、「このルソーという人は自分と「同じたましい」の持ち主だ!」「わかる、全部自分にはわかる!」と、のめり込んで読みました。
今考えると、やっちゃいけない最悪の読み方でした(笑)。もちろん哲学に限らず、文学や音楽でも「これは私のために作られたものだ」と感じるような出会いは、取っ掛かりとしてはとてもいいものです。ただ、「ルソーは私だ」となってしまうと、自分の読みたいようにだけ読んでしまう危険性がある。だから「本当にそうなのか」と吟味・検証しながら読んでいくことが本当は大事なのです。
それはともかく、『エミール』を読んだときもおそらく同じでした。本書にも少し書いたことですが、『エミール』の記述には、ルソー自身の満たされなさの反動があるんじゃないかと思っています。ルソーは人を強く愛すると同時に、人に対して不安や恐怖、猜疑心を強く抱く人物でもあったようです。だから「子どもたちが自分のように苦しむのではなく、本当にすくすくと生きられるには、どんな環境がいいか」を徹底的に考え抜いたんだろうなと思い、それも自分と共鳴するように感じました。
――苫野さんはこれまで多くの本を出していますが、特定の人物や著作に関するものは『社会契約論』に続いて今回の『エミール』と、ルソーの2冊のみです。ルソーはやはり特別なんでしょうか?
そうですね。もし自分が入門書を書くとするならば、ルソーをおいて他はない、と思っていました。
「ルソーの言いたかったことを、俺はもっとうまく現代人に伝えてやるからな」
――編集者の欲目かもしれませんが、苫野さんの他の著作と比べても、本書は『エミール』への情熱といいますか、「ほら、こんなにおもしろい! すごい!」といったのめり込み方や読者へ語りかける熱意が一味違うような印象があります。
そうだと思います(笑)。個人的なことですが、去年は体調が悪い時期があり、精神的に落ち込んだりしてもいたんです。少し元気になってきた頃にこの本の準備をしようと思い、『エミール』を読み直しました。そしたらもう、「やっぱり『エミール』は最高!」と一気に読んでしまったんですね。そしていろんな文献も渉猟して見通しが見えたところで書き始めたら、「恋愛状態」に入ってしまい、2週間で一気に草稿を書き上げてしまいました。
こういう「ゾーン」に入る経験はなかなかできることではなく、やはり『エミール』だからだと思っています。もちろん、若い頃のような「最悪な読み」に基づいて書いた、ということではありませんよ(笑)。哲学者として、ルソーの言っていることはどうなのか、吟味するために著者と対話するステップを経て、本書ではルソーの言わんとすることの心臓を掴み取ろうとしました。つまり、ルソーの言いたかったことはここだろう、それは俺もよくわかるよ、と。そして「お前の言いたかったことを、俺はもっとうまく現代人に伝えてやるからな」というつもりで書いたんです。
というのは、教育学や教育哲学、思想研究には、対象を外から見て分析するというスタイルが多い。ルソーや『エミール』の研究をみても、多くは「歴史的遺産」として取り扱っている印象です。それは研究としてはもちろん大事なんですが、それだけでいいのか、という気持ちもありました。『エミール』を、現代の教育や子育て、さらには私たちの生き方にとっても、とことん役に立つものとして改めて伝え直したい。そう願って書きました。
『エミール』は洞察の宝庫
実際、ルソーの洞察は凄まじい。本書でも言及していますが、実はルソー自身は自分の子どもを育てることができずに孤児院に預けており、そのこともよく批判されています。ただ逆に、「自分で育てていないのに、なんでこんなに本質的なんだろう? こんなことまでわかるんだろう?」と思うくらい、子どものことをよくみていることが伺えます。まさに洞察の宝庫なんですね。『エミール』のなかでも、大事なのは子どもを見ることだと、その観察眼を自分で誇っていますし、読む側もやはりそれに魅了されます。
――『エミール』で描かれている子どもの振る舞いや成長の姿は、今の我々からみても非常に緻密ですし、その教育についての大人批判も「確かに!」と納得させられるところが多いです。
『エミール』での緻密な子どもの描写は、ある面においては、実はルソー自身のことだという気もするんです。彼は自己了解能力が非常に高いので、「私は何者なのか」「自分はどう生きたいのか」「なぜこんなに苦しむのか」と、子ども時代からずっと考えてたんじゃないかと思うんです。そして後になって、「あの頃こういう経験ができたらもっと幸せだったかな」「親方から叩かれまくったあの経験が自分を歪めた、不道徳にした」とか、そういう自己分析をして、それに基づいて子どもの学びや育ちについて書いたんじゃないか。
ルソーの文章の魅力は、切れば血肉が出てくるような生々しさにあるのですが、『エミール』のそれも、彼が自分自身のことを書ききっているところにあるのではないか。だから私たちは、ルソーの肉声と格闘しなければいけない、という気持ちになるのかもしれません。
「理想」ではない。現代なら実現できる
――ルソーの時代から二百数十年が経ち、教育の方法や技術、科学的な知見もずっと進歩しています。その現在に『エミール』を読むことの意味を改めてお話しください。
「教育思想なんて意味ない」「昔の人の言っていることでしょ、それに学術的な裏付けがあるの?」という声も聞きます。ですが、じつに表層的な批判です。古典がなぜ残ってきたかというと、「人間とはどういう存在なのか、だとすると教育とは」といったことを考え抜いたものだからなのです。
今の教育研究や実践は、どうすれば学力が上がるか、学級経営がうまくいくか、そういったところに目を向けがちです。でも、「そもそも人間とはどういう存在か」を考えることが抜けたら、教育の一番大事なところも抜けてしまう。そうした思考のリレーを引き継ぐのが、古典を読むということなのです。それを通じて、「ああ、自分は今まで表面しか見てなかったな」と気づくこともあると思うんです。
大人からすると、いい子、成長している子というのは、「言うことをちゃんと聞いて、整理整頓ができて、規則正しくしていて……」と考えてしまいがちですよね。同じように、教育学や教育実践も、「どうしたら◯◯ができるようになるか」という問い(リサーチクエスチョン)を立ててしまいがちです。ところが『エミール』を読むと、そうしたそもそもの問い自体がそれでいいのか、ということに気づかされ、はっとすることになるはずです。それを現代に伝えたいという意図も、本書にはあります。
――本書では伊那市立伊那小学校、サドベリーバレースクール、きのくに子どもの村学園といった現代の学校もルソーの思想と重ねて紹介しています。それは、本書でも強調している「『エミール』の考えを現代に活かす」という意図なのでしょうか?
そのとおりです。「『エミール』は理想論だよね」と言われることがあります。でもそんなことはありません。それこそ、ルソーの時代であれば難しかったであろうことが、今なら十分実現できるわけです。二百数十年の歳月を経て、ルソーの思想を体現したような学校や実践が、すでにたくさん登場しているんです。だから、単に「『エミール』にはこう書かれています」と解説するのではなく、じゃあ現代において、そんな教育は具体的にどうすれば可能なのかということも、ふんだんに書きました。
古典の「時代の時代性」をどう読む?
――『エミール』第五編ではエミールの結婚相手であるソフィーの描写を通じて、女性の教育について語られます。ですが、今われわれが読むとかなり違和感を覚える箇所でもあります。こういった点についていかがでしょうか?
この箇所は、『エミール』の中で今日もっとも評判が悪いものです。男女の教育は異なっているのが「自然」であると論じていて、今の視点からすると大幅に修正しないといけない内容なのは確かだと思います。
ただし、いくつか考えるべきポイントがあります。まず『エミール』が書かれた「時代の時代性」です。それこそ今の私たちの価値観も、百年後・二百年後の人々からみたら「なんて問題だらけなんだ」と思われかねないことがたくさんあるでしょう。大前提として、ルソーの時代は男性優位社会で、「男とは/女とはこういうもの」という考え方が圧倒的に強かったわけです。それを理解せず、今の私たちの目から「おかしい」と批判するだけでは、後出しジャンケンになってしまいます。
それにルソーの議論は、実は当時としてはかなり進歩的なんです。というのは、ルソーは「男女は平等である」とはっきり言っている。違うのは生殖面のことだけだと。ただ、その生殖面での違いがある以上、男女の教育にもいくらか違いがあるのが自然なことだとルソーは言うんですね。そこで出てくる男女の教育論が、現在からみて問題が多いのは確かです。ただしその当時としては、「非常に」とはいわないまでも、かなり進歩的だったことは理解しておく必要があります。そうしたことも含めて、ルソーの女性観や女子教育論、また、それを現在どう読むべきかについても本書では紹介し、論じています。
なお、こうした男女観、および先程少し言及した「ルソーは子どもを孤児院に入れていた」ことを根拠に『エミール』全体を否定的に見る向きもあるようです。ただ、それはフェアとはいえません。個別にその点を批判すればいいのであって、その優れた洞察の全てを否定するのは、適切な論じ方ではないでしょう。
もう一つ、これは仮説なのですが、もしかしたらルソーはあとになって、その女性観や女子教育論を根本から見直した可能性があります。実は『エミール』には未完の続編があるんですが、それを読むと、その可能性が浮かび上がってくるんです。これについては本書の「終章」で論じましたので、ぜひお読みになってください。
子どもとの関わりに役立ててほしい
――苫野さんは「教師、保育士、保護者といった子どもに関わる方にぜひ読んでいただきたい」と仰っていますよね。そうした方たちへのメッセージをお願いします。
普段、教育や子どもとの関わりで苦しいと感じる方もおられると思います。それは、仕事の仕方やノウハウなど、表面的なところで大変に感じることもあると思うのですが、しばしばその根底には「自分はなんのために子どもと関わっているんだろう」「本当にこのままでいいのか」「何を目指していけばいいのか」という問いがある場合もあるんじゃないかと思います。そのとき、ちょっと立ち止まって考えることで、いろいろな問題がすべて繋がって氷解していくことがあります。「自分がやりたかったのはこういうことだったんだ」「目指すべきはこういうことだったんだ」と理解することで、全てきれいに解かれていくことがあるんです。それができるのが、哲学や教育哲学、教育思想というものの力です。『エミール』は、それにまさにうってつけの本なんです。
とはいえ、文庫で全3冊にもなる『エミール』を読み通すのはなかなか大変ですし、読み慣れていない方には難しいのも確かです。だから、まずはこの本で全体像やエッセンスを掴んでほしいです。編集者は「絶対挫折しない」というキャッチコピーをつけてくれましたが(笑)、エミールを楽しんで読んで、役に立ててもらうことを心がけて書いたつもりです。本書を読んだあと、ぜひ実際に『エミール』を1日10分ずつくらいでもいいから、少しずつ読んでみてほしいですね。そして、ご自分なりの発見をしてくれることを願っています。