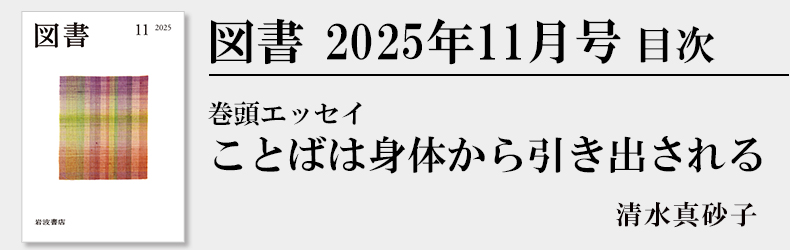『図書』2025年11月号 目次 【巻頭エッセイ】清水真砂子「ことばは身体から引き出される」
失われた故郷への憧憬……東山彰良
会いに行ける奇跡のネズミ……黒岩麻里
歴史に生きる一人として……落合由利子
子どもとプログラミング……原田康徳
読書とプロレス……大森隆男
日本文学研究と教育の50年(上)……ハルオ・シラネ
『はるかな国の兄弟』──未来の時間と賭けること……河合俊雄
イメージはどこから生まれるのか……齋藤亜矢
2400年にわたる哲学/17世紀哲学の重鎮たち……山本貴光
絵本と人の物語を味わうカフェ……大和田佳世
『静かなドン』にみる共同体家族とボルシェヴィキ的組織との類似……鹿島茂
11月の夜長に思いだすこと……柳家三三
11月、深まる秋には堅い殻……円満字二郎
夢の歌……中村佑子
11月の新刊案内
[表紙に寄せて]永遠にラフである 石松佳
はじめて「ゲド戦記」シリーズを翻訳したのは30代半ばのことでしたが、たくさんの登場人物それぞれの背景を押さえたうえで訳すことができたのか、いまでも不安です。訳者の感覚をうっかり持ち込んでしまってはいないだろうか、その登場人物のことをわかった気になってはいないだろうか。
ことばは生きもので、身体的なものです。「ゲド戦記」は少年の成長の物語であり、第4巻以降は、歳を重ねていくことの物語です。ことばづかいも歳とともに変わりますが、その人物との付き合いのなかで、ていねいに追っていくしかありません。物語に書かれていない場面では彼らはどうしていたのか、考えることからそれは始まります。そこから読む楽しさにつながり、すべての登場人物に人生があると知る喜びにもつながります。
この人はどんなことばをつかうのか、ことばを自分の身体から引っ張り出してきて、考える。それはいろんな人物を身体感覚で味わうということでもあり、息づかいのようにことばを感じることでもあります。演劇に直接関わったことはありませんが、演出家はきっと脚本を前に、訳者と同じような気持ちになられるのではないでしょうか。
(しみず まさこ・翻訳家)
〇 猛暑の合間に豪雨雷雨の襲う長い夏。いつまで続くのだろうと辟易し、そのうち秋になったのかどうか曖昧なまま、体調管理に気をつかう日が続きました。然は然りながら、海からは秋の恵みも。
〇 今年は大ぶりでよく脂の乗った秋刀魚に、鮮魚店でもスーパーでもちょくちょくお目にかかり、久々に塩焼の王様を堪能しました。国際的な資源管理の進展や、海中の餌の状態が良好なこと等の要因が考えられるそうです(読売新聞オンライン、8月29日)。鰯も、丸々と太って青光りしたものがよく出ていました。気象庁の発表では、過去最長八年近く続いた「黒潮大蛇行」が終息して鰯の水揚げ量が回復した可能性があるとか(中京テレビNEWS、9月26日)。海の幸で十分に栄養を摂って短い冬に備え、秋の夜長の読書三昧といきたいところです。
〇 昨年11月に亡くなられた谷川俊太郎さんの対話集『本当のことを言おうか谷川俊太郎精選対話』をこの10月より全3巻で刊行しています。「本当の事を言おうか/詩人のふりはしてるが/私は詩人ではない」(詩集『旅』1968年所収「鳥羽1」より)。そんな詩を書いた谷川さんが最も精力的に活動していたおもに1970年代から80年代に行われた対談から選りすぐりました。
〇 インタビューではないこと、そして谷川さんと対談者が対等の立場で真正面から意見をぶつけ合っているかどうかが選出の基準。第1巻の巻頭は哲学者で父の谷川徹三との対話「動物から人間になるとき」。1961年、66歳と29歳の親子が向かい合います。
〇 「俊太郎 子どものころは、ぼくが何かしてむずかるでしょう。すごく離れた書斎から、うるさいという声がとんでくるの。これが恐怖だったな。父親のイメージというのは、そういうところにあったよ(笑)。〔…〕いっしょに遊んでくれないし、ときどきどなる動物だと思っていたな。/徹三 両方とも動物……(笑)。/俊太郎 とにかく幼児のころ、ぼくが寝ちゃうと夫婦でダンスホールへ行ったりなんかしたでしょ。ぼくは夜中に目を覚ますといないでしょう、父親も母親も。子どもなりに孤独感を感じてさ、そのときに詩人的要素が養われたんじゃないかと思って感謝しているけれどもね(笑)。/徹三 俊太郎が完全に人間になったのは、詩を書きだすようになってからだろうね」
〇 初期エッセイのほか、第1巻と第2巻には谷川さんの貴重な「ひとり語り」も収録しています。
〇 受賞報告です。渡邉雅子さんの『論理的思考とは何か』(岩波新書)が第34回山本七平賞を受けました。また、小誌連載から岩波新書になった『東京美術学校物語』と著者の新関公子さんに対して、2025年度第4回日本フェノロサ学会特別功労賞(ビゲロー賞)が授けられました。