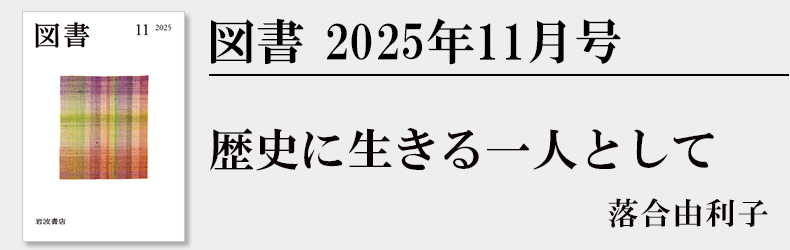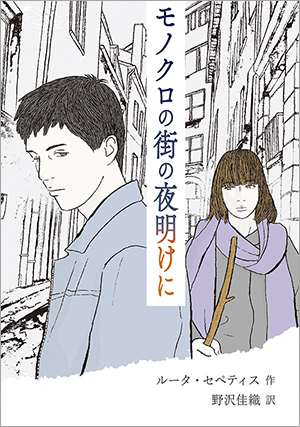落合由利子 歴史に生きる一人として[『図書』2025年11月号より]
歴史に生きる一人として
昨年10月、立て続けに3つのギャラリーから写真展の依頼をいただいた。さすがに3つ目の話をいただいた時は、ワクワクを通り越して、できるかな……と考えた。そしたら親しい友人が静かに凄んだ。
「やれ、己のキャパシティーを広げろ」
長く私の作品を見てきた彼女は、「やるやる」と言い続けて動き出さない私にヤキモキしていたのだ。その言葉に押された、やるしかない。私にとって怒濤の2025年が始まった。
1つ目の写真展は4月。「東欧1989 EASTERN EUROPE」を展示したいと思った。そして同時に写真集も出版することに決めた。
それは1989年ベルリンの壁崩壊直後のベルリン、チェコスロバキア(当時)、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアを3ヶ月かけて巡り撮影した写真群だった。
それらは帰国後に写真集出版という機会を得たのだが、出版社の事情で最終的に実現に至らなかった。写真集として産み出す作業を終え、印刷工程に手渡す状態に仕上げたファイルを、私は持ち続けていたのだった。
自分がなぜあの時期に東欧に行ったのだろうと考えると、それはジャーナリスティックな視点とは少し違うものであった。
1989年11月、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊した。そのニュースは世界を駆け巡った。壁によじ登り抱き合う東西ベルリン市民、シャンペンを飲み交わし、歌を歌い、ハンマーで壁をたたき割り、放心したように空を見上げ国旗を振り続ける、そんな人々の姿がテレビに映し出された。すごいことが起きたと思いながら、事の次第がよくわかっていなかったようにも思う。
そして知りたいと思った。テレビのモニター越しではなく、そこに暮らす人たちに一人の人間として出会いたい、会って話してその手に触れてみたいと思った。そしてこれからどんどん変わっていくであろう土地の人々や光景を、写真に留めたいと思った。それは何かの予感のようなものだった。

自費出版 yurikoochia.theshop.jp
私の写真行為は、機動性の悪い6×6判の中判カメラで「撮りたい」という気持ちがどこからともなく湧き起こってきて、その気持ちが通じ合えた瞬間の人や光景を撮り続けたものだった。
これらの写真は、36年前の歴史の転換期に一人ひとりの人が「いた」という過去形でなく、「人々が存在している」ということを、現在形で今に届けられるのではないだろうか、それによってこの混迷の時代に何かしら想像力の扉を叩けるのではないかと思ったのだ。
ファイルの写真は出版には至らなかったわけだが、一度写真集の形にまで仕上げたものを作り変えるのは勇気のいる作業だった。が、時を経て編み直す醍醐味を味わうことになった。
ベタ焼き(フィルム1本分の全カットを1枚のプリントにしたインデックス)の束を見返すまでは、冬の東欧の寒さが感じられるような体感的な写真を増やしたいと考えていたが、目を通し始めると、新たに加えたいと思う写真はほとんどが人物のポートレートだった。写真がもつ記録という特性が忘れてはいない記憶の扉を開けていく。まさにタイムスリップだ。
東欧に滞在した3ヶ月の間に、ルーマニアでは23年間続いたチャウシェスク独裁政権が市民による「革命」で倒れ、チャウシェスク夫婦の処刑という形でピリオドを打つことになる。私はこの時、隣国のハンガリーにいた。状況がままならない中で封鎖された国境の駅まで行ってみることにした。そこに居た一人の青年が気になり声をかけたが、話がうまく進まない。撮影は難しいだろうと思いながらも頼んでみると、意外にもすんなりカメラの前に立ってくれた。撮影はさせてもらったのだが、当時の私は彼のどこか陰鬱な表情が受けとめきれず、セレクトから外していた。けれど今回はそのカットから目が離せない、彼が何を抱えているのかはわからないが、その存在を大事に現したいと思った。こんなふうに何人もの人が新しい写真集に登場することになった。
2度目の写真集制作も佳境となり、セレクトや構成はもう変えることができない段階になったある夜、作業机に並べられたこれらの写真を見ながら、もしかしたら私は、とんでもない勘違いで自分本位なものを作ろうとしているのではないだろうかと、急に不安になった。すると、この1、2ヶ月間ずっと向き合ってきた目の前の写真の中の人たちが、みんな同じ気持ちでいるような感覚を味わったのだ。長いことファイルの中にいた人たちがみんな出ていきたがっている、間違ってない、大丈夫だ。なんだか勇気が湧いてきた。
写真集は思っていた以上のものが出来上がり、写真展も多くの人に足を運んでいただけたが、まだもう少し広めていく活動をしようと思う、それはこれから。
写真展「東欧1989 EASTERN EUROPE」が終わると、2つ目の写真展が6月に迫っていた。準備期間は1ヶ月だ。ルーマニアの山間の村コルネレバで撮影した写真群を展示することに心を決めた。
東欧から帰国し制作に没頭した写真集が頓挫した後、私は、1年間は帰ってこないつもりで再びルーマニアに向かった。今度は旅人ではなく、住んで生活者として写真が撮りたい。それは大学卒業以来ずっと思っていたことだった。それを今やらないと次の自分がないというくらい思い詰めていた。今度は政治に翻弄された土地をめぐる視点ではなく、人間の根源的な生活の中に身を置いてみたかった。前の旅で感じたルーマニアの「土の匂い」をもう一度ゆっくりと確かめてみたい、そう思ったのだ。
まずはブカレストの知人を訪ね、自給自足に近い生活の村に知り合いがいないか聞いてみた。彼のおばさんの友人に農夫がいるということで、紹介の小さなメモを持ってその村へ向かった。
列車を降りてから5、6時間バスに揺られ、さらに小1時間歩いただろうか。私は電話もテレビもない山間の村、コルネレバの一軒の農家の大きな扉の前に立っていた。薄暗くなり始めたころ、道の向こうから農具をたずさえた人影が現れた。老夫婦に2歳くらいの子ども、そして若夫婦。彼らは差し出されたメモを見ながらなにやら相談しはじめた。私の笑顔はかなりこわばっていたと思う。しばらくして大柄な老夫は家の扉を開け、にこやかに招き入れてくれた。知らない国から来た言葉も通じない他人の私を受け入れてくれたのだ。
ジャガイモの収穫、ジャム作り、クルミ拾い、ツイカ(プラムの蒸留酒)造りと、冬支度で大忙しの日々。そこには大地の恵みと営みに満ちた世界があった。私は何を探しにこんなに遠くまで来ているのだろうと、自問自答を繰り返しながら、写真を撮ることを触覚のようにして探し続けた。
その答えは日本に帰ってから暗室でプリントをしながらわかっていくことになる。命と命が育っていく社会、命の輝き、命に当たる光。そういうものを感じ求めては捉えようとしていたのだった。

私の中には、今この写真を展示したいという確信のような感覚があった。
コルネレバで40日暮らした後、一旦ブカレストに戻った私は、そこで子どもを授かり、結婚した。1年後に帰国、日本での生活が始まるが、ルーマニア人の夫との暮らしは長くは続かず、シングルで2人の子どもを育てることになった。そんな時に保育雑誌で乳幼児を育てながら働く男性、女性の一日に密着して写真を撮るドキュメンタリーの仕事をした。たった一日だが確実に一生のうちの一日を、その人のリズムに入れさせてもらう。4年間で39人、39家族の日常を少しずつ共有した。雑誌の連載が終わり、単行本にするためにそれまで撮った写真を見返していた時、一枚の写真から目が離せなくなった。それは月曜日の朝の日の光が差し込む保育園の廊下で、布団を抱えて歩く母親の後ろを子どもが飛び跳ねるように追いかけている写真だった。親から子に流れているものが見えた気がした。一度見えると他の写真からもそれがどんどん見え始めた。私は4年間たくさんの写真を撮ってきたけれど、こういう瞬間にシャッターを切ってきたのだ、ということにその時気付かされた。私自身も小さい子どもを育てながら仕事をする身として、時々ふと本当にこういう生活がしたかったのだろうかと思うことがあった。そんな中で、これらの写真は目に見える形は違うけれど、ルーマニアの山間の村コルネレバで撮っていたものと根底に流れるものは同じだったんだと思えた。それは大きな喜びだった。
あの時得られた命への肯定感をもって、今、展示をしたいと思ったのだ。
写真展は村の入り口にある大きな石の写真で始まり、たっぷりと水をたたえて流れる小川の写真で終わる構成にした。この展示も多くの人に見ていただけた。またもう少し発展できたらと思っている。
そして3つ目の展示は、この原稿を書き終えたら着手するので、仮タイトルだけ書いておこうと思う。『絹ばあちゃんと90年の旅──幻の旧満州に生きて』(ギャラリーOGU MAG 10月23日―11月9日の木金土日に開催)。
最後になるが、ルーマニアのチャウシェスク独裁政権の末期と「革命」を走り抜けた17歳の高校生クリスティアンを主人公にした歴史フィクション『モノクロの街の夜明けに』(ルータ・セペティス作/野沢佳織訳)に触れておきたい。
作者ルータ・セペティスはリトアニアからの亡命者を父にもつ、リトアニア系アメリカ人だ。70人以上の人々への綿密なインタビュー、徹底したリサーチの上に生み出されたフィクションは時に叫びたくなるような実感をもって迫ってくる。
チャウシェスク独裁政権下のルーマニアでは国民が海外に出ることはもちろん、外国人と接することさえ許されていなかった。セクリターテと呼ばれる秘密警察が人々を監視し、恐ろしい脅迫や叶わぬ甘い条件をぶら下げて市民の中にたくさんの密告者を作り上げていった。人が人を信じられなくなると何が起きるか。クリスティアンが敬愛する哲学者でもある祖父は言う。「独裁政治ってのは楽なもんだ!」「我々を支配するのに、武器もいらんのだからな。恐怖に陥れるだけで十分ってわけだ」。
私は、チャウシェスク政権が倒された直後の1990年1月7日に、首都ブカレストに入っている。街のあちこちにろうそくが灯され、花が供えてあった。多くの命が革命と引き換えに失われた場所だという。私もろうそくを灯し、心をこめて丁寧に写真を撮った。シャッターの音に振り返った男性に「あなたの国の一人でも多くの人に、21世紀を前にルーマニアではこんなふうにたくさんの人が殺されたということを伝えてください」と言われて、大きな手で握手を求められた。これからこの国は変わるのだという熱気のようなものが人々から伝わってきた。しかし私が2年後のブカレストにアパートを借りて住むころには、人々の熱気はすっかり冷めていた。独裁政権下の後遺症を引きずる体制はそんなに簡単に変わるものではなかった。
物語の中で、主人公クリスティアンの母親ミョアラが3時間も行列に並んでやっと手に入れた油の瓶をアパートの階段で割ってしまうシーンがある。私が暮らしていたころも、街で行列を見つけると何が売っているか確かめ、それが家になければ長い列に並んで買っていた。それでも午前中の市場だけは近郊の農家から運んでくる不揃いだけど美味しい野菜や果物が並ぶ。特に露店の花屋は色とりどの花々で心を和ませてくれた。
ある日、花屋に義父の姿をみつけた。義父はウクライナに程近い村の出身で、アパートのベランダでワインを造ったり、バスタブで鶏を解体するような、おおらかで愉快な人だった。そんな彼が何軒もの花屋をのぞいては店の主人とジョークを交わし、一本一本香りを確かめながらバラの花を買っていた。私は気づかれないように、そっとその場を後にした。翌日バラの花束を抱えた義父が「結婚のお祝いだよ」とアパートを訪ねてくれた。第2次世界大戦、その後のチャウシェスク独裁政権を生きた義父は1997年に67歳で亡くなった。
『モノクロの街の夜明けに』を読んでいると、何人もの人が行間に浮かんできた。作者ルータ・セペティスは言う。「歴史は、世界全体の物語、人間の物語の入り口です」と。
今世界にどれだけの人が息づいているのだろう、隣の人、遠く離れている人、もうこの世にはいない人、これから生まれてくる人。
そんな人々に、思いを馳せられるような、そんな仕事をしていきたいと思うのだった。
(おちあい ゆりこ・写真家)