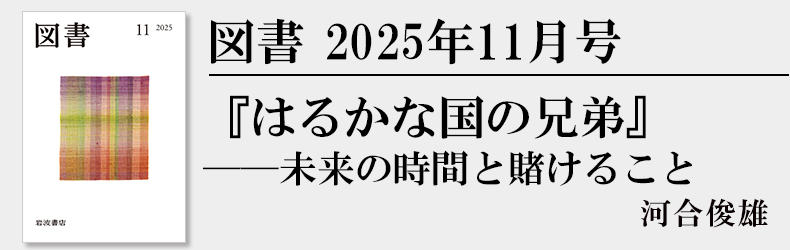河合俊雄 『はるかな国の兄弟』──未来の時間と賭けること[『図書』2025年11月号より]
『はるかな国の兄弟』
──未来の時間と賭けること
未来の時間?
ファンタジー文学において、前回取り上げた『思い出のマーニー』や『トムは真夜中の庭で』をはじめとして、過去の世界に行ったり、過去の世界の人が現れたりする名作は多いが、未来に行くことはあまりないように思われる。それに対していわゆるSF小説では、未来の世界に行くことがしばしばある。真木悠介が『時間の比較社会学』のなかで指摘しているように、前近代の世界観は、神話的な過去の大洋の上に島のように現在が載っているようなものである。従って意味を与えてくれるのは神話としての過去であって、未来は存在しない。ケニアのカムバ族出身のムビティのことばを引用して述べられているように、「[アフリカ人の伝統的な観念によれば]時間は長い〈過去〉と〈現在〉をもつ二次元的な現象であり、事実上〈未来〉をもたないのである」。ところが、このような意味を与えてくれるものとしての神話的過去が解体されていくことによって、未来が意味を担うものとして主に近代に生じてくる。それはユートピアであったり、ディストピアであったりする。
確かに昔話においても、「浦島太郎」のように竜宮城でほんのしばらく過ごしただけなのに地上では数百年が経っていて、未来の世界に来てしまったという話は存在する。しかしそれは未来が意味を与えるものとなっているのではなく、単に向こうの世界とこちらの世界の時間経過の違いを示しているだけである。また未来に行ってしまうのではないけれども、昔話や神話、さらには古代の歴史書には、未来の予言や予知夢がしばしば見られる。たとえばエディプス神話における、父を殺し、母を妻とするという神託もそうである。しかしこの場合の未来はあくまでも現在からの予言としての未来で、すぐその未来に行ってしまうのではないので、それはまた別の機会に取り上げたい。
ここではこのようなことを踏まえつつ、リンドグレーン作『はるかな国の兄弟』を取り上げてみよう。そこでは亡くなってからのナンギヤラ、そこでさらに亡くなってからのナンギリマという未来が登場するからである。なお河合隼雄は『ファンタジーを読む』で「死と向き合う」という題をつけて本書を取り上げているが、ここでは主に時間の観点から考察したい。
時間のペアとしての兄弟
『はるかな国の兄弟』は、『長くつ下のピッピ』などの多くの傑作で世界中でよく知られているスウェーデンの児童文学作家アストリッド・リンドグレーンが1973年に発表したものである。このタイトル (原題は Bröderna Lejonhjärta、レヨンイェッタ兄弟、ライオンの心の兄弟)から、この物語の中心となるのが兄弟の物語であることがわかる。物語は、ほとんど寝たきりで歩けず、もうすぐ死ぬということがわかっている弟の少年カールによる兄のヨナタンについての語りで始まる。3つ年上のヨナタンは、金髪で濃い青い目をした美しい少年で、強くしかもやさしい。弱くて「小さくかわいらしい、足がまがって、ぶかっこうな青い顔の子である」弟をクッキーと呼んでかわいがっている。この物語を通じてのヨナタンには、一点の曇りも弱さもなく、完璧である。敵の命でさえ救う。まさに神のような存在なのである。対して弟のカールは病弱で足が曲がっていて歩けず、臆病で、来世であるナンギヤラに行くと活発に動けるようにはなるけれども、その怖がりな性格は変わらない。
これは一人が神で、もう一人が人間のペアをなしている兄弟であると考えられる。神話には一人が神で、もう一人が人間である兄弟がいくつもある。たとえば、ギリシャ神話におけるヘラクレスは、アルクメーネーとの間に夫のアムピトリュオンの姿を偽ったゼウスがもうけた子どもであるが、その兄弟のイピクレスは夫婦の間の普通の子どもである。神のような兄であるからこそ、ヨナタンは人間が死んだら星の向こうにあるナンギヤラに行くことを知っている。つまり未来を知っていて、導いてくれ、励ましてくれるのである。前回までの、少女のモモと時間の根源を知る老人のマイスター・ホラ、アンナと過去から来た少女マーニーという時間のペアは、この物語では兄弟の形になり、その一人が未来を知っていることになる。
この兄弟が、ナンギヤラという未来や来世に開かれているのは、普通の時間の流れから外れているからだと考えられる。モモは親を知らず、自分の年齢すら知らず、時間の秩序を全く外れていた。だからこそ時間をつかさどるホラ老人のところに行き、時間の根源をマンダラとして体験できた。『思い出のマーニー』のアンナは、両親を幼いころに失い、引き取ってくれた祖母もすぐに亡くなってしまい、さらには養母となったプレストン夫人とも打ち解けず、親から子どもへという世代の流れを見失ってしまっていた。それゆえに双子のようでありながら自分の祖母でもあって、過去からやってきたマーニーに出会えた。
この物語の兄弟の父親は、弟のカールが2歳のときに、海にいってしまったきり、何の連絡もないという。母親はいても、父親から子どもへという時間の流れから二人の兄弟は外れているのである。これまでに取り上げてきた2つの物語と同じように、通常の時間の流れに乗っていないからこそ深い次元での時間に開かれていき、ここではそれが未来の時間という形を取るのである。リンドグレーンによるもっとも有名な作品である『長くつ下のピッピ』の主人公のピッピは9歳なのに、たった一人で暮らしていた。これも親子という時間の流れから外れていると考えられ、リンドグレーンは通常の時間や世代の流れではない時間をキャッチできる人であったのであろう。
10歳のころの男の子と戦い
もうすぐ死ぬということを偶然に耳にして、覚悟していた弟のカールだったが、住んでいた家が火事になり、3階で病床に横たわっていたカールを救おうと、兄のヨナタンは危険を顧みずに助けにいき、階段が炎に包まれて降りられないために弟を背負って窓から飛び降り、無事にかばうことに成功するが、自分はひどく傷ついて亡くなってしまう。「泣くなよ、クッキー、ナンギヤラで、また会おう!」が最後のことばであった。それの新聞報道の記事から、カールは10歳であったことがわかる。
ほどなくしてカールは亡くなったのであろうか、ナンギヤラのサクラ谷にある、門に「レヨンイェッタ兄弟」と表札がついている古い屋敷の前に立っていて、釣りをしていた兄のヨナタンと再会する。カールは普通に歩けるようになっていて、騎士服姿になって二人は馬に乗って出かけたり、パンとミルクを台所で食べたりと、質素でも充実した生活を享受する。
しかしナンギヤラでの生活は天国のような牧歌的なものではなくて、二人の住んでいるサクラ谷は平和であるが、隣の野バラ谷は、カトラという竜を角笛によってコントロールできるようになった残酷なテンギルによって力ずくで支配され、苦しめられていた。ソフィアという女性を中心にして、人びとはテンギルと戦おうとしていて、ヨナタンはそれに大きく力を貸していた。野バラ谷に一人馬に乗って向かっていったヨナタンをカールも後から追っていって、それからは冒険と戦いの連続である。
この物語は、10歳のころの男の子の世界を描いている。10歳のころという前思春期は心理学的に興味深い区切りの年齢で、自己意識が確立され、それに伴って同性の親しい友人との関係であるチャムシップが育まれる時である。『思い出のマーニー』も女の子のチャムシップの世界を示しているが、この物語は男の子の10歳の世界を描いていて、それは戦いである。たとえば今江祥智による児童文学『ぼんぼん』も10歳の男の子の世界を描いたものであるが、ちょうど第2次世界大戦が勃発したこともあり、主人公は戦争のさなかにいることになるが、それは10歳の男の子の内面に沿っている。10歳のころは激動のときであり、男の子は敵と戦うことによって自分を確立するのである。それをこの物語は反映している。またこの物語におけるチャムシップは、ヨナタンとカールという兄弟のペアなのである。さらにこの年齢のこころの時間にふさわしく、恋愛や異性との関係はほとんど重要ではなく、物語でもふれられていない。ヨナタンが13歳という思春期を目前にした年齢で亡くなっているのは、この10歳のころの時期の濃密な時間をナンギヤラで弟とともに生きるために必要であったのであろう。
現世の繰り返しとしての来世
キリスト教における天国や仏教の浄土宗や浄土真宗における極楽浄土も来世であり、理想化された未来と考えることができる。それは理想化されたものの対極としての地獄によって裏づけられている。まさに亡くなっても極楽に行けると信じることによって、未来が意味を与えてくれるのである。ところが、この『はるかな国の兄弟』における来世であるナンギヤラは、理想的な世界とはほど遠い。カールがサクラ谷に着いて、兄のヨナタンとの再会を果たしてしばらくは、馬に乗ったり、魚を釣ったりという自然のなかでの幸せそうな生活が描かれている。歩くことさえできなかったカールが来世では活発に活動できているのはすばらしいことである。しかしサクラ谷はまだ大丈夫でも隣の野バラ谷はテンギルによって支配され、人びとは重税に苦しめられ、少しでも刃向かうものは殺され、町は完全に封鎖されて兵士たちによって常に監視されている。
ヨナタンはカトラの洞窟に閉じ込められているオルヴィルという英雄を解放し、テンギルを倒そうとするが、味方のはずのサクラ谷には裏切り者がいる。しかも、野バラ谷に向かおうとしていたカールが洞窟に隠れていたときに、テンギルの部下たちとこっそり会っているのを目撃した裏切り者は意外にも、サクラ谷の人たちに会合の場を提供して親切にしていた「金のオンドリ館」の亭主のヨッシだったのである。
つまり来世であるナンギヤラは理想の世界というにはほど遠く、悪があったり、悪との戦いがあったり、さらにはその戦いのなかで裏切る者がいたりというところは、現世と変わらないし、それどころかそれをさらに凄まじく極端にしたようなものなのである。どうも未来や来世は、今の世界とあまり変わらないのではないか、というのをこの物語の未来の世界は示唆しているようである。ずっと努力してきた人、戦ってきた人が、来世ではもっとこころ穏やかに暮らすことをわれわれは望むかもしれないが、そのような人はやはり来世でも、同じように戦い続けるのかもしれない。
現世をさらに極端にしたような来世であるナンギヤラは、現実世界の深層にある神話的世界や異界とも考えられる。騎士服姿で馬を乗りまわしているときに、カールがヨナタンに、ナンギヤラで生きている時代はすごく古いのかと尋ねたのに対して、ヨナタンは、古い時代かもしれないが、それは若い時代ともいえるかもしれないと答えているのは示唆的である。つまりナンギヤラは古い時代のようで、神話的世界のようであるけれども、多くの物語で神話的世界に行った人がそこでの体験を経てまた現実に戻ることがあるのに対して、ここでは不可逆的で、元の世界に戻ることはない。ナンギヤラはあくまで未来の話なのである。この物語には、旧来の世界観に見られる、根源としての異世界があって、そこから現実に戻ってこられるということはなく、先に、未来に進んでいくしかないのである。それは現代的かもしれない。
賭けることとしての未来
テンギルとの間で最後の戦いが行われ、ヨナタンがテンギルから角笛を奪ったために竜のカトラはヨナタンの言うことを聞くようになり、野バラ谷とサクラ谷の人びとはテンギルの軍勢を倒し、多くの犠牲者を出したものの平和が訪れる。ヨナタンは、カトラを洞窟の鎖につないでほしいというオルヴィルの最後の願いを聞いて、カトラを山中の洞窟に連れて行くが、誤って角笛を滝に落としてしまう。そのためにカトラは言うことを聞かなくなり、ヨナタンとカールを襲おうとするが、ヨナタンは岩を落とすことでなんとかカトラを滝に沈める。カトラはそこにいた大蛇の怪物カルムと相打ちになって消えていく。
これで全てめでたく解決したかのようであるけれども、カトラとの戦いの最中に、ヨナタンはカトラの小さな炎を浴びてしまっていた。少しでもカトラの炎を浴びると、体が次第に動かなくなってしまい、死に至る。しかし死んだら今度は死後の世界であるナンギヤラからさらにナンギリマに行くという。それを聞いて、弟のカールも一緒に行く決意をする。そして動けなくなっている兄を背負って、崖の下に飛ぶという。「地面についたとたん、もうぼくたちには、ナンギリマからの光が見える。ナンギリマの谷々を照らす朝の光が見える。あそこは今、朝だからね」とヨナタンは言う。
ヨナタンは確信をもって語っている。しかし未来はわからない。それは何かを確かに約束するものではなく、だから不安も生じてくる。しかしナンギリマに向かって飛び、それに賭けることが大切なのである。ここに示されているのは、予感を元に、賭けるものとしての未来である。
神と人の逆転
歩くことができず、怖がりだった弟のカールは、ナンギヤラに移って歩けるようになってもいつも兄のヨナタンを頼りにしていて、これは時間のペアに相応している。何か根源からのパワーをもっている人、根源とつながっている人が片割れにいて、それを主人公は頼りにしている。モモはマイスター・ホラを頼りにし、『思い出のマーニー』でアンナはマーニーを頼りにしている。だから火事が起こったときに、兄のヨナタンは足が動かないカールを背負って3階から飛び降り、カールの命を救うけれども、自分は命を落としてしまう。まさに神が自分を犠牲にして、人間を救ってくれるのである。
しかし『モモ』の最後の方で、時間を支配して、与えてくれるはずのホラが眠りにつき、それまで受け身であったモモが一人で灰色の男たちとの戦いをやり通さねばならず、いわば立場の逆転が生じたように、この『はるかな国の兄弟』でも逆転が生じる。この物語の最後において、竜のカトラの炎を浴びたために次第に動けなくなっていって、死んでいくことになる兄のヨナタンを背負って、弟のカールは崖から飛び降りる。
これは物語の最初で、病気で動けない弟のカールを背負って、兄のヨナタンが火事になっている建物の3階から飛び降りたのと完全に対照的である。これは単に兄弟の立場が逆転していく物語としても感動的であるが、ここでの時間に関しての考察からすると、未来を知る神に任せておけば導いてくれるのではなくて、人間の方が主体的に自分を賭けて、未来を開いていくことが大切なのであろう。
時の重なり
物語の最初の方で兄のヨナタンが先に亡くなって、後からカールがナンギヤラに着いたように、そこにはタイムラグがある。もっとも元々は、病弱で間もなく亡くなることがわかっていたカールが先に行って、ナンギヤラで兄を待つことになるはずであった。しかし火事でヨナタンが自分を犠牲にしてでも弟を救おうとしたことによって、逆になってしまったのである。
ところが物語の最後では、ほとんど動けなくなった兄のヨナタンを背負って弟のカールが崖から飛び降りることで、二人は同時にナンギリマを目ざす。『思い出のマーニー』では、最後にアンナは水車小屋に取り残され、エドワードはマーニーだけを助けて去って行く。アンナはマーニーと別れ、過去とも分離し、現実の人間関係に戻っていく。『はるかな国の兄弟』では、兄弟は一体となって未来の国をめざすことになり、二人の時は重なるのである。
飛び降りる前にヨナタンが「きみ、こわいのかい?」と尋ねたのに対して、弟のカールは「ううん……ああ、ぼく、こわいよ! だけど、それでも、ぼくはやるよ、ヨナタン、ぼくは今やるよ、……今、……そのあとは、ぼく、もうけっしてこわがらない。もうけっして、こわがら……」そしてここで二人は飛んだのであろう。物語は次のカールのことばで終わっている。「ああ、ナンギリマだ! そうだ、ヨナタン、そう、ぼくには光が見える! 光が見えるよ!」
(かわい としお・臨床心理学)
関連記事
河合俊雄 『モモ』──豊かな時間とその根源
河合俊雄 『思い出のマーニー』──過去の時間との出会いと癒し
河合俊雄 こころの紡ぎ出した物語としての『モモ』