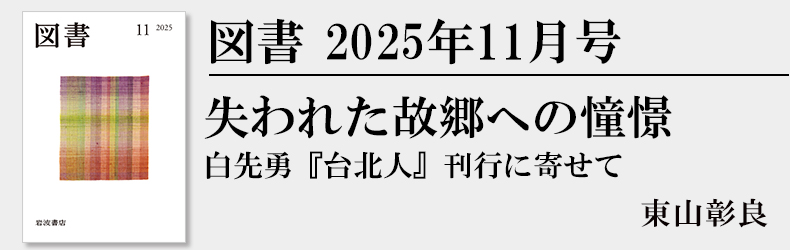東山彰良 失われた故郷への憧憬[『図書』2025年11月号より]
失われた故郷への憧憬
白先勇『台北人』刊行に寄せて
白先勇『台北人』に収められた14の短編のいずれも、まるでビスケット缶に仕舞われた古い白黒写真のようだ。
そこに写っているのは私の知らない人や風景ばかりなのに、どれひとつとして個人的な記憶を呼び覚まさないものはない。麻雀卓を囲む女たち、かつて華々しい戦果をあげた軍人の葬儀、街角の小さな食堂の日常、中国大陸から渡って来た人々が身を寄せ合って暮らす地区──白先勇が紡いでみせたのは、国共内戦に敗れて台湾へ逃れ落ちた外省人のその後の物語である。
日本に越して来る前、私は台北の廣州街にある母方の祖父母の家で暮らしていた。祖父母ともに中国湖南省の出で、彼の地は「無湘不成軍(「湘」は湖南省の略称)」、直訳すれば「湖南なくば軍もなし」と言われるほど、傑出した軍人を多く輩出している。祖父の実家は裕福な地主だったので、若旦那だった祖父は気ままに白馬を乗りまわし、歌を歌えば村の娘たちがうっとりと聞き惚れるほどの美声の持ち主だったそうだ。若くして孫文が設立した黄埔軍官学校に学び、長じてからは抗日戦争と、それにつづく国共内戦で各地を転戦した。最終的には、陸軍中将にまで上り詰めた人である。
いまでもよく憶えているのだが、台北の我が家の客間には曽祖父の巨大な遺影と、祖父が蔣介石といっしょに写っている写真が誇らしげに飾られていた。椅子に腰かけた老総統は威風堂々としつつもやさしげで(あのころは二・二八事件や、一連の白色テロのことなど知りもしなかった)、顔にあどけなさの残る祖父は兵士の鑑のように直立不動の姿勢を取っている。そのころ、私たち子供は蔣介石を神様のように思っていたので、神様といっしょに写真に写っている祖父のことが誇らしくてならなかった。
祖父の脚には銃創がいくつかあり、私はその傷にまつわる武勇伝をしつこく聞きたがった。しかし祖父の口は重く、私に聞き出せたのは、あるとき戦闘中に足の甲を撃ち抜かれたが、共産党軍の攻撃があまりにも激しかったため、撤退して何十キロも歩いたあとでやっと被弾したことに気がついたという話くらいだった。
「川を渡ったあとだった。水が入ったと思ってブーツを脱いで逆さにしたら、血がザアザア出てきた」というような話を、祖父はあまり誇らしげでもなく、どちらかといえば渋々教えてくれた。
戦争というものの実態は、けっして面白おかしく子供に語り聞かせられるようなものではない。祖父が指揮官を務めた戦闘で、苛烈を極めた混戦の末にやっと敵を制圧したとき、仲間をさんざん失って怒り心頭の部下たちが、敵の死体から心臓をえぐり出して食べた。仲間たちの死をつぶさに見てきた祖父には、彼らを止めることができなかった。そのことをずっと悔いていたと、祖父が亡くなったあとで知った。
人が亡くなってからやっと明るみに出る事実のなんと多いことだろう。本書収録の「梁父山の歌」もそうした一編だ。
ひとりの老人と、彼に付き従う中年男が葬儀から帰宅する。老人はかつて辛亥革命に身を投じた戦士で、中年男のほうは、老人と兄弟の契りを交わした男の弟子筋にあたる。そう、その日はまさにその兄弟分の告別式だったのだ。老人を家まで送りとどけて辞去しようとする中年男を、老人が引き留める。勢い、故人の思い出話に花が咲く。革命に若き血潮を燃やした破天荒な日々。時が流れ、台湾へ流れつき、やがて新しい時代の価値観に淘汰されてゆく老人の悲哀がぎゅっと詰まった小品だ。辛亥革命によって清朝が打倒され、中華民国が誕生したことは誰しも知るところだ。その革命を成就させたという目も眩むほどのまばゆい栄光のせいで、よりいっそう現在の老いの哀しみが際立つ。いよいよ暇乞いをした中年男に対して、老人は最後に故人の遺志を告げる。
「もうひとつおまえの師が臨終の時に残した言葉がある。将来大陸へ反攻した時、どんなことをしてでも棺を故郷へ移送してもらいたいのだ。遺族に申し渡してくれ。孟養がいつも着ていた軍人礼服を残し、勲章も必ず保存しておくようにとな。将来棺を移送する時、正装や勲章が大切なのだ」
孟養とは故人の名前である。この短いセリフのなかに、じつに多くの真情がこめられている。軍人としての矜持、大陸に対する郷愁、いつの日か必ず勝利するのだという信念。そのどれもが、中国本土から台湾へ渡って来た外省人第一世代が共有する感情だ。
悲しいのは、後代の私たちは老人たちの願いが叶うことはないと知っていることだ。私の抽斗のなかには、祖父にもらった勲章がいまも眠っている。厚手のビニールケースに入っていて、ケースの表には「寶星奨章」と刻印されている。「陸軍總指令部頒發」の文字もある。あるとき、祖父が戯れにその勲章を見せてくれた。先ほども述べたが、祖父は陸軍中将にまでなった人なので、きらきらした色鮮やかな勲章をたくさん持っていた。私はそのきらびやかな宝物に目を奪われ、祖父に勲章をねだった。祖父は困ったような、孫にまとわりつかれて嬉しいような顔をして、水色の綬に星型の章身がついたものをひとつくれた。
それで私は増長した。勲章はまだ売るほどあるし、祖父は私のことを目に入れても痛くないほど可愛がっている。ここでもうひと粘りしないなんて、どう考えてもあり得ない。だから、わたしはそうした。けっきょく、根負けした祖父から3つも勲章をせしめることができた。誰にも言っちゃダメだぞと釘を刺されたが、もちろん私はすぐにいとこたちに見せびらかした。恥知らずないとこたちは、まるで血に餓えたピラニアみたいに祖父の部屋へ駆け込んでいった。
いまでも、あのとき祖父はどんな気持ちだったのだろうかと思う。人生においてもっとも輝かしかった時代を忘れることができないのは、誰しも同じだろう。たとえそれが戦争の忌まわしい記憶にまみれていたとしても、あれらの勲章はたしかに祖父の人生を雄弁に物語る物的証拠だった。それを私は子供の無邪気さで、ただのおもちゃに変えてしまったのだ。
祖父にくらべて、祖母の人生が穏やかだったとは思わない。敗走する国民党軍に付き従って、祖母も長い旅の果てにやっと台湾にたどり着いたのだ。そのまえは香港で数年ほど待機し、ようやく台湾の土を踏んだときは靴も履いていなかったと言っていた。『台北人』にも女たちが麻雀に興じる場面が多く出てくるが、祖母もそうした外省人の女たちのご多分に漏れず、四六時中麻雀ばかり打っていた。愛情深いけれど子供を殴ることに躊躇などない人で、遊びに夢中になり過ぎた私がうっかりドブにハマって体を汚したりすると、庭の蛇口で水をかけてから木の棒でぶん殴った。祖母はカツラをいくつか持っていて、麻雀に行くときは気分次第で髪型を変えた。すらりとしたチャイナドレスを着るときは、いつも私が背中のジッパーを留めてやった。
廣州街には国民党の軍人や軍属の家がたくさんあったので、いつも誰かの家で麻雀が行われていた。私たち子供はそんな家に勝手にあがりこんではジュースを飲んだり、見てもわからない麻雀を見物したり、ぶらぶらしたり、ガラスのコップを割ったりしていた。台湾の戒厳令は1949年から1987年まで38年間もつづいたが、もちろん祖母たちが麻雀をしていたのも戒厳令下だった。憲兵に見つかると逮捕されることになっていたけど、私は大人たちがしょっぴかれるのを一度も見たことがない。ただ風の噂で、近所の張ばあさんの家には大人が四人も入れる大きな箪笥があって、万一麻雀をやっているところを憲兵に踏み込まれたら、その箪笥に隠れるのだという話は聞いたことがあった。
祖父に勲章をもらったように、私は祖母からも大切なものをもらったことがある。あるとき、祖母が戯れに大陸から持ってきたコインを見せてくれた。大洋(ダーヤン)と呼ばれる、袁世凱の横顔が刻まれた一元硬貨だ。俗に袁大頭(ユェンダアトウ)と呼ばれていたその硬貨を祖母は赤い絹のハンカチにくるみ、戦火を逃れるときの路銀として大事に台湾まで持ってきた。ぴかぴかの硬貨に私はすっかり心を奪われた。こちらがなにも言わないのに祖母が1枚くれたので、私はまたしても増長した。袁大頭はまだ売るほどあるし、祖母だって祖父に負けず劣らず私のことを可愛がってくれている。ここでもうひと粘りしないなんて、大馬鹿者のやることだ。だから、そうした。あいにく祖母は祖父ほど人情深くないので、蠅のように追っ払われてしまった。その硬貨を私はことのほか大事にし、日本に来てからもしょっちゅう磨いていたので、でっぷり肥えて厳めしかった袁大頭の角が取れてだんだん丸みをおび、しまいには袁世凱がアルフレッド・ヒッチコックのようになってしまった。
私が言いたいのは、とどのつまりこういうことだ。白先勇の『台北人』は、そう、そんな私たち外省人の集合的記憶そのものなのだ。まるきり初見のエピソードばかりなのに、どことなく懐かしい。私自身は台湾で生まれたいわば外省人第二世代なので、祖父世代や父世代のような中国大陸に対するノスタルジックな感傷はあまり持ち合わせない。それでも大陸時代の栄華と折り合いをつけながら、新天地の台湾でたくましく生きる登場人物たちの姿に胸が震える。「故郷というのは、二度と帰ることの出来ないものであり、いつもさびしいものなのである」と書いたのは寺山修二だ。彼はさらにこう喝破する。「故郷は、土地でも人でもない──もっとあいまいで形のないものである。土地や家に帰ることは出来ても故郷に帰ることが出来ない」(『悲しき口笛』、ハルキ文庫)。ある意味でそれは真実かもしれないけれど、故郷に対する外省人たちの憧憬は、台湾へ敗退したという精神的・空間的断絶によって幾倍にも強化されている。
戒厳令下の38年間はけっして短い時間ではなかった。若者が年老いるには十分過ぎるくらい長い。ましてや戒厳令の真っ只中にあったあのころ、そんな状態がいつまでつづくのか誰にもわからなかった。『台北人』が内包するやるせなさのもうひとつの理由は、それが故国喪失の物語であると同時に、老いについての物語でもあるからだ。なにしろ、長い長い時間が失われてしまった。白先勇はその失われてしまった時間を回顧することで、集団としての外省人の人生における、極めて個人的なエピローグを描き出したのだ。
(ひがしやま あきら・作家)