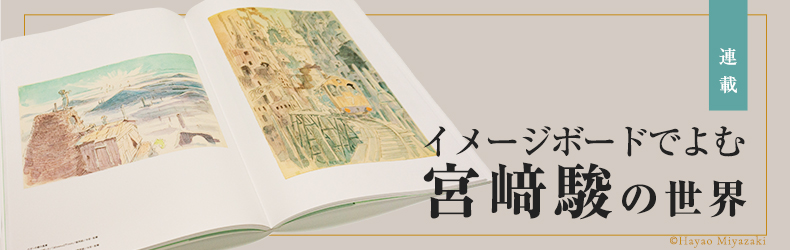齋藤亜矢 イメージはどこから生まれるのか[『図書』2025年11月号より]
イメージはどこから生まれるのか
郷愁を誘う美しい風景に、キャラクターたちの生き生きとした表情。子どものころに何度も観たナウシカやラピュタやトトロの世界がそこにあって、さまざまなシーンや台詞、音楽もよみがえる。紙の地色のままスキャンされた絵が並ぶ大判の本のページをめくっていると、古いアルバムを開いているような気分にさえなった。
でも冷静に考えると、とんでもないものを目にしていることに気づく。これらの絵が描かれたのは、物語が生まれる前なのだ。
イメージボードは、宮﨑駿さんが作品をつくるときの最初の作業で、ストーリーやキャラクターを考えるよりも先にまず、絵で構想を練るのだという。
作品のシリアスさからデフォルメの度合い、舞台となる世界の時代や気候、太陽の数、登場するキャラクター、そしてテーマ。一つひとつ自分に問いかけながら絵を描きすすめるうちに、その世界が明らかになっていく。それは、もっとも胸はずむ時期だという。
「あきれるほど自分のなかから絵が生まれてくる」という疾走感がイメージボードから伝わり、ページをめくるたびに、わくわくする。
幹を太くし、枝をひろげ、あの梢の先(それが発想の出発だったりする)、そしてその先の葉っぱへまで、枝はどんどん伸びていく。
(宮崎駿『出発点 1976~1996』)
そんな表現もあって、トトロの「ドンドコ踊り」のイメージが重なった。サツキとメイがどんぐりを植えた庭に、ある晩トトロたちがやってきて、ふしぎな踊りをするシーンだ。トトロが身をちぢめてから、ばっと伸びあがって傘をかかげると、土のなかからぽこっと芽が出る。ちびトトロやサツキ、メイも一緒になって踊りをくりかえすと、次々と芽が出て、ぐんぐん幹が伸び、枝がひろがり、森になっていく。イメージボード全集にもこのシーンのストーリーボードが掲載されていたが、小学生のころにまねして遊んだことも思い出した。
絵の素材となるのは「自分が夢想した絵の切れっぱし、組み立て中に放り出した物語の片方の幹、ある少女への憧れの記憶、趣味と思って深入りしていた分野の知識など」で、ばらばらの素材が一つの方向を見つけて流れはじめるのだという。
イメージボードは、スタッフと共有しつつ、そのなかから映画の世界の基調となる絵を見つけて整理し、ストーリーボード、あるいは直接、絵コンテのかたちでストーリーを展開していく。それはイメージボードのなかから表現したい本体を削りだし、しっかりとした根幹を打ちたてるプロセスにあたる。
つまりイメージボードとして描かれる絵がすべてのはじまりであり、描くという行為から、あの魅力的な世界が生まれ、キャラクターたちが息づき、物語が展開していったのだ。
実際、イメージボード全集のなかには、描きながらキャラクターを検討していくプロセスも垣間見える。
たとえばサツキとメイのお父さんは、映画ではやさしそうな細面の物書きだったが、四角い顔の考古学者という別の案もあったこと。サツキとメイは姉妹として真逆の性格で描き分けられたが、はじめの設定ではその中間ぐらいの年齢のメイひとりが主人公だったこと。
キャラクターはさまざまな表情や髪型、服装や姿勢で、くりかえし描かれている。その描写から人物のこころが感じられ、来歴と人格をもったひとりの人として見えてくるところがすごい。メイが集中してなにかをじっと見つめる顔や、にっこりほほえむ顔も単独で描かれているが、映画で、トトロに出会ったときのあの表情だ。
ラピュタに出てくる空中海賊団の頭ドーラは、18歳、25歳、30歳、50歳(いま)、さらに年老いた将来、と年齢による顔の変化まで描かれている。映画でシータに対する「あたしの若いころにそっくり」という台詞があって、息子の海賊たちとともに「えー⁉」とのけぞったが、あながちウソではなかったのだ。
宮﨑さんは、アニメは虚構の世界でありながら、リアリズムが大事であり、観る人にその世界がほんとうだと思ってもらえるウソでなければならないと語っている。
建物の壁や柱や屋根や窓がどんな構造でどんな素材なのか、空飛ぶ乗り物はどんな動力でどのように飛ぶのか、詳細まで設定されているため、空想上の奇抜な設計でありながらハリボテ感がない。
実際、映画では直接出てこないが、その世界の地図や、建物の間取り、乗り物の設計図なども描かれていて、一つひとつ根拠をもって構築されていることがわかる。
それらがただ説明的に描かれるだけでなく、カメラアングルを工夫した映画の1カットのような動的で美しい構図で描かれた絵も少なくない。
おもに鉛筆やペンと水彩で描かれていて、美しい色合いの風景からは、時間帯もうかがい知れるし、その場所の気温や湿度、場面の緊張感も感じられる。
さらっと描かれた抜けのある線ながら、写真をトレースして描きこまれた絵よりもリアリティを感じる。
引きの視点から、風景のなかに人物や乗り物がぽつんと描かれたシーンや、風景だけ、空だけが描かれたものもある。
ただキャラクターを動かしてストーリーをつくるのではなく、キャラクターの生きる世界が、奥行きのある空間として描きだされていくのがわかる。そして複数のキャラクターが描かれた絵には、たしかに物語が動きはじめた気配があった。
アルバムのように感じたのは、イメージボードのなかの魅力的な絵が物語に編みこまれ、映画の印象的なシーンとして記憶に残っているせいもあるのだろう。
通常、ものをリアルに描こうとするときは実物か写真を見て描くのが一般的だ。でも、宮﨑さんは、描くときに資料を参照しないと知って驚いた。
スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫さんによると、宮﨑さんは映画の構想のためにロケハンに行っても写真を撮らず、メモもせず、ひたすら目で記憶するのだという。建物を描く場合も、窓は何世紀のどこの何様式と記憶して、帰ってから絵に再現する。覚えた30個のうち20個を思い出し、忘れた10個は想像でおぎなう。そこが創造になるというが、いずれにしても驚異的な記憶力だ。
でも、写真を参照せずに一度咀嚼したイメージを描くからこそ、実在するものも、空想上のものも、同じようにリアルに描けるのかもしれない。
ふつうなら資料を参照せずにイメージで描くと、ありきたりで記号的な表現になりがちだ。でも宮﨑さんの場合は、蓄えられたイメージの源泉が人並みはずれて豊かなのだろう。
そこにはもちろんたぐいまれな才能もあるだろうが、アニメーターとして、数え切れないほどの絵を描いてきた経験によるところも大きいのではないかと思った。
認知科学の研究をしていると、人間の目が驚くほど節穴で、ちゃんと見ているつもりでも、じつはほとんど見えていないことを思い知らされる。
たとえば地面を歩く小さな黒い虫を見れば、すぐにアリだとわかる。でも、アリの絵を描いてくださいと言われて、何も見ずに描ける人は案外少ない。きちんと描けないのは、絵心がないからではなく、アリのことをよく知らないからだ。体節がいくつに分かれていて、どこから何本脚が生え、節はいくつか。触角や眼はどんなかたちか。ふだんきちんと見ていないから知らないし、知らなければ絵に描くこともできない。
そのため逆に、一度きちんと観察して描くと、その構造が知識として刻みこまれる。そうすると、はじめて見たほかの昆虫も、アリの構造との差異で覚えやすくなる。だからたくさん絵を描いてきた人ほど、モノの詳細をとらえる、いわば解像度の高い目が育っているように思う。
アニメーションでは、1秒間に何枚ものカットを描き、ひとつの映画で何万枚という単位になるそうだ。もちろんそれはたくさんのスタッフの手によるものだが、宮﨑さんが、とびぬけて膨大な数の絵を描いてきた人だということには違いがない。
ドキュメンタリー映像で絵コンテや作画のシーンを見たとき、宮﨑さんが鉛筆を走らせるスピードに驚いた。作画では描いた前後のカットを重ね、めくることで動きを確かめる。そこで少しでも納得がいかないと消しゴムで消して何度も描きなおす。
線がわずかに変わるだけで、表情やからだの動き、服のゆれにもリアリティがまして、しっかりと重力や風が感じられたり、年齢や性格まで変化したりする。まさにキャラクターに命が宿る感じで、アニメーションの語源がアニマ(魂)からきていることにも納得した。
絵画や漫画の場合は、ひとつの動作を表現するために、特徴的な姿勢をわかりやすい角度から1カット描けばよい。でもアニメーションでは、その途中の状態もすべて描きださなくてはならない。だからアニメーターの目は、空間的にも時間的にも世界をとらえるちからが磨かれているのではないかと思った。
その過程で、アニメーターは役者になるのだという。たとえば「泣く」シーンでも、時間軸で変化する気持ちが顔やからだに表れる様子をとことん考えぬく。
描くことで「それぞれの人物のそのときの感情、怒りや喜びや、やさしさが自分のものになっていく」。つまり描く過程で役者のように自分の感情をよびおこし、紙のうえで演じているのだ。
宮﨑さんは、かつてドキュメンタリーでこうも語っていた。
絵を描いて動かしていくっていうのは、自分がからだを使って経験したことが出てくるんです。バーチャルなものをいくら見ても勉強にならない。
目や耳だけでなく、感触や匂い、そのときの思いなどを含めた具体的な体験が大事なのだという。そこに、観る人にもからだで感じられるようなリアリティの秘密があるのだろう。
アニメーターとして「描く」ことをひたすら追究してきたことで身についた観察力と視覚記憶、そして膨大なイメージの源。その源泉から、視覚とそれにともなうからだの感覚やそのときの感情など、いわば身体化されたイメージをよびおこして描く。
だから一枚の絵でもさらっと印象的なシーンを描くことができるのであり、そこから立ち上がる世界にみずから没入して物語を生みだすことができるのではないかと思った。
(さいとう あや・芸術認知科学)
*このリレー連載は11月、3月、7月の年3回掲載します。
[『図書』2025年11月号より]