2 アヒルと木馬――J.D.サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
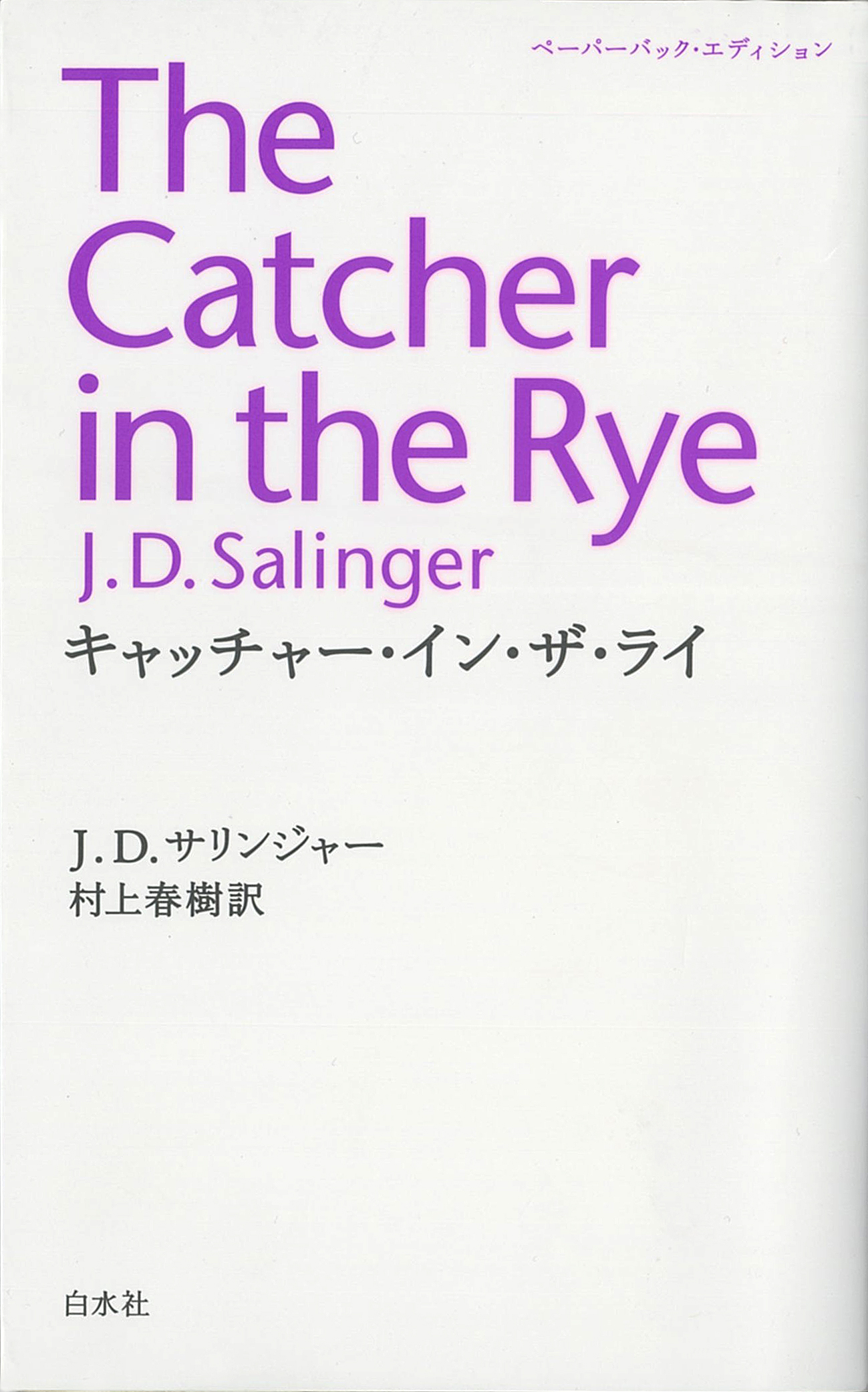
(村上春樹訳、白水社、ペーパーバック・エディション、2006年)
学校に向いてない主人公
学校は好きですか。授業は苦手だけど、部活は頑張ってる。あるいは、友達と喋れるからけっこう楽しい、とあなたは言うかもしれません。いや、自分は勉強が好きだから、わりと気持ちよく毎日を過ごしているよ、という人もいるかな。でも、J.D.サリンジャーが書いた、ひょっとしたら世界でいちばん有名な青春小説『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の主人公であるホールデンは違います。なにしろ、決定的に学校に向いてないのです。
彼は全寮制のペンシーという高校に通っているのですが、フェンシング部のマネージャーとして決定的なミスを犯します。ニューヨークの地下鉄の中で、複雑な路線図を見て悩んでいるうちに、うっかりフェンシングの用具一式を置き忘れてしまう。しかもチーム全員分です。もちろんチームの雰囲気は最悪で、そのまま試合もできずに、彼らは学校に戻ります。
友人関係も最悪です。ルームメイトのストラドレイターと、ふとしたきっかけで殴り合いの喧嘩になり、顔も服も血まみれになります。あるいは、その前のルームメイトとは、ホールデンが持っている高級品のトランクのせいで、なんとなく険悪になってしまいました。もちろん、夕暮れにボールが見えなくなるまで友人とキャッチボールをするシーンなど、高校生らしい場面はあります。でもたいていの場合、ホールデンは言うべきことを言えなかったり、あるいは誇張したり、さらには嘘をついたりと、周囲とのコミュニケーションに失敗し続けます。
それでも成績が良ければどうにかなるのではないか、とあなたは思うかもしれません。ところが、残念ながらホールデンの成績は最悪なのです。なんと4科目で落第点を取り、ここで頑張らなければ大変なことになる、と教師から何度も警告を受けてさえ、勉強に身を入れることができません。そして結局はペンシーを退学になるのです。実は、退学になるのはこれが初めてではありません。おそらく前の学校も、同じ理由で退学になったのでしょう。
それでは、ホールデンは頭が悪いのかといえば、そうではありません。英語、つまりアメリカの国語ではAをとっています。とにかく作文が得意なようです。このことは、ストラドレイターから何かを記述する作文を、自分の代わりに書いてくれ、と頼まれるシーンからも分かります。ならば、つべこべ言わずに頑張ればいいではないか。でも、ホールデンは今、興味があること以外はまったくできないのです。それは冒頭部分で、歴史のスペンサー先生に怒られる場面からもよくわかります。ホールデンが書いた古代エジプトのミイラについての回答など、典型的なダメ学生のものという感じで、ちょっと笑えます。
チームワークが不得意で気が利かない。しかも、言うべきでない時に、言うべきでないことを言ってしまう。感情が不安定で、時に手が出る。さらには、誰に何と言われようと、やりたい時にやりたいことしかできない。なんだかこう書いていると、あまりに不器用すぎて涙が出そうになります。ひょっとして、これを読んでいるあなたにも、こうした部分はあるのではないでしょうか。それでも、本当の自分のままでは生きていけないから、なんとか周囲に合わせている。けれどもホールデンのように、そうした努力が全然できず、いつも不適切にしか振る舞えない人もいるんですよね。
ニューヨーク地獄巡り
退学が決定した。スペンサー先生には怒られた。ルームメイトのストラドレイターとは喧嘩した。もう、この学校からは出て行こう。土曜日の夜、ホールデンは急に決心します。けれども一つ問題がある。クリスマス休暇は来週の水曜日からなのです。このまますんなり列車で家に戻ると、何かあったのでは、と親に怪しまれる。さらに、火曜日か水曜日には、自分が退学になったという知らせが家に届くでしょう。その手紙を両親が読む瞬間には立ち会いたくない。ならば、まずはニューヨークまで戻って、そこでホテルに泊まるなりしてほとぼりが冷めるのを待ち、予定どおり水曜日に家に帰ろう。
ここは日本の高校生には不思議なところですよね。すんなりと家に戻りたくない、という気持ちはわかる。けれども、そもそも高校生がなんで、ホテルに何泊もするほどのお金を持っているのか。おばあちゃんから多めのお小遣いをもらったばかり、という説明はされていますが、実はそれだけではありません。高級なトランクを持っていることからも分かるように、ホールデンはお金持ちの家の息子なのです。父親は顧問弁護士で、家はニューヨークのセントラルパークにほど近い、高級住宅街の広いマンションです。
とにかくここから、彼の数日間にわたるニューヨークの地獄巡りが始まります。タクシーに乗ってバーに行き、未成年だとバレて酒を出すのを断られ、夜中に女友達に電話して、非常識だと怒られ、安ホテルではポン引きの男に暴力を振るわれます。そうした大人ぶったシーンばかりではありません。
子どものころよく遊んだセントラルパークに行き、冬のあいだ、池のアヒルたちはどうしているのかを確認します。ついにお金が尽きてくると、自宅に忍び込み、妹のフィービーと再会し、彼女がクリスマスプレゼントを買うために貯めていたお金を借ります。そして、最後に近いシーンで雨に打たれながら、回転木馬に乗っているフィービーを眺めていて、あまりの幸福感に泣きそうになるのです。
最初と最後には、カリフォルニア州のロサンゼルスからほど近い何らかの施設の描写が出てきます。どうやらハリウッドに住んでいる兄のDBが、いろいろとホールデンの世話を焼いているようです。結核っぽくなったとか、ここには精神分析医もいる、という言葉もあるので、ここが療養施設であることはわかります。けれども、ホールデンが具体的にどんな治療を受けているのか、そして回復の可能性があるのかまではよくわかりません。それでも、9月からは学校に戻れる、という話も出てくるので、まあ何とかなりそうだ、というところでお話は終わります。
作者、サリンジャーについて
さて、このお話を書いたサリンジャーとはどんな人だったのでしょうか。彼は1919年にニューヨークで生まれました。父親はロシア系ユダヤ人で、母親はドイツ系のキリスト教徒です。1932年にサリンジャーはマクバーニーという私立の名門校に入学しましたが成績が振わず、わずか一年で退学して、ペンシルヴェニアにあるヴァレー・フォージ軍学校に入学します。ここはペンシーのモデルだと言われています。卒業後はニューヨーク大学に進学しましたが、これもすぐに辞め、父親の仕事を継ぐためにオーストリアのウィーンに滞在して、食肉解体業にたずさわりながらドイツ語を学びました。
この仕事がどうにも肌に合わずに、アメリカ帰国後はアーサイナス大学に入学したのですが、またも退学してしまいます。ですが1939年、コロンビア大学で開かれていた創作講座に通いだしたのが転機となりました。ここで出会ったのが伝説的な編集者のウィット・バーネットです。『ストーリー』誌を夫婦で編集していた彼は、カポーティやブコウスキーなどの初期作品を掲載したことで知られています。バーネットはいち早くサリンジャーの才能を見抜いて、ときに褒め、ときに鋭く批判しながら、彼の書き手としての力を伸ばしていきました。サリンジャーの処女短篇である「若者たち」が掲載されたのも『ストーリー』誌です。
1939年に第二次世界大戦が勃発すると、サリンジャーは1942年に入隊し、諜報部員としてイギリスで訓練を受けました。1944年にはノルマンディー上陸作戦に参加し、バルジの戦いなどの激戦をくぐり抜けます。そうしたあいだも、彼は長篇『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の草稿を持ち歩いて書き続けていました。
戦後、サリンジャーの短篇が様々な雑誌に掲載され始めます。短篇「バナナフィッシュ」が好評だったおかげで、原稿を『ニューヨーカー』誌に最初に見せるという契約を結んだのもこのころです。10年かけて書き上げた長篇『キャッチャー・イン・ザ・ライ』が1950年に完成し、翌年にリトル・ブラウン社から発売されると、全米で強烈な反応が巻き起こりました。現在までに世界で6500万部以上を売り上げたことからも、この本の人気がわかります。
53年にサリンジャーは『ナイン・ストーリーズ』を発売し、同時に執筆に集中できる環境を求めてニューハンプシャー州のコーニッシュという村に土地を買い転居します。最初は地元の高校生などとも付き合うものの、学校新聞の取材で受けたインタビューが無断で地元紙に載ったことに激怒して、彼らとの関係を絶ちます。1961年、『フラニーとズーイ』がベストセラーになるものの、ケネディ大統領の晩餐会への参加さえ彼は断ってしまいます。さらには、1965年、『ニューヨーカー』誌に発表した「ハプワース16、1924」を最後に、新作の発表自体を止めました。そのままサリンジャーはいっさい表舞台に出ないまま、2010年に亡くなりました。
池のアヒルの謎
さて、作品に戻りましょう。『キャッチャー・イン・ザ・ライ』には二つの大きな謎があります。一つ目は、けっこう能力が高いにもかかわらず、なぜホールデンはそれを学校で発揮しないのか、ということです。そしてもう一つは、彼が冒頭から、ニューヨークのセントラルパークにある池のアヒルが、寒い冬のあいだどうしているのかをやたらと気にするのはなぜか、です。彼は何度もタクシー運転手にそのことを訊き、ついには自分で見に行きます。実は、この本をよく読んでみると、この二つががっちりと繋がっていることがわかってきます。
ホールデンは作文が得意だということは、もう話しましたね。学校のシーンで彼が自分から進んで何かをするのは、ストラドレイターから頼まれて、何かを描写する作文を書く、というこのくだりだけです。そのときホールデンがどんな作文を書いたかが、この作品を理解する上での大きな鍵となります。実は彼は、弟のアリーが野球のグローブにびっしりと詩を書きこんでいた、という文章を書くのです。野球の試合中、暇なときに詩が読めるなんて、けっこうしゃれた話ですよね。でもホールデンはストラドレイターに、こんなものを頼んだんじゃない、と言われて激怒します。
なぜホールデンがここまで怒るのかといえば、このちょっとしたエピソードが、彼にとってはものすごく大事だったからです。実は三年前に、二歳下の弟のアリーは白血病で亡くなってしまいました。それがあまりにも悲しすぎて、ホールデンが家のガレージの窓を全部素手で叩き割り、ついには拳をだめにしてしまう、というシーンが出てきます。そして今や16歳で、高校生になっているホールデンですが、いまだにアリーがいなくなってしまったということが飲み込めないでいるのです。ふとした時に思い出すのはアリーのことばかりで、だからホールデンは学校の授業になど、とても集中できません。
それでは、セントラルパークのアヒルについてはどうでしょう。もともとここは、ホールデンにとって家の近所の公園でした。だから、弟のアリーや妹のフィービーと一緒に、よく遊びに来ていたことでしょう。その点では、すごく思い出のある場所です。僕も実際に行ったことがあるのですが、ここにはかなり大きな池があって、冬には凍ってしまいます。さてそのとき、アヒルたちはどうしているのでしょうか。逃げ遅れて冬中、池から逃げられなくなったら一大事です。
普通そんなわけない、と思いますよね。アヒルには翼があるからどこかへ飛んでいけるだろうし、そうでなくても短い脚で、どこかへ歩いて行くこともできるわけです。ホールデンもそのことはわかっているでしょう。しかしそれでもホールデンは、冬にアヒルはどうしているのかをいろんな人に何度も訊きます。なぜなら、おそらく彼の脳内には、水中で凍りつき、ピクリとも身動きできなくなったアヒルのイメージが浮かんでいるからです。だからこそ、それを誰かに打ち消してほしい。
地面より低い場所で、身動きが取れなくなったまま水に濡れている、というのはアリーが入れられた墓地の比喩になっています。日本と違ってアメリカは土葬が中心です。だからアリーの場合も棺に入れられて、地面に掘られた穴の底に降ろされるわけです。そして土がかぶせられ、その上には重い墓石が置かれる。ホールデンも二度ほどアリーの墓を訪ねた、という場面があります。すると毎回、雨が降り出し、墓参りに来ていた大人たちは慌てて自分たちの車に走った。そして、たったひとり土の中でアリーは雨に濡れ続けているわけです。
死の世界への恐れ
ホールデンが心配しているのはアヒルだけではありません。自分自身もまた、死の世界に引きずり込まれて身動きがとれなくなってしまうのではないか、と考えています。ニューヨークのフィフス・アベニューを歩きながら、道を渡るたびに、自分がこのまま沈んでいって姿を消してしまうのではないか、という妄想に彼が襲われるシーンがあります。あまりの恐怖に全身びっしょりと汗をかいたホールデンは、心の中で必死にアリーにお願いします。「アリー、僕を消したりしないでくれよな。アリー、僕を消したりしないでくれ。アリー、僕を消したりしないでくれ。頼むぜ、アリー」(『キャッチャー・イン・ザ・ライ』[ペーパーバック・エディション]335頁、村上春樹訳、白水社、2006)。そして、道を無事渡り切るたびに、アリーに感謝をします。
なぜホールデンはこんなにも死を恐れているのでしょうか。実は、窓から飛び降り自殺をしたクラスメイトを見てしまったからでもあります。ほとんどしゃべったことのないジェームズ・キャッスルという生徒に、たまたまホールデンが自分のセーターを貸した日のことです。キャッスルはそのセーターを着たまま、いじめっ子に追い詰められて窓から飛び降り、そのまま亡くなってしまいました。
自分の服を着た少年が自分の代わりに死ぬ。ホールデンにとっては鮮烈すぎる光景です。そしてここにも、下降と死という連想が読み取れます。さて、勇敢にもアントリーニ先生は、血が服につくのも気にせず、キャッスルを抱き上げます。このときは間に合わなかったけれども、死の危機に瀕した子どもを抱きとめる大人という本書のタイトルのイメージは、こうしたシーンにも繋がっていることがわかります。
ここまできて、本作の題名の謎も徐々に明らかになってきました。妹のフィービーに、どうせこの世でなりたいものなんて一つもないでしょう、と言われて、ホールデンは、ライ麦畑のキャッチャーになりたい、と答えます。これはいったい何でしょう。崖のすぐ手前の畑で子どもたちが夢中で遊んでいる。そして危うく落ちそうになると、このキャッチャーが片っ端から捕まえて助ける。そうした存在になりたいんだ、とホールデンは言うのです。子どもたちを救うという点では、アントリーニ先生のような人になりたい、とホールデンが言っていることがわかりますね。ただし死の危機に瀕しているという面では、ホールデンは捕まえられる子どもの側でもあります。ちなみにこのシーンにも、崖の上から下、という移動のイメージが出てきますね。
それでは結局ホールデンは、ライ麦畑のキャッチャーになれたのでしょうか。実は、そんな存在など必要ない、ということに気付けた、というのが答えになります。これはどういうことでしょうか。ヒントは、本書のほぼ最後にある、回転木馬のシーンです。ホールデンとフィービーは久しぶりにセントラルパークにやってきます。そして小学生の彼女は、一人で木馬に乗るのです。
回転木馬には金属の輪っかが付いていて、それを摑むことができると、もう一回ただで乗れます。けれども、そうするためにはだいぶ無理な姿勢を取らなければならない。あるいは、ひょっとしたらフィービーはそのまま木馬から落ちてしまうかもしれない。落下というのは、ホールデンが最も恐れているイメージでしたね。
けれどもホールデンはこう思います。「もし子どもたちが金色の輪っかをつかみたいと思うのなら、好きにさせておかなくちゃいけないんだ。余計なことは言わずにね。落ちたら落ちたときのことじゃないか。あれこれそばから口を出しちゃいけない。」(357-358頁)。そして、ぐるぐる回り続けるフィービーを見ながら、とてつもない幸福感に包まれます。
さらには、急に土砂降りの雨が降り出しますが、それでも濡れたまま回り続ける彼女を眺めているのです。雨に濡れたままでいる、というのは、アリーの墓場を想起させる部分です。けれども、フィービーは雨の中、木馬から落ちることもない。だから落下もしない。ただ楽しげに回転運動をしながら、この世を駆け巡り、喜んでいるのです。
しかも、たとえ木馬から落ちたところでフィービーが死ぬことはないでしょう。言い換えれば、すべての子どもの中には、死を弾き飛ばし、世界を楽しみながら成長していく生命力があるのです。ホールデンの中にも存在する、そうした力を信じること。兄であるホールデンは年下の妹に、この真実を教えられます。このあとホールデンは療養施設に入ります。ですが、フィービーに知恵を与えられた彼は、やがて自分なりに生きていく力を取り戻すことでしょう。そして、こうした力を示してくれる本書だからこそ、今も世界中で読まれ続けているのです。
(とこう こうじ・アメリカ文学、翻訳家)





