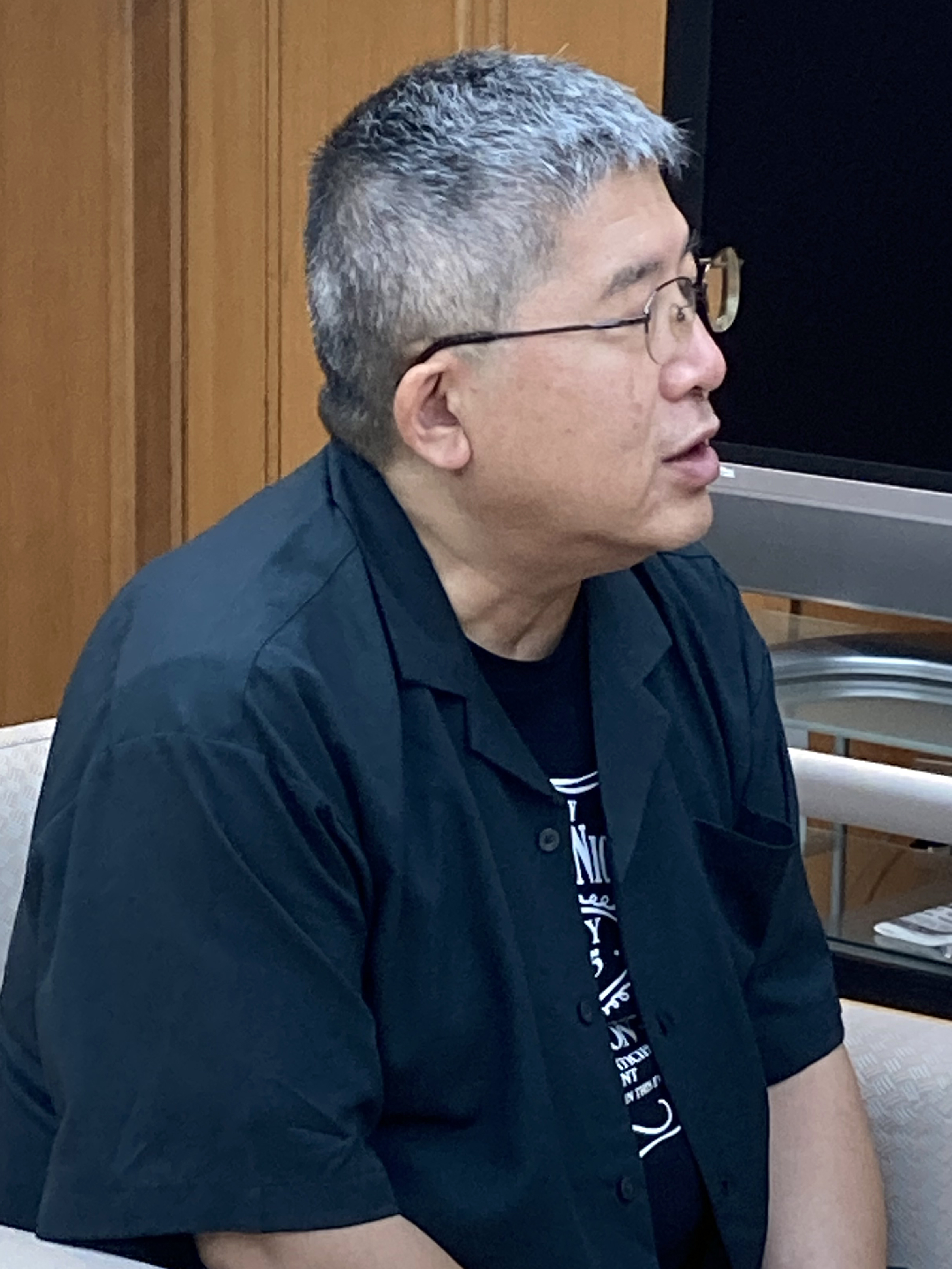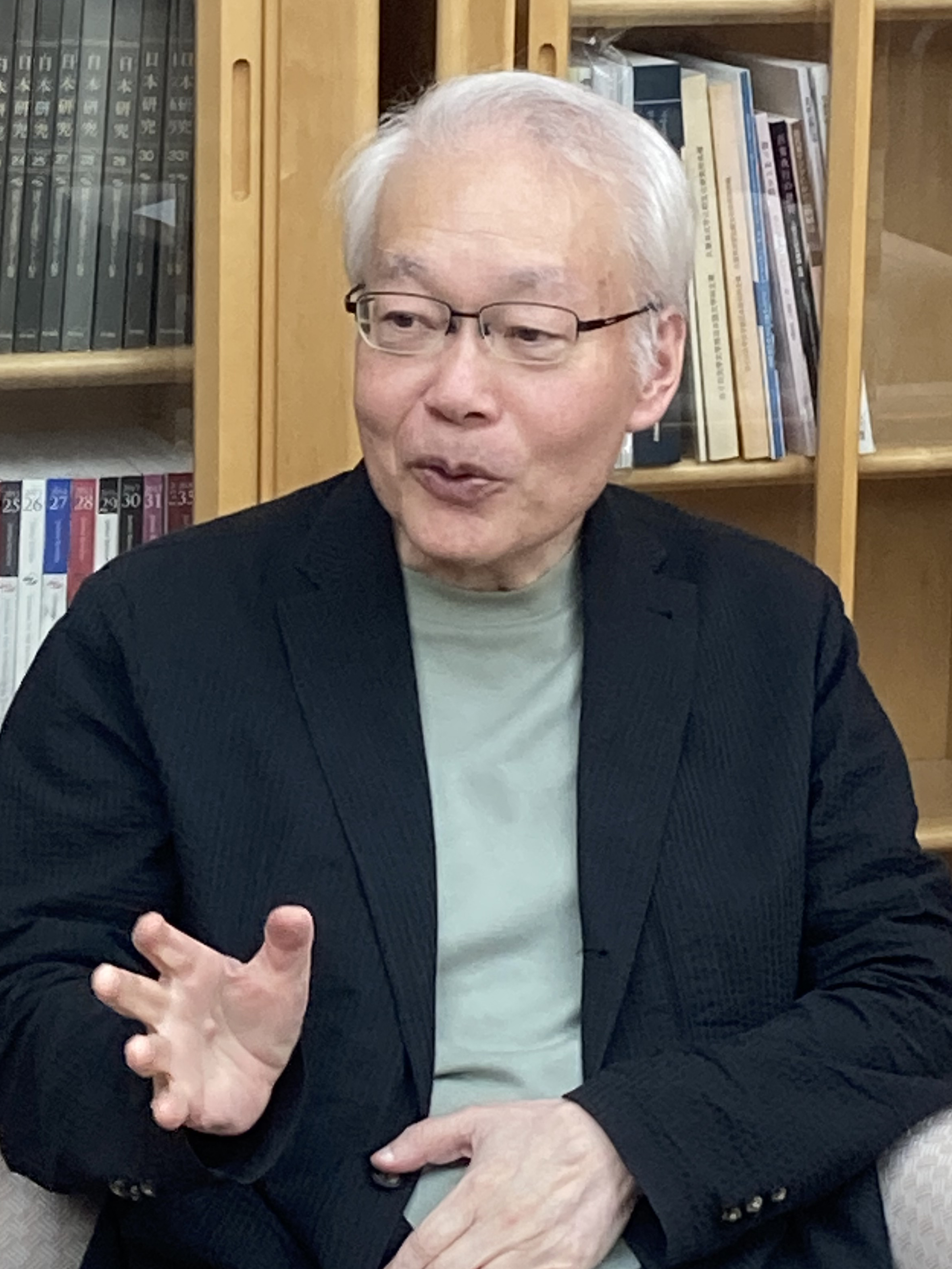対談 『統制百馬鹿』を読む 井上章一 ✕ 前田恭二(第2回)
前田恭二編『統制百馬鹿 水島爾保布 戦中毒舌集』刊行を記念して、近代日本の風俗史に通じ、『関西人の正体』『京都ぎらい』などの著作で知られる井上章一さんをお招きし、前田恭二さんとご対談いただきました。全3回でお届けいたします。(第2回、第1回はこちら)
ハルビンのストリップ批判
前田 今回の対談をお願いできないかとお電話したとき、1939年の満洲紀行で、水島が訪ねたハルビンにちょっと興味があって、というお話をされていました。ハルビンでは、ロシア人女性のストリップショーを見ているわけですが……。
井上 あれも勉強になりました。日本のストリップショーを論じた読み物は、終戦直後、新宿の帝都座に始まったとしか書きません。けれども、大日本帝国時代の日本人は、まあ男たちだけですが、しばしばハルビンで、ストリップを楽しんでいた。出張届けにハルビンと書くだけで、周りのおっさんたちがニヤニヤしたといいます。
前田 そうなんですか。
井上 ただ、大日本帝国が本格的に満州経営へ乗り出してからは、ハルビンのストリップはだんだん下火になっていったと、私は思い込んでいたんです。大日本帝国は道徳を満州におしつけたと。ところが、この本を読んで、戦時体制下でも相変わらずやっていたんだなと。
前田 水島自身、若い頃は猥談の名手だったらしいんですが、ハルビンのストリップに対しては、あんなものに金を払って、ポカンと口を開けて見入ったり、ゲスな笑いを発散したりする「日本人の馬鹿さ加減に気がついてもいいはず」と批判していますね。少し時期はさかのぼりますが、外国で娼婦を買う日本人のふるまいを罵倒した文章もあります。そこは倫理的というのか。
谷崎潤一郎と水島 感受性の違い
井上 どこかで以前、前田さんは同じ東京人、あるいは江戸ッ児ということで、水島と谷崎潤一郎に通底するところがあると書いておられましたね。そのことに関係して、あれっと思ったことがあります。細かい話ですけれども、女の人にモンペが支給された。あのいでたちだと、女の人のお尻が大きく見えるのが嫌だと、水島は言っています。
前田 1938年のコラムで、「あまり恰好のいいものじゃない」「ことさらにケツをデカくして」とけなしていますね。
井上 お尻の張った女の人が嫌だったんですよね。水島はすらりとした和風、柳腰をひいきする。いっぽう谷崎は、ハリウッド女優のメアリー・ピックフォードの足に魅了されます。
前田 たしかに谷崎の名作『痴人の愛』のナオミも、彼女のとりこになっていく男の想像の世界では、白人女性の白い肌に近づいていく。水島のほうは徹底的にアメリカ嫌いで、関東大震災直後、日系移民の排斥問題が起きたあたりから、物質文明の権化と見なして罵倒しつづけます。
井上 水島さんは谷崎と同じような育ち方をしているようで、感受性が違いますね。大正時代ぐらいからは映画もあったわけですが。
前田 アラ・ナジモヴァ(サイレント期の女優)については、ほれ込んだ映画評を残していますが、震災後には、アメリカ映画なんかボイコットしちまえと啖呵を切り、メアリー・ピックフォードと、当時は夫だったダグラス・フェアバンクスに対しても、来日したら塩をぶっかけろと散々ですね。
井上 私は、この問題にちょっとこだわりがあります。鈴木邦男(1943-2023)と、私は若い頃しばしば語り合う機会があったんです。忘れられないのは、どういう女の人が好みかと聞いたら、キム・ノバックとおっしゃる。それに続けて、ハリウッドの女優がずらずら出てきました。あなたは民族派の親分じゃないですか。岸恵子や岡田茉莉子はどうなったんだ、と思いました。問い詰めることはしませんでしたが、民族主義者にもアメリカニズムは浸透する。これは、研究するときにも忘れてはいけないなと思った。だけど、水島さんはちがいますね。

1941年12月の日米開戦を逗留先の新潟で聞いた水島は、暗々裏に敵対してきた両国の越しかたを考え、コラムを残している。
42年の漫画にはルーズベルトが登場した。
アメリカ嫌いの嫌米批判 戦時下のパラドクス
前田 水島の戦中コラムには、真珠湾攻撃の直後、そこに至る日米の因縁をたどった回があり、自身、アメリカ嫌いで通した来し方を回顧しています。
井上 新橋の芸妓さんが、アメリカ製のクリームは使わないと申し合わせをした折には「お前ら、今までそんなもん使ってたんか」といちゃもんをつけるとか。その一方で、筋の通らない嫌米論ははねつけた。1943年に、女性の竹槍教練を皮肉ったコラムがあります。アメリカでは女性飛行士を育成している、国家的野蛮行為だという記事を読み、女子に竹槍を持たせておくわれわれに、アメリカを野蛮という権利があるのかと。
前田 竹槍教練など「まさに浪花節を地で行こうて趣向だ」と皮肉る。アメリカ嫌いだったはずが、日米開戦後は、反米にも限度があるだろう、なんでもアメリカのせいにするのはおかしいと言い出す。よくあの時代に平気で言えたなあと思いますが、ああ言えばこう言うで、ほんとにへそ曲がりの人です。
井上 いや、私は筋が通っていると思いました。
前田 全体としてフェアで、理性的で、そこは私自身、水島という人が好きな理由です。ただ、常に憎まれ口を叩いていたはずが、いつの間にか正論を言わざるをえない立場になっていた気もします。世の中があまりにおかしい。彼の感じ方からしても、今日から見ても、かなりファナティックな時代になっていたことはまぎれもない。その中で減らず口を叩き続けていると、ぐるっと回って逆に正論の人みたいになってしまう。おそらく本人も意識しないまま、そういう立場に追い込まれたのではないかなと。
井上 そうか、丁寧に読んでいくとそういう変化がわかるのかな。
前田 大戦末期に、『孟子』だ『荀子』だと漢籍を引っ張り出すのも、結局、自身嫌っていた道学者流と変わらなくなる。
井上 本来、皮肉やくすぐりが得意だった水島さんを、戦時体制は道学者に追い込んでしまった。世の中をおちょくりたい人が、世の中が変になればなるほど、真面目な人になってしまうというパラドクス。

水戸黄門になった東條英機
前田 水島はこの時期、流言蜚語も意識的に書き残しています。そういう関心をもったきっかけは、関東大震災直後、朝鮮人暴動のデマやそれに煽られる人々を見聞したことです。そのあたりはさきほどの岩波ブックレット『関東大震災と流言』でも、解説でふれました。ちなみに、清水幾太郎の『流言蜚語』も、やはり中学生の頃、関東大震災後の混乱を体験したことが出発点だったようですね。
井上 東條英機を水戸黄門のようにみなす流言があった。私はこのことを全然知りませんでした。たとえば、闇米の袋を背中に負い、帽子をかぶせて赤ん坊に擬装していたおばあさんの話です。その帽子が落ち、闇米だとばれた。ところがすべてを了解しつつ「気をつけなさい」と帽子を戻してやった巡査がいたのだとか。この話が広がるなかで、巡査ではなく、たまたま居合わせた東條さんだったという話に変わったという。本当にこんな話が流布していたんでしょうか? これ、東條英機研究でも、あまり注目されていないんじゃないかな。
前田 あちこちの村落に東條英機が出没した流言も記していて、いずれ「東條首相廻国噺」の挿話になるだろうとまぜかえしています。映画化されて人気だった直木三十五の「黄門廻国噺」のもじりですね。本書に収録したコラムで、水島は何度か「親心」というキーワードを使っています。東條英機が「親心」を示す宰相として偶像化されるなかで、さまざまな流言が広がったのだと思います。
井上 僕の能力ではできませんが、これは比較指導者論になりますよね。ソビエト時代に、うちのお母さんを闇食料品の疑いから救ってくれたのはスターリンだったという話があっただろうか。ムッソリーニを水戸黄門のように語る話があるだろうか。
前田 それと流言については、ナショナルなメディアがきちんと機能しているかどうかも関係しますよね。関東大震災では新聞社が倒壊し、ろくに新聞を発行できない状況がしばらく続いていた。すると、にわかに流言が広がる。
井上 小メディアの乱立する時代はそういうものだったと思います。江戸の瓦版なんかも、とんでもないことを書いている。いまのSNSで広がる陰謀論とかデマは困ったことだと思いますが、フェイク・ニュースはそんな頃にもでまわった。
前田 以前、長く新聞社にいた身としては少し言いづらいですけれども、昨今の場合はナショナルメディアへの不信感と裏表になっているように感じます。
(ここまで第2回、第3回へ)