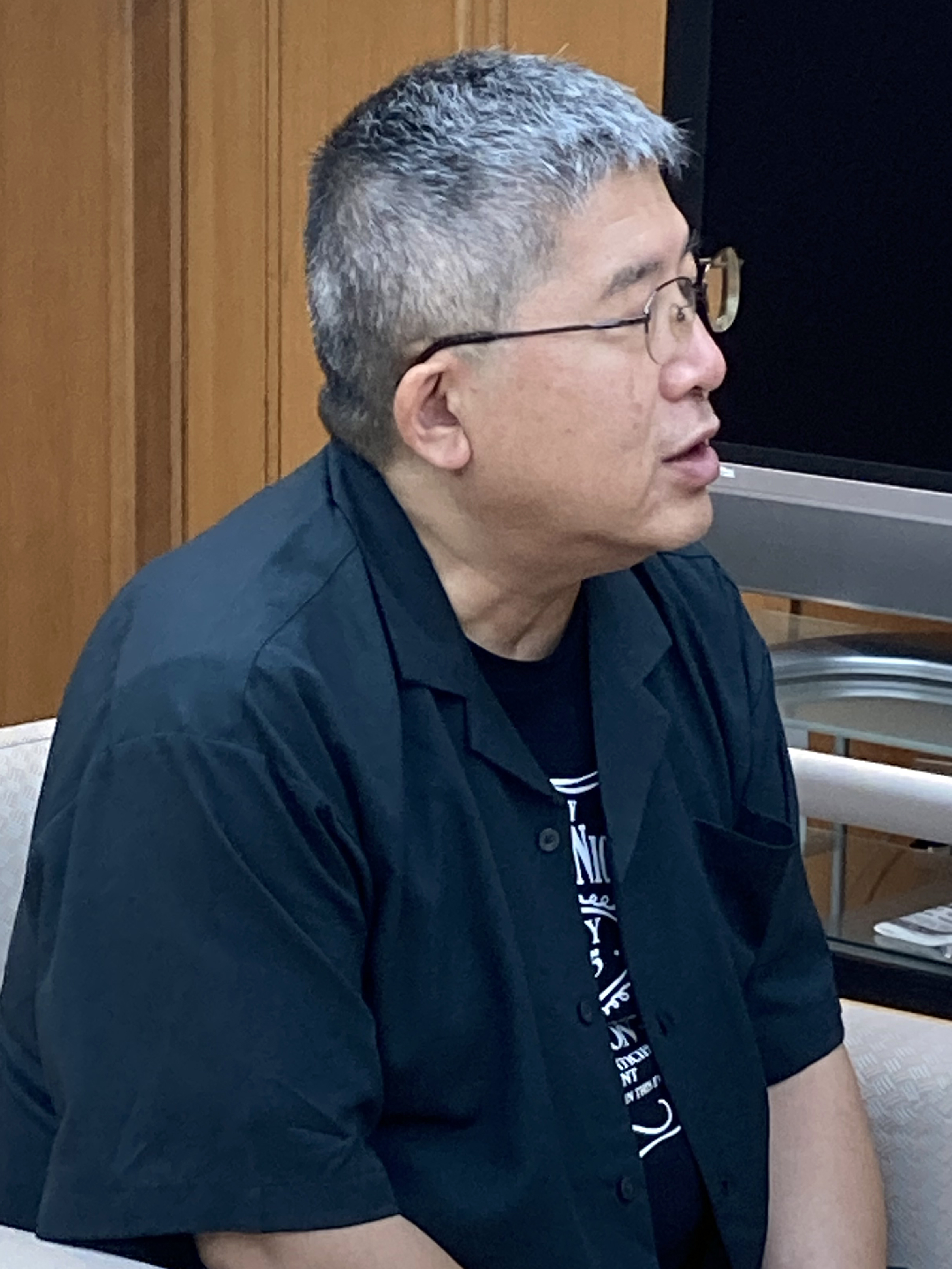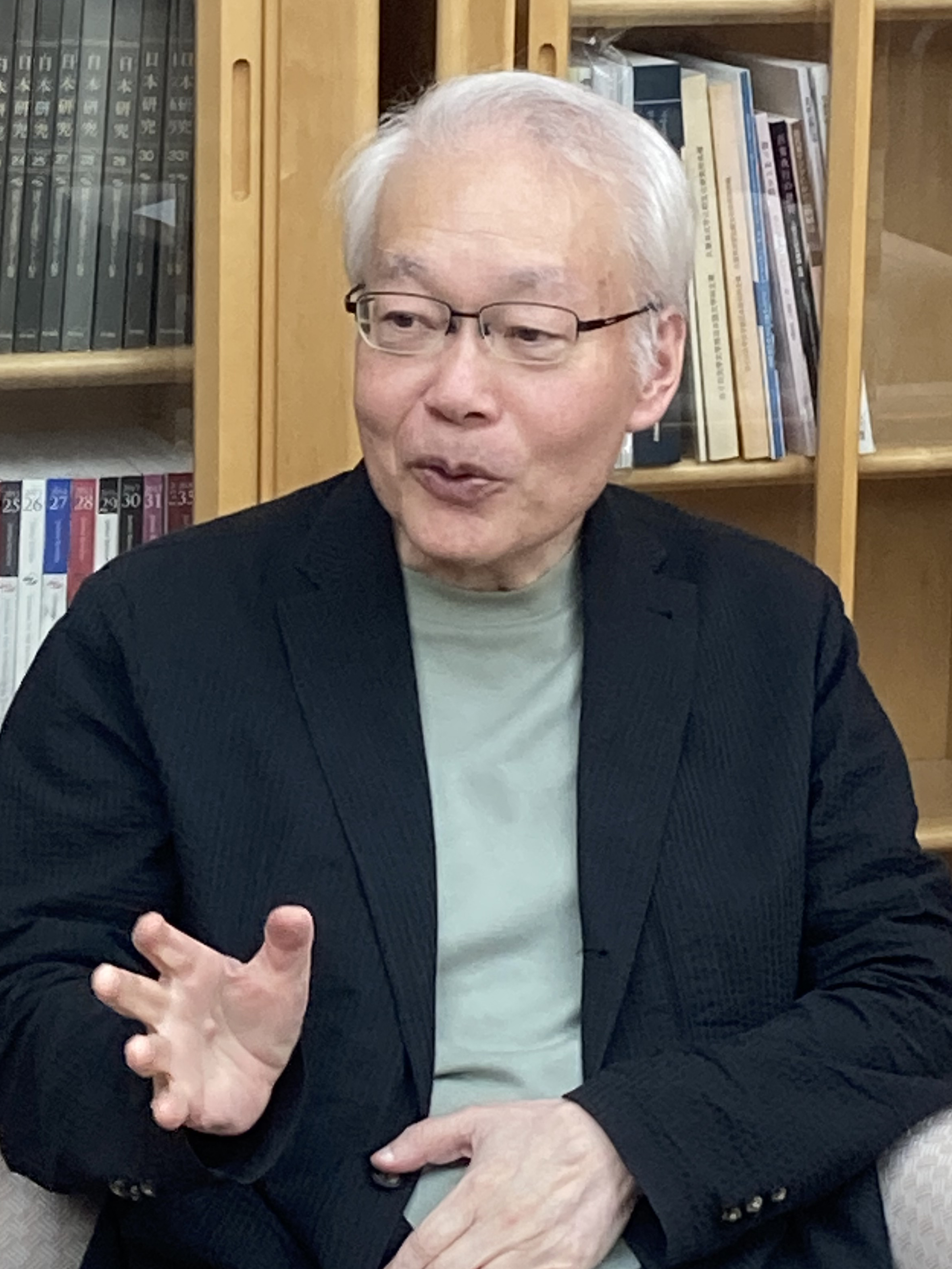対談 『統制百馬鹿』を読む 井上章一 ✕ 前田恭二(第3回)
前田恭二編『統制百馬鹿 水島爾保布 戦中毒舌集』刊行を記念して、近代日本の風俗史に通じ、『関西人の正体』『京都ぎらい』などの著作で知られる井上章一さんをお招きし、前田恭二さんとご対談いただきました。全3回でお届けいたします。(第3回、第2回はこちら)
満州紀行と気になる伏せ字
前田 水島の文章については、評伝を書くために(『文画双絶 畸人水島爾保布の生涯』、2024年、白水社)、片っ端から集めて読みました。そのなかで、これは広く読んでもらったほうが?と思ったテキストがありました。関東大震災の発禁版体験記「愚満大人見聞録」もそうですし、『統制百馬鹿』に抄出した1939年の満洲紀行もそのひとつ。水島は1929年、すでに満洲に渡っていましたが、満州でも南部だけだった。1939年の旅は第一次ノモンハン事件の直後にあたり、ソ連との国境地帯までめぐっている。しかも、遠慮会釈なく、現地の見聞を書いているすごみがあります。
井上 満蒙語が通り名になっている駅名、日本語が通り名の駅名が混在しているという話がありました。どうして佳木斯(チャムス)は現地語で、牡丹江(ぼたんこう)は和語なのか。真っ当な疑問だと思いました。
前田 地名については、日本人の勝手で好きなことはしない方がいい、という開拓村の人の意見まで書かれている。ただ、この満洲紀行には、延々と伏せ字が続く箇所があります。この時期、内閲(事前検閲)が復活していたはずで、さすがにこれはやめろと引っかかったのではないかと思いますが、『大日』時代のコラムは、政府・官僚を批判しても、あまり伏せ字になっていないんですよね。
井上 満洲紀行にありましたね。入国する際、朝鮮系の人や満州系の人からは税金を取るけど、日本人からは税金を取っていない。これはよくないと水島さんは書いていました。そのていどの指摘は伏せ字になっていないから、大丈夫だった。
前田 去り際には、満州は王道楽土などでなく、百鬼横行なんじゃないか、とまで書いていて、そのまま載っています。それを思うと、伏せ字の部分はヤバい話が具体的に書かれていた可能性が高い。文脈からすると、当時「匪賊」と言われた地方豪族たちよりも、はるかに悪辣な日本人の話だったかもしれません。
井上 阿片の話だったのかな。関東軍の軍資金になっていたと、公然の秘密だったようですが。
前田 この満洲紀行には、全般に水島らしい観察眼が発揮されていて、私自身、特に印象深く読んだくだりがあります。やはり開拓村を訪ねた時のことで、移民団の団長さんは、二十年後には満洲の模範田園にしたい、「第二世の若いところに、恋でもささやかせるとしますかなアハハハハハ」と、どんどんビールを飲みながら、大きな夢を語るのですが、そこで水島はさりげなく、「窓の外の小雨はいつしかドシャ降りになっていた」と書き添えている。実は調べてみると、この開拓村では終戦前後、避難しなかった人々は現地の農民に襲撃され、大半が命を落としたと言います。そこまで水島が予見していたとは思いませんが、どこか危うさを感じていたのではないか。そういう文章の呼吸になっています。

前川千帆、水島爾保布、森島直造、小野佐世男「伸びいく満蒙漫画行進」より
戦時下の団体旅行と大阪人
前田 ところで、ひとつお聞きしたかったことなんですが、水島はやはり生粋の東京人で、皮肉やギャグにも江戸っ子らしさがあるように思います。関西に長くお住まいの井上さんからすると、そこはどうお感じになったかなと。
井上 いや、特にコメントはありませんが、ただ、団体旅行の無作法な大阪人については、あっちゃーと思いました(笑)
前田 大阪の団体客と温泉宿で一緒になったあと、「あないなものは着いたすぐチャッと鞄に入れてしまうに限るンや」という会話が聞こえてきた。宿の置き物か何かをくすねようとして、しくじったらしいという、あの話ですね。
井上 やんちゃな関西人像には、メディアで作られた部分がある。つまり、フェイクだと、私は思いたがっています。ですからこんな時期からそういうやつもいたのかと、ちょっとがっかりしました。
前田 水島は耳も結構いい。方言、特に関西弁を再現できてしまう。もともと4年ほど、大阪朝日新聞社にいましたから。
井上 その関西弁については、私なりに言い分があるんです。おそらく日本中どこの方々でも、旅の恥はかき捨てという心性があったでしょう。そして、関西人以外の旅人は、特に東京なんかへ行くと、極力、土地言葉を自粛する傾向があった。だけど、当時の関西人は自粛をしなかったと思います。ちなみに、今は自粛しだしていますね。少なくとも、私が若かったころとくらべれば。
前田 戦時下の団体旅行ということ自体、表向きには物見遊山の旅は控えろとなっていたわけですが、水島が言うには、「皇軍の武運長久を祈る」として神社をひとつ、「戦没勇士の冥福を祈る」としてお寺をひとつ、必ず入れる旅程になっていると。これを水島は「時局的迷彩」と言い切っています。要はカモフラージュで、実際は物見遊山が横行していたというわけです。
生活史のディテール
前田 戦時体制に便乗する御用学者のことも、水島は繰り返し批判しています。雑草には栄養があるからと、雑草食を推奨したりする手合いのこと。
井上 黒砂糖は健康に悪い、蛔虫は黒砂糖のせいだといっていた人たちが、砂糖不足になると、黒砂糖を褒めはじめるとか。
前田 井上さんは、初期の著作『作られた桂離宮神話』の中で、ブルーノ・タウトが桂離宮を称賛したあと、戦時体制に入り、物資も乏しくなるなかで、反装飾のモダニズムとして桂離宮を捉える見方が広がった、と指摘されていたかと思います。ああしたことも、一種の御用学説みたいなものでしょうか。
井上 当時、桂離宮を論じた人たちに御用学説をふりまわすという自己認識はありません。ただ、彼らも、非主流的なモダンデザインをアピールするために、桂離宮が使えるとは思っていたでしょう。しかし、私自身は、モダニズムとは関係ないだろうと初めから考えていました。桂離宮は八条宮というお公家さんの別荘です。言ってみれば、ベルサイユ宮殿の片隅に、マリ-・アントワネットが建てた農村風の建物みたいなものです。自分の本とのかかわりで言うと、むしろ『霊柩車の誕生』という本に関係するんですが、葬式饅頭の話がありましたよね。
前田 あ、水島が東京美術学校(現・東京藝大)の学生だった頃の話ですか。紀州旅行の時、かろうじてありついたふかし芋をかじりながら、いったん豊かになったはずが往時に逆戻りしていると、食の変遷を回顧した際のエピソードですね。
井上 学生だった水島さんたちは他人の葬式にもぐりこみ、会葬者用の和菓子をもらっていたと書いてある。制服制帽だったりするから、いちおう礼服です。会葬者を装って参列できました。また、くすねた和菓子で茶話会を開いていたと。『霊柩車の誕生』という本を書いたときに、こうしたエピソード自体は知っていました。葬式を執行する側が得体の知れないやつらに菓子を持って行かれるという記録は、いっぱいあるんです。万が一、本当に会葬者だったらとんでもないことになるので、怪しいなと思っても大概は黙っている。だけど、饅頭を取っていった側、得体の知れない側からの記録に、今回初めて出あった。ちょっと感動しました。
前田 狩野芳崖ならぬ「狩野方外」と名乗ったとか、あけすけに書いてますよね。ひどい話なんですが(笑)
井上 ただ、葬式饅頭が配られる葬式を、日本古来の醇風美俗とたたえていらっしゃる点には、違和感を持ちます。江戸時代にそんなものはなく、明治期以降、ブルジョワが葬式で見栄を張るようになってからの風俗かと思います。
前田 水島が美術学校生だったのは明治時代後半のことですが、くわしく葬式菓子のラインナップを書いていますね。普通は塩釜で、ちょっといいと羊羹に薄皮饅頭、あるいは蕎麦饅頭だとか。
井上 生活の歴史を追いかけているような読者にはうってつけです。それぞれ読む人が自分なりの面白さを見つけられるように思います。

水島の時事漫画の掲載は、44年1月が最後。「アメリカ敗戦発表 配給のやうに戦報小出しなり」。この後、時事漫画はみられない。
おわりに
井上 戦時体制下の生活についても、後世からは一色で描かれやすいだけに、ディテールが大切で、水島さんは大事にしてらっしゃる書き手だと思います。さきほど中国の話をしましたが、テレビの見方に面白い娯楽があるっていうのも、たぶん中国共産党体制一色で語ってしまうと出てこない部分でしょう。私はうんこの話とか、やや俗悪な部分を面白がって取り上げましたが、いや、あの時代を一色にしてはいけないと思いました。
前田 たしかに何らかの観点から捉えようとすると、銃後のリアルというのか、ディテールが落ちてしまうことがありそうです。貴重なご指摘、ありがとうございます。
(ここまで第3回、終)