それぞれの『失われた時を求めて』第5巻『ゲルマントのほうⅠ』(講師:根本美作子 司会:坂本浩也)

残酷さをめぐるレッスン
でも、読みどころはそれだけではありません。今回は、プルーストにくわえ、カフカや日本近代文学(谷崎、三島、漱石)における夢の主題や意識の変容を分析してきた根本美作子さんを講師にお迎えして、テクノロジーの比喩と結びついた「距離」と「残酷さ」の問題に迫ります。
いつもどおり、このイベントレポートは忠実な文字起こしではなく、要約・省略・補足・再構成したものです。引用はすべて吉川一義訳、岩波文庫。丸囲み数字が巻、アラビア数字がページを指します。
すべてがプルースト的
根本 学校の友だちが『スワン家のほうへ』の「アスパラガスの描写が好き」と騒いでいたのをおぼえているので、きっと学校で抜粋は読んだはずですが(①269:第3回も参照)、正直にいうと、授業の印象はあまり残っていません。
坂本 ちなみに日本語では読んでいます?
根本 読んでいないです。
坂本 根本さんにとって「プルースト的」なもの、プルーストらしさとは?
根本 うーん、すべてがプルースト的なので、なにがプルースト的といわれても……。17歳でプルーストを読んで、通読したのは2回ですが、ずっとプルーストのプリズムがかかりっぱなしだから、ものの見かた、感じかたにプルースト・バイアスがかかって生きている。ぜんぶ読むっていうのは、そういう経験なんじゃないかな。
坂本 プルーストを読むとは、プルーストのものの見かたをとりこむこと。第6巻には「独創的な画家や芸術家は、眼科医と同じ方法をとる」と書かれています(⑥342)。芸術家による「治療」を受けると、世界は「昔の世界とはまるで異なるすがたであらわれ、すっかり明瞭に見える」。いってみれば根本さんは、もうプルーストになってしまった。
眠ること、想い出すこと
根本 これは聖書でいうと闇から光が創造される『創世記』のような場面で、作品全体がここに含まれています。眠りかけて起きて、という状態の描写が続くなか、ふと目覚めたとき「私」は自分が誰かわからない。どこにいるのかわからない。デカルト的なタブララサといえるでしょうか。たぶんプルーストの読者は最初に語り手といっしょに、目覚めたときの混沌に立たなくてはいけない、それが重要なのかなと思います。いくつもの部屋をだんだん想い出したあと、こんな文章がきます。
たいていの場合、私は、すぐにふたたび眠りこもうとはせず、コンブレーの大叔母のところや、バルベックや、パリや、ドンシエールや、ヴェネツィアや、その他の土地ですごした私たちの昔の生活を想い出したり、そんな土地や、そこで知り合った人たちのこと、そんな人たちについて私が見たり聞いたりしたことを想いおこしたりして、夜の大半をすごしたのである。(①36)
根本 固有名詞が並べられて、「私」が現実世界に結びつけられる。そして物語は、ここにあげられた土地で順番に展開していく。作品全体が胚胎されているすごく重要な場面です。
坂本 5巻まで読んできた現時点でふり返ると、最初に説明ぬきで書かれていた人名や地名の指すものがいくつかわかって、はっとしますね。はじめて読む人にはわからなくても、もちろんプルーストは、ちゃんと最初から計算して書きこんでいる。眠りというテーマは小説全体の構成においても重要なわけです。
根本 もしかするとプルーストは、小説を書き出す前、この冒頭で書かれているような状態にあったのかもしれない。
夜のただなかに目覚めたとき、自分がどこにいるのかわからないので、最初の一瞬、私には自分がだれなのかさえわからない。私は、動物の内部にも微かに揺らめいている存在感をごく原初の単純なかたちで感じるだけで、穴居時代の人よりも無一物である。(①29)
根本 みんな生きている時間の三分の一くらいは眠っていますが、その時間が自分の人生の物語にかかわっていると考える人は少ないはず。眠りの時間は忘れさられたり、無関係な負の部分と捉えられたりするほうが多い。でもプルーストは、その眠りの部分をまさに創造のはじまりにおいている。作中で「私」は習慣と徹底的に闘おうとしますよね。図式的にいうと、起きている時間は習慣でなりたっている。それを一度「エポケー」して、なにか新しい力をえるために、あえてマイナスの眠りの時間から始めたのではないかと思います。
坂本 眠りによって日常のなかの意識的なものをそぎおとすことで、なにかつかめるものがある、と。ちょうど5巻にもこんな文章があります。
眠りのなかに浸すのでなければ人間の生活を充分に描くことなどできない(⑤181)。
根本 眠りの不思議は、目覚めたときに他人ではなくまたちゃんと前日の自分になっていること、いわば「復活」していることにある、とプルーストはその先で書いています。目覚めることは、想い出すことに似ている。「そうだとすると死後の魂の復活も、ひとつの記憶現象としてなら理解できるかもしれない」とまで言っている(⑤188)。このあたりを読むと、眠りのテーマが、『失われた時を求めて』で重要な記憶のテーマと深く結びついていることが、よくわかります。
ゲルマントGuermantesの名をめぐる夢想の色合い
そもそも当時のゲルマントの名は、酸素なりべつの気体なりを封じこめた小さな風船のようなものだ。それを破って中の気体を発散させれば、私にもその年その日のコンブレーの空気を吸うことができる。そこに混じるサンザシの匂いは広場の片隅から吹いてくる風にあおられ、雨を告げるその風は、聖具室の赤いウールの絨毯のうえから陽の光を吹き飛ばしたかと思うと、こんどはその日の光をおなじ絨毯のうえにくり広げては、その絨毯にゲラニウムのようなバラ色に近い光かがやく肉色をあしらい、歓喜のなかにも祝賀の儀にふさわしい高貴さを保ちつつ、ワーグナーを想わせる心地よさを醸し出していた。(⑤27)
坂本 このゆたかな色彩描写は、時代を反映しているのではないか、という質問が届きました。「じつに甘美な薄紫色」は、オデットとの関連で頻出した色で、世紀末的な気がする。鮮やかな「赤」は、フォービスムや前衛芸術に代表される20世紀初頭の「原色」文化を思わせる。「ゲラニウムのようなバラ色に近い光りかがやく肉色」は、コレットの1920年代の小説に頻出するバラ色を思い起こさせる。もちろんある時代を一つの色合いで定義するのは無謀でしょうが、こうした色彩描写をどう読めるのか? どう「誤読」できるのか?
根本 ゲルマントは、中世と結びついた名前で、むしろ古色めかしい赤を思わせます。そこには高らかにラッパを吹き鳴らすような輝かしい響きがある。研究者ジャン・ミイによると、ゲルマントGuermantesは、コンブレーCombrayと音のレベルでも対照的だといえます。前者に含まれる鼻母音anが開いているのにたいして、後者のomはこもっている。こちらは墓つまりtombeやtombeauとおなじだと。ただし、コンブレーも、教会の地下室でゲルマントとつながっていることになるのですが……。
坂本 ゲルマントの「名」をめぐる色彩ゆたかな夢想について、音の重要性を感じさせるべつのくだりに注目した参加者もいます。
私はゲルマントの高名なタピスリーのうわさを聞いたことがあり、それゆえ私の目には、中世のいささか目の粗い青いタピスリーが、赤紫(アマラント)色の伝説的な名を背景にして、キルデベルト[訳注:メロヴィング朝のクロヴィス一世の息子、パリ王]が頻繁に狩りをした大昔の森のふもとに、雲のように浮かびあがるのが見えた。(⑤32-33)
坂本 ここでは、まるで言葉遊びのように、ゲルマントGuermantesと赤紫(アマラント)色amaranteという音の響きの類似によって、色彩が名前に付与されている。ひとつ不思議なのは、ゲルマントの名前が、ここでは赤紫、つまり赤紫蘇の色をしているのに、第1巻では「オレンジ色」とされていたこと。少年時代に主人公が思い浮かべるゲルマント公爵夫妻は、「つねにメロヴィング朝時代の神秘に包まれ、まるで日没時のように、ゲルマントの「アント」という音節から発するオレンジ色をおびた光に浸っていた」(①369)。
根本 ステンドグラスや幻灯にも言及されている箇所ですね。そうしためくるめく色彩が名前のなかにたたみこまれているという点で、「オレンジ色」は「赤紫」とつながっているのでしょう。
坂本 めくるめく色彩といえば、先ほどあげた引用の最後で「七色の独楽」というイメージが用いられています。「めまぐるしく慌ただしい日常生活」のなかでは、名前は「ひたすら実用にしか使われず、七色の独楽もあまりにはやく回転すると灰色にしか見えないのと同じで、あらゆる色彩を喪失することがある」(⑤28)。でも、夢想のなかではそうした運動が停止し、「さまざまな色合いが、横に並び、それでいて互いを判然と区別されて目の前によみがえる」。
根本 やはり物語の冒頭から登場する幻灯は重要ですね(①36-40)。『失われた時を求めて』全体が、幻灯みたいな世界観でできていると思えます。
オペラ座でラ・ベルマを観る
根本 正面から答えるのではなくて、問いをずらしましょう。ヴァンサン・デコンブという哲学者が、『プルースト、小説の哲学』という本(未訳)を書いています(Vincent Descombes, Proust : Philosophie du roman, Minuit, 1987)。『失われた時を求めて』、とりわけ最終篇『見出された時』には、芸術論とか文学論とか、哲学的なことがたくさん述べられているわけですけれど、デコンブの結論を言うと、そうした哲学的な芸術論よりも、小説全体としておこなっていることのほうがすばらしい。プルーストの芸術論にこだわりすぎるよりも、むしろ作品全体の流れに身を任せるほうがためになるのかなという気がします。
坂本 『失われた時を求めて』には、評論的なところと物語的なところがあります。どうしても評論のパートに大切なことが書いてあるような気がするけれど、そこにとらわれすぎずに、物語の実践を読むことが重要だという指摘ですね。
根本 ラ・ベルマの場合は、演劇論というより、主人公にとっての演劇体験という次元が物語上では重要でしょう。おそらくここも、マイナスの力、消極性がプラスになる場面のひとつです。女優に期待しすぎると演技を評価できなくなる。意識や覚醒、意志的な記憶は、芸術の受容、芸術の創造を妨害する。主人公は、むしろ力をぬいたときにはじめて作品が書けるということを学んでいく。
残酷さのテクノロジー(電話と写真)
根本 電話の場面では、受話器をとおして聞いたおばあさんの声が、肉体のない、習慣と切り離され、肉体のない「亡霊」「幽霊」のような声だという描写があります(⑤296)。それに続く帰宅の場面を読みます。(フランス語原文を朗読)
Hélas, ce fantôme-là, ce fut lui que j’aperçus quand, entré au salon sans que ma grand-mère fût avertie de mon retour, je la trouvai en train de lire. J’étais là, ou plutôt je n’étais pas encore là puisqu’elle ne le savait pas, et, comme une femme qu’on surprend en train de faire un ouvrage qu’elle cachera si on entre, elle était livrée à des pensées qu’elle n’avait jamais montrées devant moi. De moi — par ce privilège qui ne dure pas et où nous avons, pendant le court instant du retour, la faculté d’assister brusquement à notre propre absence — il n’y avait là que le témoin, l’observateur, en chapeau et manteau de voyage, l’étranger qui n’est pas de la maison, le photographe qui vient prendre un cliché des lieux qu’on ne reverra plus. Ce qui, mécaniquement, se fit à ce moment dans mes yeux quand j’aperçus ma grand-mère, ce fut bien une photographie.
遺憾ながら、客間に入った私が目にとめたのは、そんな幻影[幽霊]である。それは私の帰宅に気づかず、本を読んでいる祖母のすがただった。私はその場に居合わせたとはいえ、祖母がそれを知らなかったからには私はいまだその場に居合わせなかったというほうが正確かもしれない。編み物をしている女性は、不意に人が入ってくるとそれを隠してしまうことがあるが、それと同じで祖母は私の前で一度も見せたことのないもの想いに耽っていた。私はといえば――長くはつづかないが、帰宅した一瞬だけ、不意に自分自身の不在に立ちあえる能力を授けられる特権のおかげで――帽子とコートの旅すがたの証人であり、観察者であり、この家の者ではないよそ者であり、二度と見られぬ現場の写真を撮りにきたカメラマンにほかならなかった。私が祖母を見たとき、その瞬間、私の目のなかに自動的に映し出されたもの、それはまさしく写真であった。(⑤304-305)根本 この先、場面の最後のところで、主人公が撮った「写真」、つまりメンタルなイメージが描写されます。
Et, comme un malade qui, ne s’étant pas regardé depuis longtemps et composant à tout moment le visage qu’il ne voit pas d’après l’image idéale qu’il porte de soi-même dans sa pensée, recule en apercevant dans une glace, au milieu d’une figure aride et déserte, l’exhaussement oblique et rose d’un nez gigantesque comme une pyramide d’Égypte, moi pour qui ma grand-mère c’était encore moi-même, moi qui ne l’avais jamais vue que dans mon âme, toujours à la même place du passé, à travers la transparence des souvenirs contigus et superposés, tout d’un coup, dans notre salon qui faisait partie d’un monde nouveau, celui du Temps, celui où vivent les étrangers dont on dit « il vieillit bien », pour la première fois et seulement pour un instant car elle disparut bien vite, j’aperçus sur le canapé, sous la lampe, rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant au-dessus d’un livre des yeux un peu fous, une vieille femme accablée que je ne connaissais pas.
長いあいだ自分の面相を見たことのない病人が、見もせぬ自分の顔を、脳裏に想い描いた理想のイメージ通りにつくりあげていたのに、ふとのぞいた鏡で、干からびて何もない顔のまんなかに巨大なピンクの鼻がエジプトのピラミッドよろしく斜めにそびえているのを目のあたりにしてたじろぐのにも似て、私からすれば祖母はいまだ私自身でもあり、祖母を見るときはかならず私の心のなかのつねに変わらぬ過去の場所に据えつけ、隣りあい重なりあうもろもろの思い出の透明なプリズムを通して見ていたのに、突如として私が目にしたのは、わが家の客間という新たな世界、「時間」の世界、「ずいぶん老けたな」と人からささやかれる見知らぬ者たちの暮らす世界のなかに、はじめて、ほんの一瞬のあいだ――というのもあっという間に消え去ったからである――、ソファーのうえでランプに照らされ、赤らんだ顔をして、いかにも鈍重で品もなく、病魔に冒され、夢想にふけっているのか、本の上方にいささか惚けたような目をさまよわせている、見覚えのない、打ちひしがれた老婆であった。(⑤306-307)根本 このページを選んだ理由はふたつあって、まず第4篇『ソドムとゴモラ』における衝撃的な展開の伏線になっているから。『ソドムとゴモラ』では、世界の逆転とも天変地異ともいえるような展開がいろいろ起こるのですが、そのなかにはおばあさんと関連した重要な場面があります。
坂本 ここでいう残酷さは、身近な他者との日常的な関係における相互性、見る=見られるの関係が断ち切られることによってうまれるものでもあると思います。では「死ななければ書けない」とおっしゃるときの「死」は、他者との相互的な関係の断絶とも言えるでしょうか。「死」とは生や愛へのあきらめの別名でしょうか?
根本 それも含めてだと思いますが、やはり自分にたいしての距離ですね。全体をとおして、「私」も残酷に描かれている。日本の私小説でワルになりたがる私が自分を残酷に書くのとは違う。たとえば5巻でも、主人公がサン=ルーにゲルマント夫人に紹介してくれとねだるキモい場面があります(⑤214-221)。面白おかしい場面ですが、登場人物の「私」と書き手の「私」の距離はないと書けない場面です。
坂本 もうひとつのポイントは、距離をとおした残酷さが写真のメタファーで語られていることですね。
根本 写真も電話も、モデルニテのテクノロジーで、たしかに写真は当時すでに出回っているけれど、電話はまだ定着していないものとして描かれている。ふたつとも、ないものをそこにあらしめる技術です。電話をとおして、そこにいない遠い人、不在のものが今ここにたちあらわれるからこそ、幽霊になる。写真も、この場面はちがいますが、やはりおなじ機能をもっている。死というものと関係している技術です。
坂本 写真や電話という複製技術をとおして、「そこにいること」と「生きていること」が完全にイコールでは結ばれなくなるわけですね。複製された声や映像は、オリジナルである大切な人が生きていないかもしれないという疑念を生じさせる。電話が、むしろ祖母の死を想像させてしまう。写真も、そこにうつっている人が、むしろ死者ではないかと思わせてしまう。そこが残酷さの問題とつながっているのかなと思います。
根本 『ソドムとゴモラ』の重要な場面でたっぷり味わえるので、楽しみに読んでほしいですね。
(後記)セミナーの参加者は吉川訳をとおしてプルーストの魅力にふれているわけですが、今回は根本美作子さんの美しいフランス語朗読や、固有名詞の音韻的特徴への着目をとおして、原文の世界をかいまみる機会にもなりました。『ゲルマントのほう』は通読の難所といわれるものの、まだこの巻は比較的スピーディーに読み進められたという感想が寄せられました。物語のいたるところに、タイトルが予想させる「貴族社交界への憧憬と失望」というイメージにはまったくおさまらない、脱線のように見える(ときに詩的でときに残酷な)伏線が隠されていて、祖母との電話のエピソードもそのひとつです。セミナーではあまりとりあげられませんでしたが、ドンシエールの兵舎にサン=ルーを訪ねる挿話も、のちに重要な意味をもってきます。第6回は、専門の英米文学だけでなく、幅広く現代文学に通暁し、ユニークな読解法を提唱している阿部公彦氏を講師にお迎えして、「注意散漫」という角度からプルーストを読み解きます。
司会・レポート:坂本浩也(さかもと・ひろや)

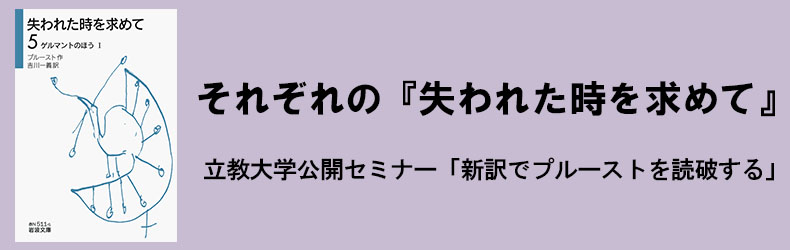
.jpg)



