それぞれの『失われた時を求めて』第7巻『ゲルマントのほうⅢ』( 講師:高楼方子 司会:坂本浩也)

講師:高楼方子、司会:坂本浩也
2018年10月6日、立教大学池袋キャンパスにて
テキスト:『失われた時を求めて』第7巻「ゲルマントのほうⅢ」岩波文庫、2014年
幼年時代の記憶、家族の会話と社交界の会話
プルースト・マラソンも第7回、いよいよ折り返し地点です。
全篇最大の難所と見なされる『ゲルマントのほう』。「私」はついに憧れのゲルマント公爵夫人邸の晩餐会と夜会に招待されます。しかし、その描写だけで300ページ近いとなると、怖気づく読者がいるのも理解できます。
そもそもなぜ、プルーストは長々と社交の場面を描いたのでしょう? 私たちはどんな心構えで、上流貴族の会話に耳をすませばよいのでしょう? 読みどころは語り手のコメントにあるのでしょうか?
この公開セミナーは、「プルースト研究者」ではないかたを積極的にゲストにお招きすることで、より自由に『失われた時を求めて』を楽しむことを目指しています。今回は、児童文学・絵本の分野で数多くの愛読者をもつ作家の高楼方子さんに来ていただきました。
2017年5月に出た『図書』の特集「岩波文庫、私の三冊」で、吉川訳『失われた時を求めて』をあげていた高楼さんが『記憶の小瓶』(クレヨンハウス)と題する自伝的なエッセイも書かれていると知り、取り寄せて読んでみた私は、プルーストとの親和性を感じさせるすばらしい文章に、すっかり魅了されてしまったのです。
さらに高楼さんには『老嬢物語』(偕成社)という、映画や小説のなかに出てくるいろんな「おばあちゃん」をじつに楽しく、愛をこめて論じた著書もある。ぜひレオニ叔母さんやフランソワーズ、主人公の祖母、さらにはセリーヌやフローラについても語っていただきたい!
というわけで今回は、記憶や回想の問題、老嬢ないし老婦人といったあたりに着目しつつ、前巻までの名場面・珍場面を振り返ったうえで、「ゲルマントの壁」の最終段階である第7巻の読みどころを探っていきます。
特別企画として、前巻までのセリフ当てクイズもあります。ぜひ挑戦してみてください。
いつもどおり、このイベントレポートは忠実な文字起こしではなく、ところどころ要約・省略・補足・再構成したものです。引用はすべて吉川一義訳、岩波文庫。丸囲み数字が巻、アラビア数字がページを指します。
(構成:坂本浩也)
プルーストとの出会い
坂本 プルーストとの出会いを語ってください。
高楼 スタートラインについて「よーいドン」と行く前に転ぶ選手っていますよね、まれに。ずいぶん前、はじめて手にとったのは3段組の全集[筑摩書房の世界文学大系]だったんですけど、1ページ目をめくってこりゃダメだと、そのまま本棚にしまって終わり。でも数年前にたいへん落ちこむことがあって、「いつまでも終わらない物語を読もう」と。自分なりに落ちこみの本質を探ってお話をひとつ作りたいという気持ちもあり、そのときに「そうだ、プルーストだ!」と思いました。ちょうど岩波文庫から出ていた新訳を夫に薦められて読んでみたら、「こんなにおもしろいものだったのね!」となって、ワクワクして線を引きたくなるところがいっぱいありました。
1巻の終わりに、「私」が読書のあと散歩して、傘を持ったまま土手の近くを走り回って、沼のほとりのあばら屋のまえで恍惚として「えい、えい、えい、えい」って叫ぶところがありますよね。この場面で語り手は、そういう感情をちゃんと言葉にするのが自分の「義務」だと思うのですが、私自身も、ぐちゃぐちゃした気持ちをなんとか変換しようとしてお話を作ってたので、関わりのある思いだな、と感じて嬉しくなりました。
瓦屋根は、太陽のおかげで新たによく映えるようになった沼のなかに、バラ色のマーブル模様を描いていたが、それは私が今まで気にとめたことのなかったものである。水面と壁面で、かすかな微笑みが空の微笑みに応えているのをみて、私は興奮し、閉じた傘をふりまわしては「えい、えい、えい、えい」と叫んだ。しかし同時に、私の義務は、このようなわけのわからないことばに甘んじることなく、恍惚状態にあってもさらに明確にものごとを見極めようとすることだと感じたのである。(①338)
高楼 これが私のプルーストとの出会いです。このたび再読していると、読みこぼしているところや、おもしろい発見がいっぱいあって、底なし沼みたいでズブズブとハマってしまうなと思いましたね。
子どもの視点
坂本 まさにこのセミナーは底なし沼への招待です。児童文学作家として、プルーストの小説における幼い「私」の視点については、どのように感じますか?
高楼 誰でも昔を回想することはできる、でも回想していて自分が子どものときこうだったな、ああだったなというときの過去を見つめる視点と、その時点に立って、子どもの目になって見つめるという違いはあるわけです。その区別は、とても難しいとは思うんですけど、1巻の最初のベッドのなかで過去を思い出しているときは、まだ自分がここにいて回想しているということですね。なおかつ「心細さ」にその頃はとらわれていますよね。それがひとつのポイントで、「心細い」という感情のときは自分が幼かった頃の心情と近いものになっていると思います。ですから、たとえばお母さんがキスをしてくれないとか、寝室に向かう階段のニスの匂いまで思い出すところは、かなり子どもの立場にくっついている。
4巻で、おばあさんと一緒にバルベックに行きますね。汽車のなかで一瞬、本当に子どもの視点になっていると思った場面があります。詰め襟のユニフォームを着て検札に来た車掌さんの銀色のボタンがキラキラしていたというところ。そのボタンがものすごく羨ましくて、「横に座ってくれるよう頼みたくなった」というフレーズは、そのときの自分の目になっているということを感じさせます(④50)。ふつう過去を回想するときにそういうことまで書きませんよね。そこに筆を伸ばしてしまう、それを書いてしまうのが、たいへんおもしろい。
バルベックに着いてから、おばあさんに会いたくてノックしたり抱きしめてもらったりするときの描写に、おばあさんの顔を大きいと表現するところがあります。どうですか、自分のおばあさんを思い出すとき、顔の大きさって、ふつうは浮かばないんじゃないかしら。でも小さいときの目になってみると大人の大きい顔が、目の前に迫ってくるんだと思います。
それから私が飽きることなく見つめたのは祖母の大きな顔である。その顔は熱い想いを秘めた穏やかな美しい雲のように浮かびあがり、背後には愛情が陽光のように輝くのが感じられた。(④81)
心細さというと、バルベックのホテルの部屋の紫色のカーテンが自分に対して「第三者がいて目障りだと肩をすくめる人の態度」をとっているようなよそよそしいものに見え、自分が拒否された寂しさを感じるという繊細な感情も描かれています(④78)。プルーストは、子どもの視点と今の視点との行き来がしやすい人だったのではないかしら。その点に関しては、私自身もたぶんにそうで、だから今の仕事は身に合ってると思ってるのですが。つまりただ思い出すだけじゃなく、ふとした拍子に、たとえばあそこの部屋の襖の一角だとか、庭のあそこに咲いていた花だとかが目に浮かぶと、そのときの視点にヒュッと移るわけです。そうするとそこからワーッと当時のことが思い出される。そういう子どもの視点にスッと行く回路が繋がって、油をさしたように滑らかになると、わりと行きやすくなる。
コンブレーの老姉妹と「ほのめかし」の喜劇
坂本 前巻までの、つまり『失われた時を求めて』前半の読みどころを語っていただきます。『老嬢物語』の著者からみると、主人公の祖母やレオニ叔母のような「おばあさん」たちの特徴はどこにあるのでしょう?
高楼 長い長いプルーストの小説の読みどころは? ときかれて「おばあさん」というのもずいぶんとずれた話ではあるんですが、でも、流してしまいたくない、一つの観点ではないかと思います。私自身がとても好んで読んだところだし、話題にしてみたいなと思っていました。
「おばあさん」というと、主人公の祖母、年齢不詳だけれど女中フランソワーズ、レオニ叔母さん、祖母の妹のセリーヌとフローラという老姉妹などがいますね。ヴィルパリジ夫人とかはおいておくとして。フランソワーズは全巻通して、主人公の生活に密着しています。祖母も密着する形でしばらく出てきます。けれどもレオニ叔母さんと老姉妹(セリーヌとフローラ)は、あとの巻にも回想として出てくるとはいえ、実像としては、ほぼ1巻だけに閉じ込められているといってもいいような存在です。その他おおぜいの登場人物は巻を追うごとに変遷していく。でもレオニ叔母や老姉妹は変貌しない。コンブレーという場所に閉じこめられて結晶化している感じがするんです。
この老姉妹は、ごくごく最初の、「マドレーヌ体験」以前の、ベッドに入って眠れない夜にたえず思いだしていたあのコンブレーの家(寝室や庭)という非常に限定された記憶のなかに入っている。そのときの「私」はお母さんが来てくれるか心配だという、不安のなかにいる時間帯なんですよ。にもかかわらず、このおばあさんたちの滑稽なやりとりをなぜここまで書いたのか?
これは私の想像ですけど、おばあさんたちのやりとりを見ていたときの幼い「私」は、それをさほど滑稽だとは思っていなかった。でも繰り返し繰り返し、年をとって思い出しているうちに、記憶のなかでキラキラっと光ってクスクスっと笑えるような、そういうやりとりだったという印象が醸成されてきたんじゃないかと思うんですね。
老姉妹がおじいさん(主人公の祖父)から「スワンにワインのお礼をするんだよ」といわれたとき、具体的に「あの高級なワインをありがとう」というのは下品だと思って、ほのめかして言うんですね。ただあまりにもほのめかしているからわけが分からなくなっちゃう。家族が夕刻の庭にいるところにスワンがやってきて、そこでおじいさんとスワンが高尚な話をしようとする。そのあいだに姉妹が割りこんで辟易させる場面です。
「親切なお隣さんに恵まれてるのは、ヴァントゥイユさんだけじゃありませんわ」とセリーヌ叔母が大声を出した。その声は、臆病さゆえに大きくなり、あらかじめ考えていたせりふであるがゆえにわざとらしくなったが、そう言いつつスワンに、本人が言うところの意味ありげなまなざしを投げかけた。するとフローラ叔母は、この発言がアスティ・ワインにたいするセリーヌの御礼だと悟り、たんにセリーヌの機知を際立たせようとしたのか、そんな機知を想いつかせたスワンを羨んだのか、それとも矢面に立たされたスワンをからかわずにいられなかったのか、スワンを称賛と皮肉のまじった目でじっと見つめた。(①67-68)
こういうやりとりがずっとあって、スワンが帰ったあと、
「なんだって。お前たちは、あれが御礼だと言うのかね!」と祖父は大声をあげた、「たしかにそれは聞いたが、あれがスワンに向けたものとは思えなかったぞ。スワンにはなにも伝わらなかったと考えといたほうがいいかもな。」「とんでもない。スワンだって、ばかじゃありませんよ。」(①87)
こういうワインをめぐるやりとりっていうのがひとくさりあって、そういうのがすごくおもしろいところだったんですね。
その後は、この姉妹はそんなに出てこない。このあと少ししてルグランダンという、スノビスムの見本みたいな人物が出てくるのですが、この人の妹さんは地方貴族に嫁いでカンブルメール夫人になっている。それで、祖母と「私」がバルベックに行くときに、お父さんがカンブルメール夫人に紹介してほしいとルグランダンに頼むんですが、紹介したがらないわけです。そのことについてこのセリーヌとフローラの老姉妹が、プリプリ怒っている。そのとき「私」がこう書くんです。「私たちが侮辱された仇を討つためか、母親のルグランダン夫人を訪問しても[老姉妹は]娘の名前はもはや口にしないことにした。」「あなたも知ってる人のことはほのめかしもしなかったわ」「あれでだいたいおわかりになったと思うわ。」というようなやりとりが4巻にあります(④36)。そういうちょっとしたところが、とてもおかしい。
セリーヌとフローラへの言及がのちに登場するのは6巻。おばあさんが危篤のときに電報を打つんですが、大好きな自分の姉であるにもかかわらず来ないんです。そのときの断りかたがまたおかしいんですね。「すばらしい室内楽の演奏をしてくれる音楽家を見つけたので、その音楽を聴いているほうが病人の枕元にいるより、一段と瞑想にも悲痛な精神的高揚にもいいと考えたので」(⑥337)という。それについてもおじいさんが「あのふたりを恨んじゃいかん。完全に頭がおかしいんだから、」(⑥375)と言います。二人はこういうふうに出てくるんですが、記憶のなかの懐かしいコンブレーのなかで、小さいけれども滑稽味とともにチカチカっと光って、「私」を幸福にしてたんじゃないかなと思います。
レオニ叔母
高楼 レオニ叔母さんは、マドレーヌを食べて記憶がバーッと広がったときからどんどん出てくるおばあさんです。おかしなところはいっぱいあるんですけど、たとえば「自分は絶対に寝ない」と言ってるんです。だからつい「こんな夢を見た」と口を滑らすと、しまった、と赤面してごまかす(①124)。ベッドから窓の外を一日中眺めていて知らない人が通ったならともかく、知らない犬が通った場合でもそれが何者か気になって気になってしょうがない(①139)。元気づけようとしたお見舞い客から「「健康を気にする」のはやめるよう忠告」されるとムッとし、「私の容体、かなり悪いの。」という弱音に対して「そりゃ、健康でなくっちゃ大変ですね。」などと相槌をうたれると、これにもムッとして追い払ってしまう(①162以下)。声かけの加減がいかに微妙で難しいか、そこの描写がとてもおもしろい。
レオニ叔母さんの思い出が美しいと思うひとつのポイントとして『千夜一夜物語』のお皿というのがあります。
「卵のクリームソース添えは、かならず平らなお皿で持って来てね。」この皿のセットだけに絵が描いてあり、叔母は食事のたびに、その日に出てきた皿の説明文を読むのを楽しみにしていた。叔母はメガネをかけ、ひと文字ずつ、アリババと四十人の盗賊、アラジンと魔法のランプ、と読みあげ、にっこりしては、「なるほど、なるほど」と言うのだ。(①137)
この場面がすごくかわいい、と最初に読んだときはそう思ってたんですけど、ずっと読んでいくと『千夜一夜物語』というのが、大事な意味を担っていることに気がつきました。プルーストにおける『千夜一夜物語』についての論文も書けるんじゃないかと思うんですよね。
坂本 じっさいフランスでは研究書も出版されています。
高楼 叔母さんが読んでいるのはかわいらしい子どものお話的なものだと思うんですよ。不思議な異国のお話。でも本当はもっとおどろおどろしいものですよね。「私」が大きくなってから『千夜一夜物語』を思い出すとレオニ叔母さんを思い出すというふうに、長い人生の中であたかもレオニ叔母さんがお話のなかの人物のように存在している。レオニ叔母さんが眺めるお皿と、「私」が『千夜一夜物語』と聞いて思い出すレオニ叔母さんは、どこか関係があるのではないかと思います。
子ども向けのお話と、もっとおどろおどろしい大人向けの『千夜一夜物語』のことも巻を追うと出てきますね(8巻)。お母さんとしては子どもヴァージョンだけ読んでほしくて大人ヴァージョンは読んでほしくないという気持ちが出てくるところもあるんですが。レオニ叔母さんというか「おばあさん」一般が、あたかもお話の世界のものという感じで、これが「おばあちゃん性」というものにつながるかなという気もします。
坂本 プルーストの世界では、登場人物、あるいはその見方、イメージが変わっていきます。錯覚や思いこみが連鎖していくともいえます。でも「おばあさん」的な登場人物はその連鎖を免れ、変わらない存在として描かれている。主人公の生きている時間のなかで変わりゆく人間関係を超越した、お話の閉域のなかにいる存在なのかもしれません。
高楼 閉じこめられて結晶化して、変容のしようがない存在として、また女っぽさや危険な香り、おどろおどろしさ、ソドムとゴモラ……といったところからも免れた「おばあさん」という存在を体現しているのが、老姉妹であったりレオニ叔母であったりするのかなあと思います。超越的な時間といってもいいかもしれませんね。
坂本 老姉妹の「ほのめかし」の場面など、プルーストのコミック作家としての腕も冴えていますね。
高楼 そうですよね。「読者を喜ばせる作家」であるということが『クロワッサン』での坂本先生と小山田浩子さんとの対談でありましたよね[『クロワッサン』981号(2018年9月10日発売)「お茶の時間 プルースト入門2 坂本浩也さん×小山田浩子さん」]。ただ「読者サービス」としておもしろおかしく書いたというよりは、そう書かざるをえなかったというか、そういう資質の人なんじゃないかと思います。
セリフ当てクイズ
坂本 この7巻でちょうど『失われた時を求めて』の前半を読み終えたことになります。これまでの名セリフをクイズ形式で振り返ってみたいと思い、各巻からひとつずつ、高楼さんに選んでいただきました。それぞれ誰のセリフか、どんな場面か、みなさんに考えていただきましょう。
【第1問】
『スワン家のほうへⅠ』「コンブレー」より
「もしこの鐘塔がピアノを弾くようなことがあれば、きっと無味乾燥には弾かないでしょうね。」(①151)
【第2問】
『スワン家のほうへⅡ』「スワンの恋」より
「あんなに頭のいい男が、あの手のばかとか言われている面白くもなんともない女のために苦しむなんて。」(②344)
【第3問】
『花咲く乙女たちのかげにⅠ』「スワン夫人をめぐって」より
「トロンベール夫妻が服従したからには、近隣の部族もおっつけ降伏するでしょうね。」 (③198)
【第4問】
『花咲く乙女たちのかげにⅡ』「土地の名──土地」より
「とくに競馬の初日にうっとりさせられたのは、このうえなくエレガントなご婦人がたが、オランダのような湿った光の中に佇んでいて、日向にいても水が滲みこむような冷気が感じられたからです。」(④543)
【第5問】
『ゲルマントのほうⅠ』より
「じつのところ私は、わが身を流謫としか感じられぬかような地上に帰属感など覚えません。」(⑤334)
【第6問】
「ゲルマントのほうⅡ」より
「結局われわれは、自分の暮らす樽の底で、ディオゲネスよろしく人間を求めているのだ。」(⑥252)
第7巻の読みどころ
サン=ルーについて
坂本 それでは第7巻の読みどころに移りましょう。サン=ルーとの「友情の夜」について、参加者から事前に質問が届きました。ステルマリア夫人と会う約束が取り消されて絶望した主人公のまえに、サン=ルーが現れ、霧の中、レストランに案内してくれる場面です。
「道に迷うどころじゃない、自分がどこにいるのかわからないんだ」というセリフからもわかるとおり、深い霧の夜です(⑦143-144)。同時に、友情をめぐる認識のちがいが語られる場面でもあります。質問者のかたは、高楼さんの『時計坂の家』(福音館書店)にも言及しながら、この場面に主人公の「迷い」を読みとっている。実際、主人公が回転式ドアから抜け出せない、というコミカルな場面もあります(⑦134)。ではそうした「迷い」のテーマと「友情」のテーマにはどういう関係があるのか? 「迷える主人公」にとって、この「記憶に残る友情の一夜」はどのような意味をもつのか? 高楼さんは、主人公とサン=ルーの友情をめぐるエピソードをどのように読んだのでしょう?
高楼 サン=ルーはカッコいいんですよね。とくに「私」にコートを持ってきてくれる場面(⑦154-155)では、長椅子に座った「私」が立たなくていいように、「競走馬が障害物をとび越すよう」な身のこなしで曲芸まがいのことをして手渡してくれます。みっともない人だったらズテンってどこかにぶつかって、頭からひっくりかえったりしますよね。サン=ルーは絶対そういうドジなことはしない。紳士的だし、いろんな美質はあるし、「私」のおばあさんもサン=ルーを気に入りますよね。先をずっと読んでいくと「あれ?」と印象が変わっていくわけですが。
この「友情の一夜」は、すごく好きなところです。サン=ルーと出かける途中、「私」がコンブレーやドンシエールのことを思い出す。それぞれの場所の記憶がそれぞれ違うものであることに気がついて感激するページです。ここで「私」は、記憶をめぐる幸福な啓示に近づくわけですよね。でも、もう少しで真理をつかもうとするときに、サン=ルーがそばにいるものだから、じつは邪魔なんです。
ふつう「友情のなかに投げ込まれた」というとポジティブな意味になりそうですが、この「私」にとって「友情」はちっともよいものではない。価値のないものなんです。いろいろなことを悟るのは自分ひとりの頭で、孤独のなかで到達するのであって、友人はむしろ夾雑物なわけです。「少女たちと遊ぶ楽しみは精神生活と無縁なだけに、友情のように精神生活を損なうことはないと考えていた。」っていう記述もありました。(⑦122)
サン=ルーは自分の一夜を一生懸命「私」に注ぎ込んで、相手のために自分の友情を捧げようとしてくれるけど、それは「私」がサン=ルーに見出した美しさとはぜんぜん違うものです。サン=ルーのなかに見出したのは、サン=ルーが自分で否定して乗り越えようと思っている貴族的なもの。そこからして友情は相互的な、インタラクティヴなものじゃなくなっていますね。「私」の認識って、「見るもの」なんです。身のこなしを含め、相手を対象物として、材料のように認識している。
このときにもしサン=ルーがそこにいなければ、無用な回り道をしないで、啓示をつかみとっていたかもしれない。尻尾をギュッと捕まえてしまったらよかったのに、パッと放してしまったために、ズルズルと最終巻の「見出された時」までこの人は書くはめになってしまった。
幸福と芸術について
坂本 この巻は一般に退屈とされ、読者が挫折しやすいところなので、私は「ゲルマントの壁」と呼んでいるのですが、この夜のシーンなど、意外と奥が深くて面白い読みどころもしっかり隠れています。
高楼 「壁」といわれれば社交の場面はそうかもしれないけど、ここはとても美しいシーンですよ。
われわれは自分の人生を十全に活用することがなく、夏のたそがれや冬の早く訪れる夜のなかにいくばくかの安らぎや楽しみを含むかに見えたそんな時間を、未完のまま放置している。だがそんな時間は、完全に失われたわけではない。あらたな楽しい瞬間がそれなりの調べを奏でるとき、その瞬間も同じくか細い筋をひいて消えてゆくのだが、以前の時間はこのあらたな瞬間のもとに駆けつけ、オーケストラの奏でる豊饒な音楽の基礎、堅固な支えとなってくれるのだ。かくして失われた時は、たまにしか見出されなくとも存在しつづけている典型的な幸福のなかに伸び広がっている。(⑦125-126)
高楼 この「典型的な幸福」という表現に少しひっかかります。「現在の例でいえば、それは快適な場所で友と夕食をとる」(⑦126)ことだと書いてありますから、いわゆる「愉楽」と考えていいのかもしれませんね。食べることや飲むこと、生理的な快楽、居心地のいい満たされた状態というふうにとっていいのかなと思って読んだのですが……。
坂本 ここは「幸福」にくわえて、「失われた時」と「たまにしか見出されなくても」という表現によって、作品全体をつらぬく記憶と時間のテーマが示唆されている重要なパッセージですね。音楽の比喩も印象的です。
高楼 宙づりにされていた時間が消えていくんじゃなくて、何かがあったときにもう一回ヒューっと駆けつけてきて、基礎の低音というものをさらに堅固にしてくれる感覚ですよね。
ゲルマント公爵夫人について
坂本 このセミナーの後半では、参加者同士のディスカッションの時間を設けています。そのとき全員に「私の選ぶ1ページ」を提示してもらいますが、それに先だってゲストに1ページ選んで解説していただきます。高楼さんが選んだのは次の一節。ゲルマント公爵夫人が、ユゴーの詩を暗唱するところです。
公爵夫人は、詩にふさわしい感情を託し、おのが抑揚にありったけの力をこめて悲しい想いを絞りだし、声のかなたへと投げ出したその想いを夢みるような魅力あふれるまなざしで見すえつつ、ゆっくりと朗唱した。[…]公爵夫人は、苦悩をあらわす口もとを醒めきった笑みで優雅にくねらせながら、[同席している]アルパジョン夫人のうえに、明るい魅力あふれる目から発する夢みるようなまなざしを注いだ。私は、そんな目や、重々しく尾をひいて耳を刺激する快い声の正体がわかる気がしてきた。この目、この声のなかに、ふんだんにコンブレーの自然が含まれているのに気づいたのだ。(⑦326-327)
高楼 少し先に、「まるで古い唄を聞いているときと同様の安らぎ」という表現があります(⑦330)。公爵夫人の声は低くて、きっとふつうにいったら美しくない声なんでしょうね。でも「私」はその声のなかに「イル=ド=フランスふうで、きわめてシャンパーニュふうと思われる」土着的なものが含まれているのに気づくんですね(⑦329)。井上訳や鈴木訳では「シャンソン」となっているところを、吉川先生が口偏の「唄」をあてて「古い唄」と訳されていて、童謡のような素朴な感じを醸し出しているなと思いました。「シャンソン」というと日本人にはお洒落なものに聞こえてしまいますが。
さらに先、「夫人が文学の話をすると私には愚かなフォーブール・サン=ジェルマン[貴族社交界]の典型としか思えなかった」という文章があります(⑦331)。せっかくゲルマント公爵夫人に良いところがあるのに本人はそれに気がついていないんだよな、というところなんですよね。
私はゲルマント家と対置されているクールヴォワジエ家の社交の話は、それほど退屈ではなかったんです。なぜかというとナラティヴがおもしろいから。ところがその後に「ライヴ」で聞かされるゲルマント公爵夫人の才気(エスプリ)は、そんなに面白いとは思えなかったんですよ。吉川先生は「あとがき」で、クールヴォワジエ家がいかに凡庸な貴族であるかわかると、対照的にゲルマント家の才気が冴え渡って、そこに居合わせるお客さんたちと同じような目で読者も公爵夫人の気の利いた冗談を楽しむことができるって書かれていたんですけど、私には「そうなのかなぁ」っていう感じでした。
だって、これはプルーストの筆がそうさせるんだけど、嫌な感じなんですよ。公爵夫人はウケを狙ってるでしょ。「こう言えばウケる」と思って、言うな言うなと思ってたら「あ、言った」みたいな、目から鼻に抜けるような、そういうタイプの冗談を次々いうのは、はっきり言って読んでいて、一緒に笑える余裕はなかったですね。はぁ、嫌になっちゃったと思っていたところへ突然くるんですよ、公爵夫人ならではの美しい声と表情が。まるで古い鐘がカランコロン……って鳴ったみたいな綺麗さで。本当はゲルマント公爵夫人っていいもの持ってたんだってことを、「私」と同じように私も感じたんですね。だから「私」が感じたような退屈を感じるためにリアルな会話があったんじゃないかと思うわけなんです。
セリフ当てクイズ第3問のなかで「存在を証明するかのような会話」と言ったのは、そういうことですね。読者も同じようにそれを通過する。通過するこの退屈さというか腹立たしさというか、そういうものがあったからこそ、目のなかの青空だとか、声の響きだとか、「古い唄」だとか、そういうところに「いいものあるなぁ」と、一緒に大きくため息をついたページです。
そんなゲルマント夫人を見つめながらその声に耳を傾けていた私には、夫人の目に宿る果てしなく穏やかな午後の光のなかで、そこに囚われたイル=ド=フランスやシャンパーニュの空が、[夫人の甥である]サン=ルーの目のなかでと同様の角度で傾き、青味をおびて斜めに広がるのが見えた。(⑦330)
高楼 6巻に、この先ぶれがあります。ちなみにこの段階では主人公はまだ公爵夫人に憧れています。
ずっとのちに夫人がもはや興味をそそらぬ人になり果てたとき、はじめて私は公爵夫人の多くの特徴を認識できたが、そんな特徴のなかにはとりわけ(当時の私がはっきり識別できないまますでに魅惑の虜になっていたものだけをさしあたり挙げると)夫人の目があり、その目はフランスの午後の青い空をまるで画に描いたように映し出して広々と晴れわたり、たとえきらきら輝いていないときでも明るい光をたたえていた。ついで挙げるべきは声で、最初に出てくるしわがれた音だけを耳にすると粗野にも聞こえかねないその声には、コンブレーの教会の石段のうえや広場の菓子屋の店先と同様、田舎の太陽ののらくらとくぐもりがちな黄金色の光が消えやらずただよっていた。(⑥71-72)
高楼 こういうところに本当の美質がある。それは先天的なもので、貴族のものって実は土着的なものだと思うんです。田舎の広大な土地にお屋敷があって、遊ぶときは「ネコをいじめたりウサギの目玉をくり抜いたり」と、粗野なことをしていた(⑦350)。そんなやんちゃな娘なのに、上流貴族の教育によってどんどん洗練されていって、結果的に本当のよさが覆われていることに、語り手は気がついたんじゃないかと思います。
ちょっと上から目線に、「あなたのよさはここよ」「バカでかわいいところがいいのよ、利口ぶらなくていいの」みたいなことを言う人っていますよね。「私」は恋人アルベルチーヌだけじゃなく、公爵夫人のこともそういうふうに見ていたところがあります。長い長いゲルマント公爵夫人のおしゃべりが幻滅だったというのは、ちゃんと書いてありますよね。「期待とは大違いであったこのフォーブール・サン=ジェルマンへの旅と到着がもたらした幻滅」(⑦330)。
ここは、コンブレー的なものを感じたのが、とても重要だと思います。それまで「ゲルマント」はオレンジ色だとか明るいイメージでしたけれど、その奥に入っていたのはコンブレー的な、灰色の裏寂れたようなイメージ。それが感じとられたところで、シンパシーというか愛しさを感じたのかなと思わせる場面です。
(後記)まずは更新の遅滞を全方面にお詫びしなくてはなりません。それにしてもコロナ禍をはさんで振り返ると、吉川訳を手にした数多くの愛読者が一堂に会する企画が14回も実施できたのが夢のようです。そのちょうど折り返し地点にあたる第7回は、「専門家」以外がプルーストのおもしろさを思い入れたっぷりに語るというセミナーのコンセプトを、まさに体現するすばらしい時間になりました。『失われた時を求めて』を自由自在に引用する高楼方子さんの声をとおして、作品のいたるところで響きあう多様な主題──幼年時代、「おばあさん」たち、家族と貴族の会話──の豊かさを再確認することができました。かくしてゲルマントの壁がついに崩壊。次回からは、いよいよ「ソドムとゴモラ」の世界へ入っていきます。
講師:高楼方子(たかどの・ほうこ)
函館市生まれ。東京女子大学文理学部日本文学科卒業。絵本に『まあちゃんのながいかみ』(福音館書店)、「のはらクラブ」シリーズ(理論社)、童話に『ルゥルゥおはなしして』(岩波書店)、『トムと3時の小人』(ポプラ社)、高学年向きの近著に『4ミリ同盟』『黄色い夏の日』(ともに福音館書店)、翻訳に『小公女』(福音館書店)、エッセイに『記憶の小瓶』(クレヨンハウス)、『老嬢物語』(偕成社)など、著書多数。『いたずらおばあさん』(フレーベル館)で路傍の石幼少年文学賞、『キロコちゃんとみどりのくつ』(あかね書房)で児童福祉文化賞、『十一月の扉』(リブリオ出版→福音館書店)『おともださにナリマ小』(フレーベル館)で産経児童出版文化賞、『わたしたちの帽子』(フレーベル館)で赤い鳥文学賞・小学館児童出版文化賞、『わたし、パリにいったの』(のら書店)で野間児童文芸賞を受賞。
司会・レポート:坂本浩也(さかもと・ひろや)
立教大学教授。著書に『プルーストの黙示録──『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』(慶應義塾大学出版会、2015年)、訳書に、ピエール・ブルデュー『男性支配』(坂本さやかとの共訳、藤原書店、2017年)など。ツイッター「プルーストを読破した@立教」を更新中。

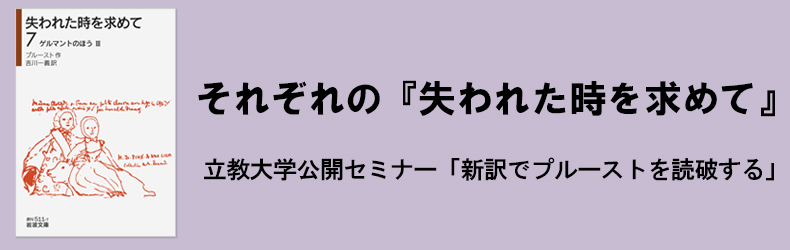
.jpg)



