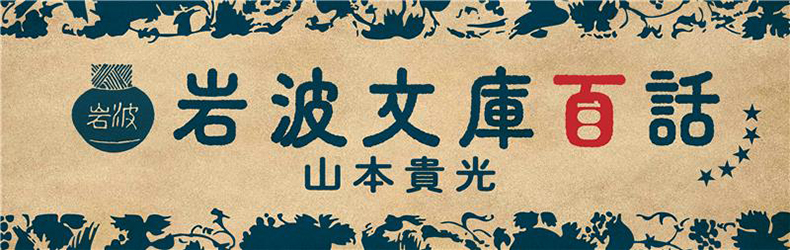第13話 2400年にわたる哲学
岩波文庫の哲学書といえば、どんな印象をお持ちだろうか。手にしたり読んだりしたことのある書目を思い出す向きもあるかもしれない。あるいは、岩波文庫を離れて、哲学書と言われて思い浮かべるのはどんな人物や本だろうか。今回から何話かを通じて、岩波文庫の哲学書に注目してみよう。
岩波文庫で「哲学」に分類されるのは、主に青帯の600番台のものである。青帯の600番台は、大きく見ると西洋哲学が中心で、その他には現代の学問や書物の分類でいうところの心理、社会、教育、政治、宗教、芸術、文学、建築、言語、歴史、生物、物理などに関する書目も入っている。近代に学術が専門分化する以前は、多様なものが哲学で扱われていたことを思い出しておこう。
ごく一部、日本語で書かれた本を除くと、ほとんどがなんらかの異言語からの翻訳書だ。翻訳元の言語は、古代ギリシア語、ラテン語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、デンマーク語、ロシア語など。西洋が中心である様子が窺える。
量はどうだろう。目下、私が把握している範囲では、青帯600番台の岩波文庫は504冊ある。ただし、この数字は改版された書目の旧版も1冊、新版も1冊と数えた場合の総冊数。例えば、プラトンの『ソクラテスの弁明』は都合5版が刊行されており、それぞれを1冊とカウントする場合には5冊となる。これに対して、新旧版や新旧訳などをまとめて1冊と数える場合、青帯600番台は357冊となる。ただし、これはひとまず集計したもので、今後修正される可能性もある。
さらに言えば、この357という数字は、分冊本の各巻をそれぞれ1冊と数えた数字だ。例えば、ルソーの『告白』は上中下の3分冊で、これを3冊と数えている。分冊された本をまとめて1点としたらどうなるか。細かく見るといろいろな場合があるので、あくまで概算だが275点となる(以上は2025年9月末時点)。これを多いと感じるか少ないと感じるかは人によるだろうけれど、この規模で哲学書が集められてきたことにまずは注目しよう。
では、どんな本が揃っているか。時代でいくつかのブロックに分けられる。大きく見ると古いほうから、古代ギリシア・ローマ、中世、ルネサンス、近代以降は世紀で区切ると、17世紀、18世紀、19世紀、そして下限は20世紀まで。古代の本は制作年がはっきりしないが、古いところではクセノポンやプラトンのものがある。最も新しいものとしては、フランスの哲学者ジャック・デリダ(1930―2004)による1990年代後半の本が2冊入っており、ざっと2400年という長きにわたっている。
時代ごとに著者を見てみよう。総勢112名で、一度に並べると名前を書くだけで終わってしまうので、まずは古代、中世、ルネサンスまでで区切ろう。生年順ではなく、著者番号順に並べてみると次の通り。ここで中世とは5世紀から14世紀あたりまで、ルネサンス期は15、16世紀としておこう。
【古代】プラトン(601〜602)、クセノポン(603)、アリストテレス(604)、ルクレーティウス(605)、エピクロス(606)、セネカ(607)、エピクテトス(608)、テオプラストス(609)、マルクス・アウレーリウス(610)、キケロー(611)、ディオゲネス・ラエルティオス(663)、プルタルコス(664)、プロチノス(669)、アテナイオス(675)
【中世】トマス・アクィナス(621)、ボエティウス(662)
【ルネサンス】エラスムス(612)、ブルーノ(660)、カンパネッラ(679)、ロレンツォ・ヴァッラ(697)
こうして見ると、古代は手厚く、中世とルネサンス期の哲学は手薄に見える。古代ギリシア・ローマが総勢14人であるのに対して、時期として1000年近くに及ぶ中世は2人、ルネサンスは4人となかなかの偏りだ。
ただし、中世哲学については、いま見ている青600番台以外の場所にも入っているものがある。例えば、青800番台の「宗教」には、アウグスティヌス、アンセルムス、エックハルト、クザーヌスなどの著作がある。中世ヨーロッパにおける哲学は、神学と重なるところも大きく、分類の仕方によってはこのように2箇所に分かれることにもなるわけだ。
それから中世に続くルネサンス期も、ペトラルカ、ボッカチオ、マキアヴェッリ、トマス・モア、モンテーニュなど、ここで名前が挙がってもよさそうな人びとは、赤帯(海外文学)と白帯(法律・政治)に分類されている。コペルニクスは青900番台(自然科学)、ルターやカルヴァンは青800番台(宗教)にいる。
もっとも、偏りというなら、ここには男性しかいないこと、古代ギリシアの知を翻訳・発展させたアラビア哲学が不在であることなど、いくつか目に留まることもある。とはいえ、哲学やその歴史の見方も時代に応じて変遷するもので、百年近くの集積でできている岩波文庫にそのまま適用するわけにもいかない。むしろ、西洋に限らない世界哲学という見方や、歴史から消されてきた女性の哲学者たちの著作を取り入れてゆくことで、岩波文庫の哲学カテゴリーを刷新してゆくという可能性に開かれていると見たい。
(やまもと たかみつ・文筆家、ゲーム作家)
[『図書』2025年11月号より]