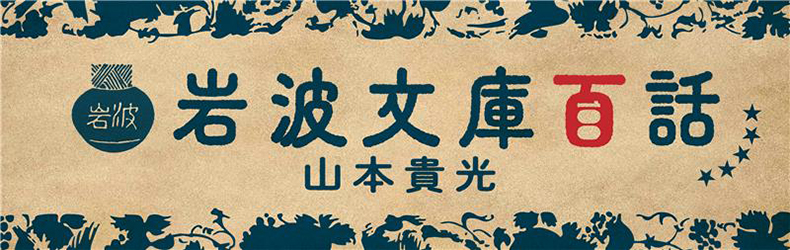第14話 17世紀哲学の重鎮たち
前話では青帯600番台「哲学」の概要と、古代ギリシア・ローマ、中世、ルネサンスという時代ごとの哲学書として誰の著作が入っているかを大きく眺めてみた。続きを見てみよう。17世紀にはどんな人がいるだろうか。
【17世紀】デカルト(613)、パスカル(614)、スピノザ(615)、ライプニッツ(616)、ベーコン(617)、ロドリゲス(681)
ここでは人物の生没年ではなく、岩波文庫に入っている著作の刊行年が17世紀である人を抽出している。これを徹底するなら、カンパネッラ『太陽の都』(1602)もここに入れるべきだが、彼はルネサンスのほうで挙げておいた。それを言うなら、ベーコンもルネサンス期と近代の境界にいた人物と見立てることもできる。だが、ここでは近代哲学の出発点に近い人として17世紀の枠に入れてみた。
人数は6人と控え目だが、この一角には西洋哲学史の近代篇で逸せないビッグネームが並んでいる。ここにいてもおかしくないトマス・ホッブズやジョン・ロックは、白帯「法律・政治」セクションに分類されている。
いま並べた6人の中で少し場違いに見えなくもないロドリゲス(1561―1634)は、イエズス会の宣教師で、戦国末期の日本を訪れ、豊臣秀吉や徳川家康とも会見する機会のあったポルトガルの人だ。岩波文庫に入っているのは『日本語小文典』(上下、池上岑夫訳、青681―1〜2、1993)で、同書はラテン語の文法をもとに当時の日本語の文法を解説したたいそう面白い言語方面の本である。当時の日本には、ここまで体系化された文法書はなく、大変貴重な試みだったが、残念ながら同書を引き継ぐ日本語文法の研究は現れなかったようだ。
その他5人の哲学者のうち、デカルト、パスカル、スピノザについては主著と呼べる本が揃っている。書き残した文章の総量で見るとこの中で最大規模のライプニッツは3冊に留まっている。工作舎から刊行された全2期13巻に及ぶ『ライプニッツ著作集』(1988―2018/第1期全10巻新装版、2018―2019)で哲学、論理学、数学、自然学、宗教哲学、中国学、地質学、法学、神学、歴史学、医学、技術、普遍学など多方面にわたる仕事の輪郭が示されていることもあり、アンソロジーでもよいので何冊かライプニッツ選集的なものが岩波文庫に入るとよいのではないか、と時々夢想している。言うは易しかもしれない。
この時代、17世紀頃の哲学者は、いまで言う自然科学(当時の言葉でいうなら自然哲学)や数学や工学などにも関心を向けていた。例えば、最初に岩波文庫に入ったパスカルの本は『パンセ』を差し置いて、『科学論文集』(松浪信三郎訳、青614―1、1953)だった。これは真空や流体に関する自然学の文章を訳出したものだ。白水社科学選書(上下巻、松浪信三郎、安井源治訳、白水社、1946―48)という2巻本の上巻として刊行された本が元になっている。円錐曲線論やパスカルの三角形など、数学の論文が収められた下巻は文庫には入らなかったようだ。この方面の文章は『パスカル 数学論文集』(原亨吉訳、ちくま学芸文庫、2014)や『パスカル科学論集 計算機と物理学』(永瀬春男、赤木昭三訳、白水社、2023)でも読める。また、岩波文庫の『パスカル 小品と手紙』(塩川徹也、望月ゆか訳、青614―5、2023)には、パスカルが生前公開しなかった遺稿や書簡が集められており、その中に彼が発明した計算機に関わるものや、自然学に関する文章も入っているので併せて読むとよい。
こんなふうに岩波文庫について述べながら、ついブックガイドのようになるのは、本が互いにつながりあっているからでもある。私は日頃、岩波文庫全体を学術マップの基礎のように使っている。日本語で読める学術の古典名著のシリーズとしては最大規模の岩波文庫を棚に並べておく。すると、それでなんでも対応できるわけではないものの、そこに並ぶ人物や書名が知識のインデックスのように使えるのだ。
例えば、前話から眺めているように、青帯600番台を順番に見ていくと、西洋哲学の大きな流れや翻訳された時代に重視されていたと思われる本が目に入る。601のプラトンから611のキケローまで古代ギリシア・ローマの哲学者が並び、612にルネサンス期のエラスムスが1人挟まって、613から先ほど眺めたデカルト、パスカル、スピノザ、ライプニッツと続く。この棚の並びを見ていると、時代順なら中世哲学やルネサンス哲学の諸家をエラスムスの前後に入れたくなったりするし、実際そのように並べてみてもよい。また、ここにまだ岩波文庫には入っていないドゥンス・スコトゥスがいてほしいとか、ピコ・デラ・ミランドラもいつかここに入ってほしいと思ったりもする。これができるのは、ベースとなるだけの書目が岩波文庫で揃っているからだ。
もう一例を挙げると、岩波文庫のスピノザは、畠中尚志訳で主著のほとんどを文庫で読めるようにしてくれたものだ。学生のころ、この一連の文庫のおかげでスピノザの哲学に近づき、またその仕事の全貌を窺うことができたのは本当にありがたいことだった。また、ここに入っていない自然学やヘブライ語に関する本を読みたいと思い、ゲプハルト版全集その他を手にするきっかけともなった。現在刊行中の『スピノザ全集』(全6巻 別巻1、岩波書店)を読んでいるのも、もとはといえば岩波文庫で親しんでいたからである。
そういえば、第13話と第14話で名前の挙がった青帯の哲学者のうち、プラトン、アリストテレス、セネカ、キケロー、スピノザについては、いずれも岩波書店から全集や選集が刊行されている。岩波文庫は、哲学の歴史的な展開を大きく見渡す手がかりになるとともに、そうした全集類やさらにはその原典へとつながる入口にもなる。そんなこともあって、集めて並べておきたくなるのだった。
(やまもと たかみつ・文筆家、ゲーム作家)
[『図書』2025年11月号より]